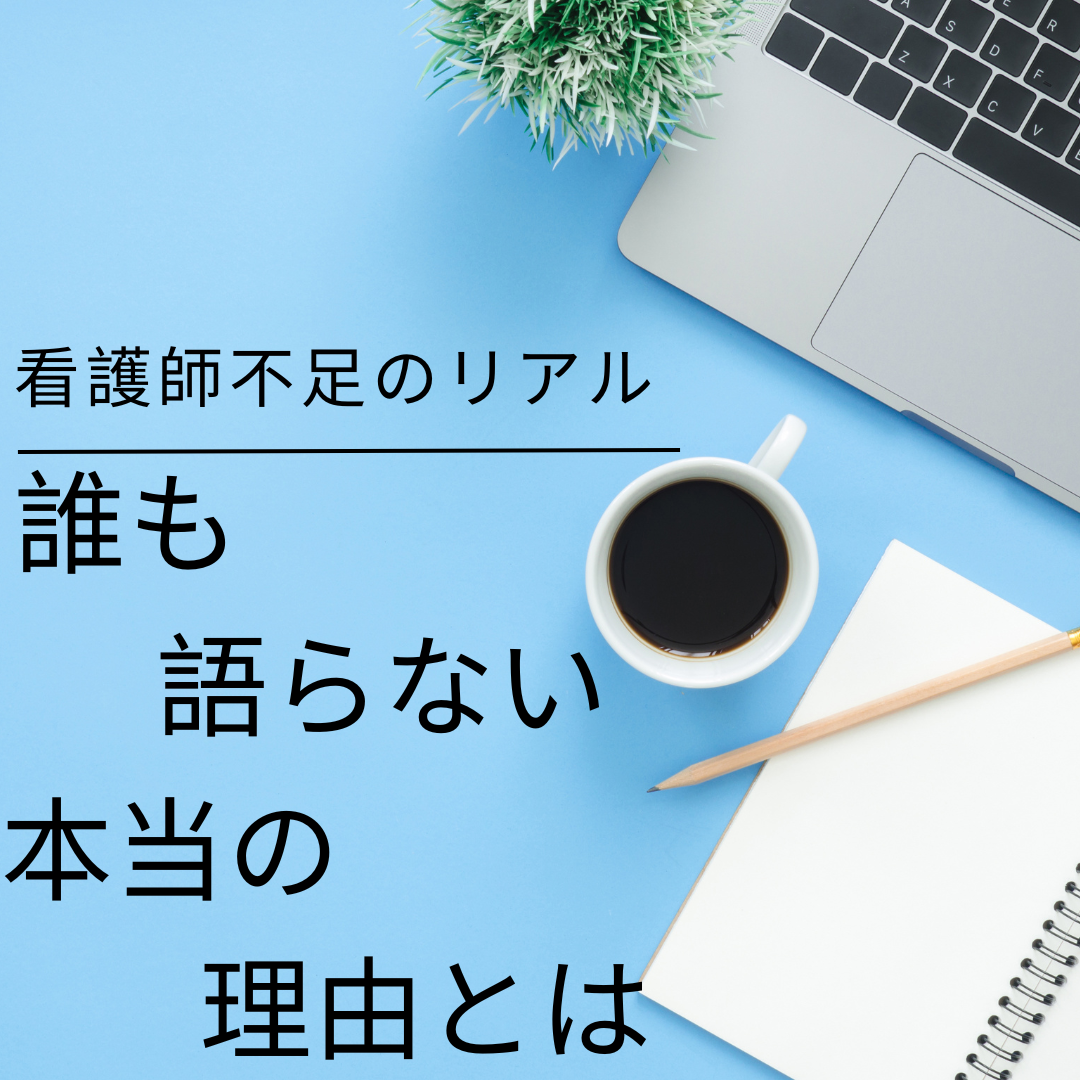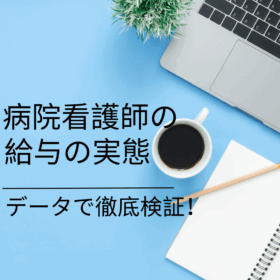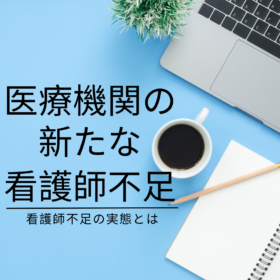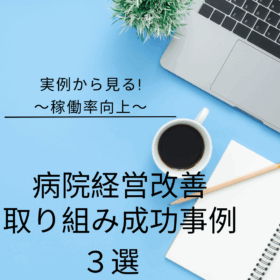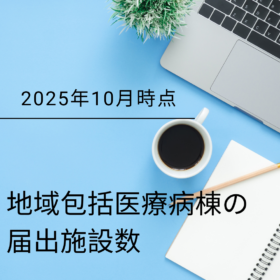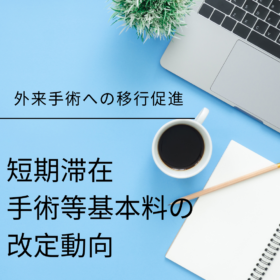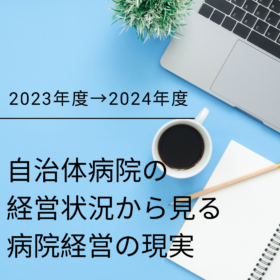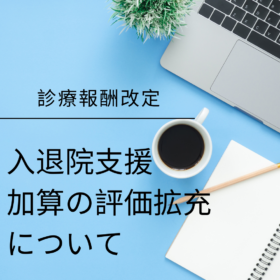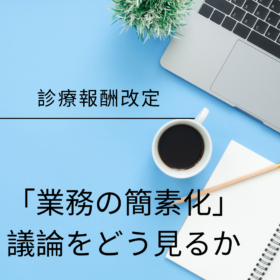Contents
看護師不足が医療現場にもたらす深刻な影響とは?
近年、「看護師不足」という言葉をニュースなどで耳にする機会が増えています。実際、今の病院現場では、看護師の不足が深刻な課題となっており、その影響は現場のスタッフの働き方だけでなく、病院経営や患者への対応にも及んでいます。
この記事では、病院が直面している看護師不足の実態を、コンサルティングの現場で得られた知見を交えながら丁寧に解説しています。
筆者が支援している複数の医療機関においても、看護師不足は避けられない問題となっており、さまざまな対応策を講じているのが現状です。まずは、看護師や看護職員の確保に関する最新データを確認しつつ、実際に現場でどのようなことが起きているのかを見ていきます。
看護職員の数は増えているのに、なぜ現場は足りないのか?
まず初めに注目すべき点は、看護師全体の人数自体は年々増加傾向にあるということです。看護職員の確保が進められて、看護職員就業者数は増加を続け、2020年(令和2年)には173.4万人となりました。
単純な数の上では人手が増えているはずです。しかし、その一方で医療現場では「人が足りない」「シフトが回らない」といった声が後を絶ちません。
この矛盾の背景には、単なる数の問題ではなく、働き方や人員配置に関する新たな課題が潜んでいます。特に夜勤体制の維持が困難になってきていることや、働ける時間帯に偏りが出ていることなど、看護師の勤務条件に関する問題が浮き彫りになっています。
また、看護師の年齢層にも変化が見られます。看護職員の平均年齢は上昇しており、若年層の割合が減少し、60歳以上の構成割合が増加していっています。
これが人手不足の要因のひとつにもなっています。若い世代の看護師が夜勤を避けたり、短時間勤務を選ぶ一方で、年齢を重ねた看護師は体力的な問題から勤務に制限が生じやすくなっているのです。
地域差が生む人材供給の偏り
看護師不足の問題は、地域によっても状況が大きく異なります。例えば、神奈川、東京、千葉、埼玉、群馬など、首都圏に位置する県では、人口10万人あたりの看護職員数が全国平均を下回っているというデータがあります。一方で、地方の一部では全国平均を上回る数の看護職員が存在しており、都道府県ごとに供給のばらつきがあることがわかります。
また、看護師の有効求人倍率にも注目すべきです。全体の職種と比べても、看護師の求人倍率は明らかに高く、人材の需要に供給が追いついていないことが示されています。これは、特定の地域や病院において深刻な看護師不足が起きている現実を裏付けています。
さらに、2025年の時点で看護職員の需要が供給を上回ると予測されている都道府県もあります。特に首都圏や関西圏では、人材の確保が今後さらに難しくなる見込みです。2040年には、少子高齢化の進行に伴って看護職員の需要が一層高まり、状況はさらに深刻になると予測されています。
病院経営に直結する看護師不足のインパクト
看護師不足が病院経営に与える影響も見過ごすことはできません。人員が確保できないと、病床の稼働率を維持できなくなり、結果として病床の縮小や一部閉鎖、最悪の場合は病院全体の経営にも影響を及ぼすリスクがあります。患者の受け入れを制限せざるを得ない状況に陥ると、地域医療の機能が弱まり、患者にとっても不利益となるのです。
また、経営面での打撃は単に収益の減少にとどまりません。人手が不足している状態で無理な運営を続けると、現場の職員の負担が過剰となり、離職やモチベーションの低下を招く悪循環にもつながります。
こうした状況を打開するには、「人を増やす」だけではなく、「今いる人材でどうやって現場を回すか」という視点がますます重要になります。人材確保と同時に、人員配置や業務効率化などの戦略的な取り組みが求められているのです。
見えてきた「新しい人手不足」という構造的問題
看護師不足というと、「単純に人数が足りない」というイメージを持たれがちですが、現場で実際に起きているのは、従来とは異なる“新たな人手不足”です。これは、単なる人手の数の問題ではなく、働ける「時間帯」や「シフト構成」に偏りが生じていることで、必要な時に必要な人員が確保できないという状況を指します。
たとえば、病院によっては入院基本料に基づく基準人数を上回る看護師を確保しているケースもあります。にもかかわらず、「夜勤シフトがどうしても回らない」といった声が聞かれるのです。つまり、数字上では足りていても、実際の勤務可能な条件と現場のニーズが一致していない「ミスマッチ」が発生しており、これこそが現在の「質的な人手不足」の本質だと言えるでしょう。
このような状況では、ただ看護師の数を増やすだけでは根本的な解決にはなりません。勤務体系や働き方の見直し、そして人材の適切な配置が求められる時代になっているのです。
夜勤体制が崩れる4つの要因とは?
では、なぜ現場で夜勤が組めなくなっているのか。ここではその原因として考えられる4つの要因について詳しく見ていきます。
1. 働き方改革による就労条件の多様化
まず最初に挙げられるのが、「働き方改革」の影響による就労条件の多様化です。現代では、子育てや介護、個人のライフスタイルに応じて、看護師の働き方が大きく変化しています。たとえば、20代~30代の看護師は結婚や出産を機に短時間勤務や時短勤務を希望することが多く、40代では育児と仕事の両立、50代では親の介護や自身の健康問題が背景にあります。
このように、それぞれのライフステージに応じた柔軟な働き方が選択できるようになったことは、とても良いことです。しかし一方で、夜勤を担える看護師が相対的に減っているという現実があります。短時間勤務が普及すればするほど、フルタイムでの夜勤シフトが回らなくなるという問題が浮上してくるのです。
2. 新人看護師の夜勤対応までに時間がかかる
かつては、新人看護師が入職してから数か月で夜勤デビューを果たすことが一般的でした。しかし最近では、安全面や教育体制の変化により、夜勤への一人立ちに時間がかかる傾向が強くなっています。
実際、新人看護師が夜勤に入れるようになるまで半年以上、時には1年近くかかることもあります。これは新人教育としては理にかなっていますが、現場の人手不足の補充という点ではタイムラグを生んでしまい、結果として「夜勤に入れる人が増えない」という事態に直結してしまいます。
3. 看護師の高齢化による勤務制限
続いての要因は、看護師の平均年齢の上昇に伴う「体力的な制限」です。これまで夜勤を担ってきたベテラン看護師たちも、年齢を重ねることで夜勤が困難になってきているという実態があります。
もちろん、こうしたベテラン層が引き続き日勤帯で経験を活かして活躍してくれていることは、病院にとって大きな財産です。しかし、夜勤シフトを支える主力層が徐々に少なくなっていることで、若手や中堅への負担が集中するという新たな歪みが生まれています。
4. 夜勤72時間ルールによる制限
最後に重要な制度として、「夜勤72時間ルール」があります。これは、看護師1人あたりの月平均の夜勤時間を72時間以内に抑えるという規定で、2006年度の診療報酬改定によって導入されました。
このルールは、看護師の健康や安全を守るために設けられたものですが、平均値での制限という特性上、夜勤を免除された人や夜勤回数が少ない人の分を、残された現役世代がカバーする必要があるという現象が起きています。結果的に、夜勤をこなせる人への負担が過剰になってしまい、それがさらなる離職やシフト組みの困難さへとつながっているのです。
医療現場の変化がもたらす「相対的な人手不足」
看護師の人数が増えているにもかかわらず、現場では「人が足りない」という感覚が根強く残っています。その背景には、医療現場自体の変化によって、求められるケアや業務の内容が大きく複雑化していることが挙げられます。つまり、看護師一人あたりの業務負担が、以前と比べて重くなっているのです。
たとえば、入院患者の高齢化が進んでいることは顕著です。かつては50代〜60代の患者が中心だった病棟でも、現在では平均年齢が70代後半から80代近くになってきています。高齢の患者が増えると、認知症や複数の持病を抱えていることが多くなり、日常生活の多くをサポートしなければなりません。トイレの誘導やおむつ交換、食事や入浴の介助など、ケアの手間が大きく増加しているのです。
そのため、仮に患者数と看護師数が過去と同じであっても、実際の業務量は圧倒的に増えており、現場にかかる負担は一層重くなっています。これが、看護師不足が「質的な問題」と言われるゆえんでもあります。
入退院短縮が業務を加速させる
加えて、医療制度改革の影響により、急性期病院を中心に入退院のスパンがどんどん短縮されていることも、大きな業務負担の要因です。入退院が早くなるということは、それだけ患者の入れ替えが激しくなることを意味し、それに伴う準備や手続きも多くなります。
現在の医療現場では、入院にあたっての同意書や診療計画書、手術・検査に関する書類などが多数存在しており、1人の患者に対して必要な書類対応が非常に煩雑になっています。また、高齢患者が増えたことによって、家族への丁寧な説明や本人へのサポートも欠かせません。
これらの業務はすべて、看護師の貴重な時間と労力を必要とするものであり、医療そのものとは別の「書類仕事」や「対人対応」が現場の大きな負担となっているのです。
タスクシフトの遅れと現場のジレンマ
このような背景から、国は医療現場での「タスクシフト」を積極的に推進しています。タスクシフトとは、看護師でなくてもできる業務を、看護補助者などの他職種に移行させることで、看護師の負担を軽減しようという取り組みです。
しかし現実には、まだまだこのタスクシフトが十分に進んでいないのが実情です。医療的判断が求められる場面が多いことや、そもそも「任せるより自分でやった方が早い」という現場の心理的な抵抗感も大きな壁となっています。
また、業務を委譲することでミスが起きた場合、その責任を負うのは看護師自身であるという不安も根強く残っており、それがさらなるタスク移行の障害となっているのです。
一方で、看護補助者の採用数自体は増えてきています。にもかかわらず、実際に移行された業務の範囲は限られており、現場での看護師の負担軽減にはまだつながっていないというギャップが存在します。
今後に求められるのは「配置」と「働き方」の最適化
ここまで見てきたように、現代の看護師不足は、単純に「人がいない」という話ではありません。むしろ、人材の配置や働き方のミスマッチによって、「いるのに回らない」現象が起きているのです。
看護師のライフステージや体力的条件、夜勤可能な年齢層の変化など、さまざまな事情を踏まえた上で、どのように適切なシフトや業務分担を設計していくか。病院経営や人事戦略の中核に、こうした「現場に即した柔軟な仕組み」を取り入れていく必要があります。
また、タスクシフトを成功させるには、単に業務を割り振るだけではなく、補助職員の教育や現場全体の信頼関係づくりも不可欠です。「チーム医療」の意識を持ち、誰もが安心して役割を担える環境を整えることが、これからの病院運営のカギを握っていると言えるでしょう。
終わりに―「数」ではなく「機能」が問われる時代へ
今後、少子高齢化がさらに進む中で、医療現場ではより一層の人手不足が予測されています。しかしそれは単に「看護師を増やせばよい」という話ではありません。どのようにして既存の人材を活かし、組織として最大限の機能を果たすかが重要です。
働く看護師一人ひとりが無理をせず、それでも質の高い医療を提供し続けられるような仕組みづくりこそが、今最も求められているのではないでしょうか。
看護師不足という複雑で根深い問題に対して、現場の声とデータを元に冷静に向き合い、現実的な対応策を模索していくことが、私たちの社会全体にとっても大きな意味を持つはずです。