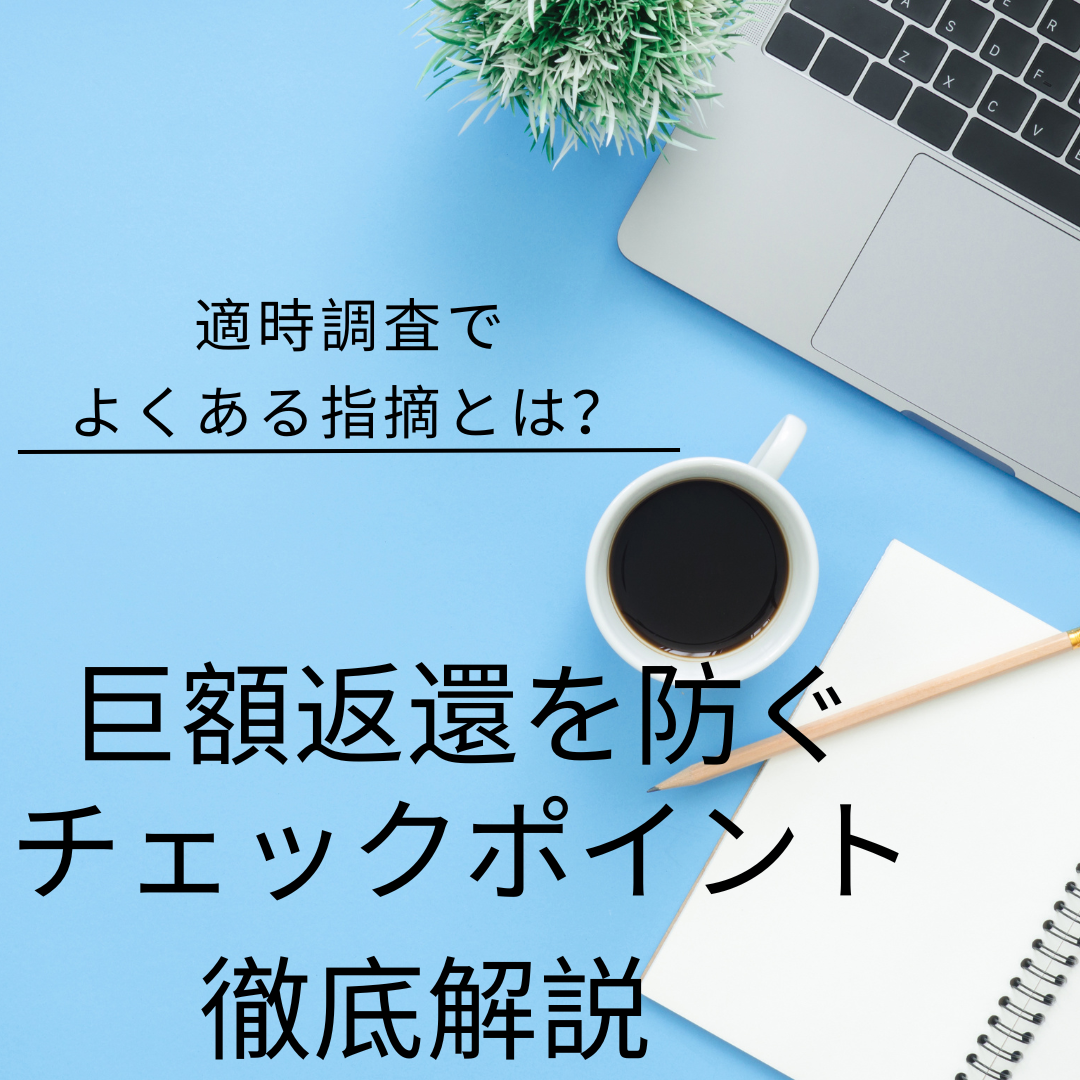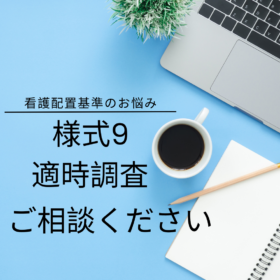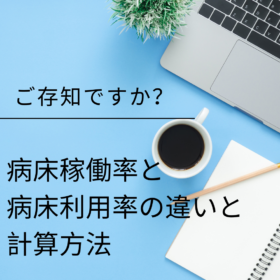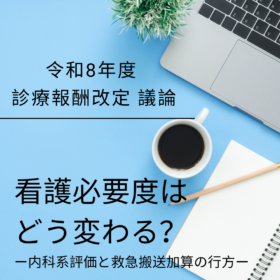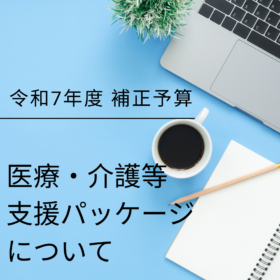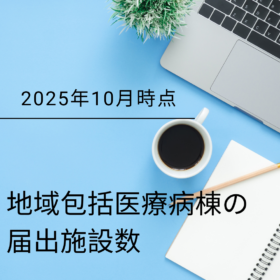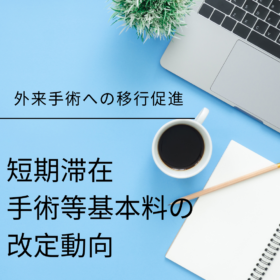Contents
適時調査による巨額返還が起こる理由とは?
医療機関や福祉施設を運営していくうえで、避けて通れないのが「適時調査」です。これは厚生労働省や地方厚生局が行うもので、診療報酬を算定するための“施設基準”が、現場できちんと守られているかどうかを確認するために実施されます。
例えば、人員配置や施設の設備、掲示物の内容などが基準に沿っているか、あるいは申請した加算内容が実際の運営と一致しているかといった点が厳しくチェックされます。この調査で問題が見つかると、業務の改善を求められるだけでなく、診療報酬の返還を命じられることもあります。
しかも、返還額は数百万円から、時には数千万円、場合によっては数億円にものぼることもあり、医療機関の経営に大きな打撃を与えかねません。こうした事態を防ぐためにも、事前に「適時調査ではどんな項目が指摘されやすいのか」を知っておくことがとても重要です。
適時調査はなぜ怖い?
医療や福祉の現場で「適時調査が入る」と聞くだけで、緊張感が走るというのはよくある話です。というのも、ほんの少しのルールの理解不足や、軽微な事務ミスが原因で、何百万~何千万円、時には数億円の返還を求められるケースがあるからです。
この調査では、あくまで「申請内容と現場の実態が合っているか」が重視されます。ですから、たとえミスが意図的でなくても、制度上は「不適切な請求」「不正な請求」とみなされてしまうリスクがあるのです。
実際にあった例としては、
・「月に1回実施が必要な会議を開いていなかった」
・「勤務時間に、研修や委員会の活動時間を含めてしまっていた」
といった、いずれも現場では“よくあること”と感じてしまいそうなミスが、返還対象として指摘されたケースが多数報告されています。
また、制度の解釈を間違えていたり、部門同士の連携ミスがあったり、職員の異動にともなう届出を忘れていたりと、日常業務の中に落とし穴が潜んでいることも少なくありません。こうした不備は、気づいたときにはすでに手遅れになっていることもあり、結果的に莫大な金額の返還命令を受けてしまうケースもあるのです。
適時調査とは?
適時調査とは、医療機関や介護施設が申請している施設基準や加算の届出内容と、実際の運用状況が一致しているかどうかを厚生労働省または地方厚生局が実地で確認する調査を言います。この調査は事前に予告があり、書類提出と現場確認がセットで行われる定期的な指導・監査としての意味を持ちます。特に下記のような項目が重点的に確認されます。
・看護配置基準
・夜勤体制
・研修の実施状況
・職員の勤務実態と届出との一致
また、適時調査=罰するための調査ではなく、制度の適正運用を促し、是正の機会を提供することが本来の目的となります。しかし実際には、不備が見つかった場合、返還処分や施設基準の届出の取り下げが命じられることもあります。調査対象となった施設の経営に大きな影響を及ぼすことも考えられます。
適時調査の流れとは?
適時調査の流れは、基本的に以下のようなステップで進行します。
1、調査対象の通知
まず、厚生局や保険者から文書で調査実施の通知が届きます。調査日程や調査範囲、提出書類のリストが記載されており、通常は1か月の準備期間が与えられます。
2、書類の事前提出
通知を受けた施設は、調査前に必要書類を提出します。ここでは勤務表や職員名簿等が求められます。書類が揃っていない、もしくは内容に齟齬がある場合は、調査当日の質疑でも不利になる可能性が高くなります。
3、現地調査(実地確認)
調査員が施設に訪問し、現場の運用が一致しているかを確認します。ここでは、実際の職員配置、業務内容、職員への聞き取り等が行われます。虚偽申請や過失による不整合がないかが細かくチェックされます。
4、調査結果の通知
調査終了後、調査報告書が作成され、数週間以内に指摘事項とともに通知されます。指摘内容に応じて、加算取り下げ、返還命令、改善指導が行われることになります。
適時調査の中でよくある指摘事項とは?
適時調査では、各施設の実態と届け出内容の整合性が厳しく確認されます。その中で、特に頻繁に見られる指摘事項は以下の通りになります。
1、看護配置基準の不備や用語の混同
・夜間看護配置が不足している(解釈を誤認している)
・各病棟に3名以上の看護職員が配置されていない
・12対1、16対1などの配置基準を満たしていない日がある
これらは、巨額の返還につながりかねません。また、看護師・看護職員・看護要員の用語を見間違えたことで、多額の請求をされることもあり得るのです。
2、72時間ルールの違反
勤務表の管理ミスや研修・委員会、もしくは申し送り時間等の時間の取り扱いにも注意が必要です。
3、届け出内容と実態の不一致
・異動や退職後の人員変更が届け出に反映されていない
・届け出た業務と実際の配置業務が異なる
・兼務可能な業務と兼務不可能な業務があることが理解できていない
上記のような場合は、意図的ではなくても指摘対象となるのです。
4、研修・加算要件の誤解
・看護補助者に対する必要研修が施設基準通りの運用ができていない
・必要な研修修了者が配置されていない
・入退院支援加算、入院時の支援加算、患者サポートの体制充実加算などは人員配置基準に誤解を生じやすい
・専任と専従の用語の理解が不十分となっている
5、通則で減算対象となった項目
・身体的拘束の最小化の取り組み
・栄養管理体制の基準
これら2つは、2025年度以降さらに巨額な金額になってしまう可能性があります。
まとめ
適時調査は「ルールを守れているか」を確認するための制度ですが、現場のわずかな勘違いや記録の不備が、大きな返還リスクに直結するという特徴があります。適時調査がある時だけに限らず、普段からいつ調査されても大丈夫な状態を保っておくことに越したことはありません。
「知らなかった」や「うっかりしていた」では済まされない制度であるからこそ、以下のポイントを日頃から徹底することが大切なのです。厚生労働省が出している適時調査実施要領等の中身をよく確認しておきましょう。
・職員への周知と定期的な研修
・届出内容と現場実態の定期照合
・基準の正しい理解とマニュアル整備
・職員異動・退職時の情報更新の徹底
また、制度の改定や運用の厳格化により、今後も調査内容はさらに複雑で詳細なものになっていくことが予想されます。調査は罰則ではなく見直しの機会として捉え、適時調査に備えることが医療現場の健全な運営につながります。
毎年、各施設の基準が8月1日現在において、届出基準を満たしているか否かを自己点検する機会があります。その際には、研修や異動などに特に注意し確認しておくことが重要になります。