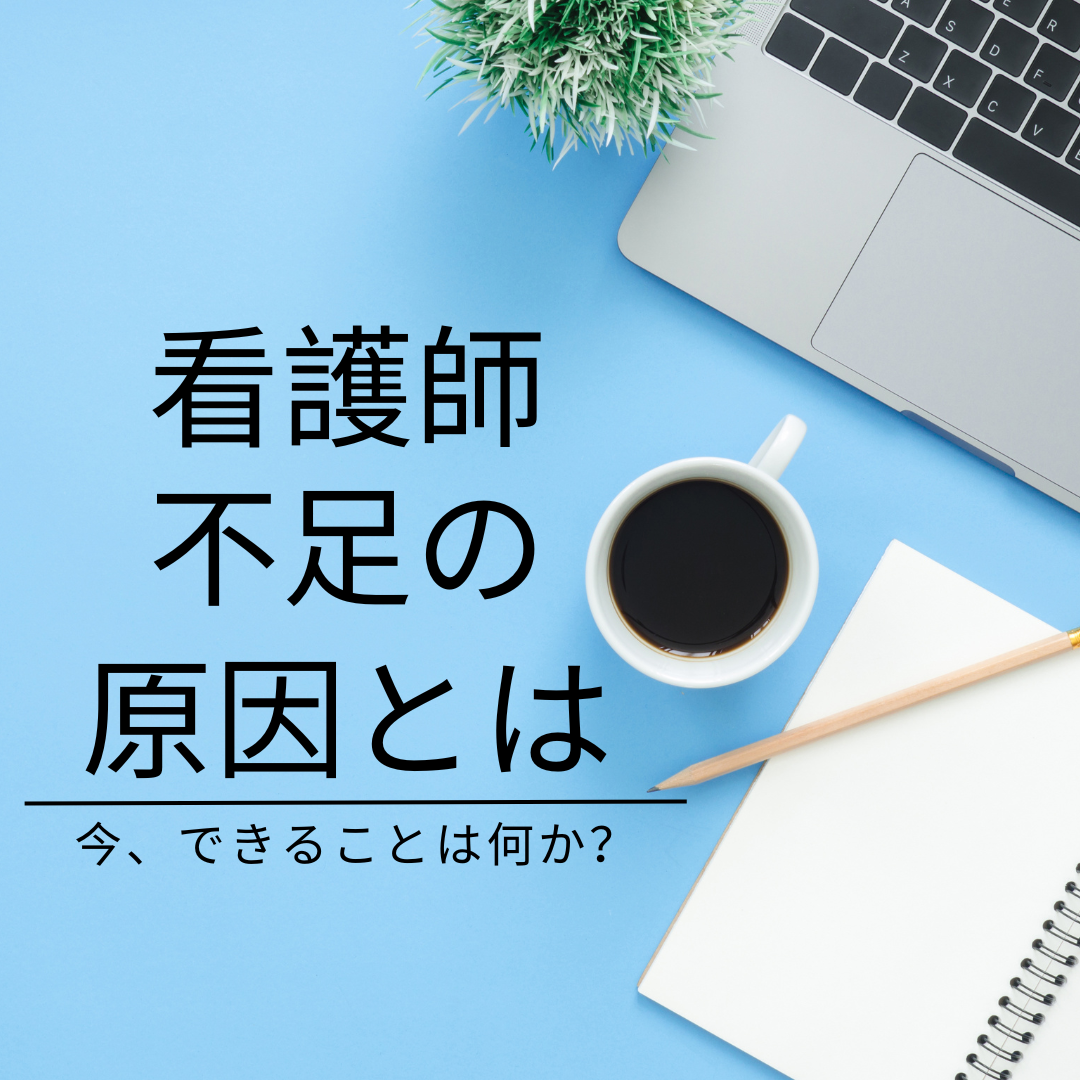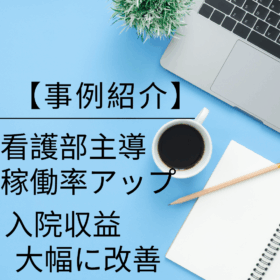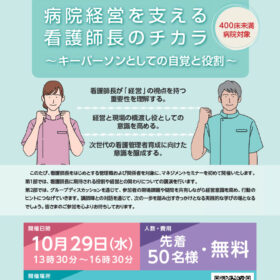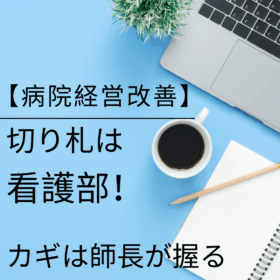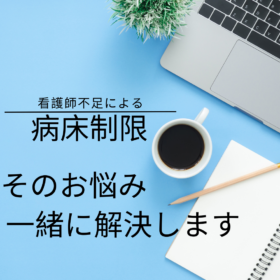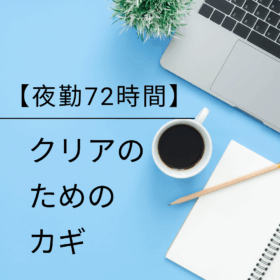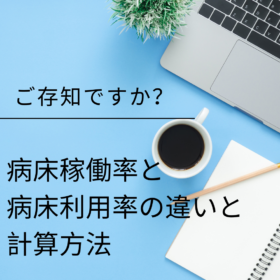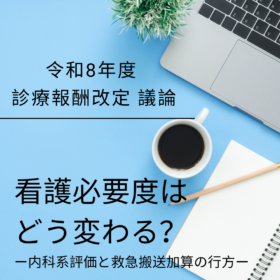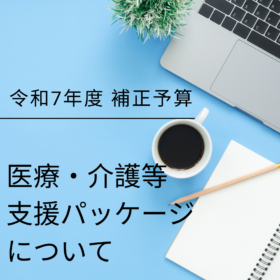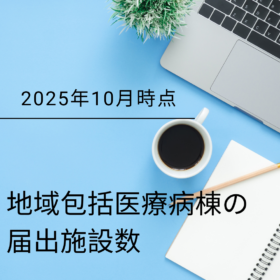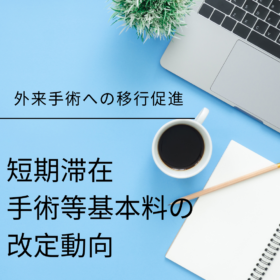医療機関において看護師は重要な役割を果たします。現在でも医療・看護業界では少子高齢化の影響を強く受けていますが、新型コロナウイルスの蔓延や少子高齢化、人口減少などに伴い、今後、看護師の需要はさらに高まっています。2025年には日本の総人口における65歳以上の比率が30%ほどに達し、2060年には40%ほどを占めるといわれています。今後さらに在宅医療のニーズも増え続け、在宅医療の利用者も増加することが予想されているため、今後ますます看護師の人手不足は深刻化していくでしょう。
そのような中、病院や在宅医療(訪問看護など)における看護師不足が問題視されています。看護師不足が原因で病床制限、病床縮減へと追い込まれている医療機関もあります。では、一体なぜそこまで看護師の人手不足が深刻化してしまっているのでしょうか。また、看護師の人手不足を解消するには一体どうすればいいのでしょうか。
この記事で詳しく解説していきます。
Contents
看護師不足の現状とは?
看護師の人手不足は全国的に問題視されていますが、具体的にどの程度不足しているのでしょうか。
以下、現状と今後の展望について解説します。
看護師の有効求人倍率は約2倍
厚生労働省が発表している「看護師等(看護職員)の確保を巡る状況」によると、2022年の看護師(保健師・助産師含む)の有効求人倍率は、年間を通して約1.9~2.5倍となっています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時期はやや有効求人倍率が下がったものの、現在においても2倍を下回ることがほぼありません。有効求人倍率が約2倍ということは、募集に対して半分もしくはそれ以下の人数しか募集がないということです。
この数値からも、現状の看護師不足の深刻さがうかがえます。
2025年には最大27万人もの看護師が不足する?
現時点でも看護師の人手不足はかなり深刻化していますが、2025年にはさらに状況が悪化するといわれています。厚生労働省は、2025年までに188万人~202万人の看護師が必要だと予想していますが、現実的に見ると175万人~182万人に留まる可能性が高いと推定されています。
つまり、2025年には最大27万人もの看護師が不足する恐れがあるということです。(参考:厚生労働省「看護師等(看護職員)の確保巡る状況」)
世界的に見る日本の看護師不足問題
新型コロナウイルスの感染拡大後、今なお、インフルエンザや新型コロナウイルによる感染症の影響は強く、現在では各国で看護師不足が問題視されています。その中でも、特に日本の看護師不足は深刻です。理由はいくつかありますが、大きな要因の1つは、「病床数過多」です。
日本医師会総合政策研究機構が発表した「医療関連データの国際比較」によると、日本の病床数は16,553,234床であり、人口1,000人あたりに対して13.1となっております。この数字は、先進国の中でもトップクラスの病床数で、この病床数の多さが、看護師不足を加速させてしまっているのです。
看護師不足の原因として考えられること(看護師の適正人数の検討)
今紹介したように、日本で看護師不足が進んでいるのは「病床数の多さ」が関係しています。病院は保険診療が主であり、その収入源は診療報酬で定められています。そのため、各診療における対価(請求金額)を各病院ごとに自由に設定することはできません。それどころか、入院収益を得るためには、その価格(入院料)を患者さんに請求するために、「施設基準」というルールを遵守する必要があります。
そのルールの中の1つに、入院基本料を算定するために設けられている看護配置基準というものがあります。この看護配置基準は、届け出ている入院料によって、7対1や10対1、13対1基準などがあります。そのため、多くの病院では、病床数に対し看護師を配置しようとする傾向があり、病床数が多いと、看護師の必要人数が相対的に多くなる傾向があります。よって、看護師不足が生じるのです。
しかしながら、多くの病院では病床稼働率が下がってきており、稼働病床に対して入院している実際の患者数は減少傾向にあります。それにも関わらず、病床数に対し、看護師数を配置しようとして、看護師不足と認識していることがあります。
看護師不足の原因として考えられること(夜勤看護師の不足)
また、看護師の数は充足しているけれども、夜勤の出来る看護師が不足していることによって、「看護師不足」が生じている病院も多々あります。入院患者は365日24時間体制で看護を必要としてます。そのため、夜勤の出来る看護師の確保をすることが必須です。しかしながら、子育て世代や介護世代に突入した職員はなかなか夜勤をすることが難しく、夜勤のできる看護師の確保ができず、入院患者数の制限を余儀なくされている病院が有ります。夜勤の看護体制を適正化し、病床数の検討を行うことは、非常に重要です。
さらに、入院病棟に配置する看護師以外にも、病院では、外来、手術室、透析室などへの看護配置も必要です。その為、病院全体で看護師が果たして何人必要なのかよくわからないまま、適正に配置されているのかどうかもわからぬまま、看護師不足と認識していることもあります。
看護師不足について各病院で検討する際には、適正配置、適正人数、夜勤の看護体制、先を見越した人員確保、シルバー人材の活用方法の検討などを考えていく必要があります。人件費高騰の昨今、看護師不足を現場の声だけで話すのではなく、数字根拠と共に、現場の運用状況を加味して、検討していく必要があります。昨今の看護師不足、そして今後さらに深刻化していく可能性のある看護師不足の中、病院経営においてやるべきは、今の看護師の数で、もしくは今後の各病院における看護師数の推計で、どうやって病床の最大化を図るのか、もしくは、縮小した病床数では何人の看護師まで減らしてもいいのか、そういった現実的な数字を見て、看護師数の最適化、病床数の最適化を考えていくことです。
看護師不足の原因として考えられること(離職率の高さ、子育て世代が働きにくい環境)
また、看護師の離職率の高さも問題です。特に看護業界は、その他の業界に比べて離職率や求職率が高い傾向にあります。令和5年の7月7日に発表された「看護師等(看護職員)の確保を巡る状況」によれば、以下のような理由で退職する看護師が増えているようです。
・結婚→11.6%
・子育て→10.5%
・転居→9.1%
・妊娠・出産→8.8%
・自分の健康(主に精神的理由)→7.4%
・看護職の他の職場への興味→7.2%
・親族の健康・介護→6.7%
・配偶者の転勤→6.5%
・勤務時間が長い・超過勤務が多い→5.4%
・夜勤の負担が大きい→4.9%
看護師はその他の業界に比べて定着率が低く、このようなことも人手不足に拍車をかける原因となっています。実際に、日本医療労働組合連合会が2017年に行った「看護職員の労働実態調査」では、約74.9%の看護師が仕事を辞めたいと回答しています。
当然、看護師の不足は1人1人の看護師の業務量を増大させます。日本看護協会が行った「看護職員実態調査2021」では、2021年の1か月間の平均超過勤務時間が17.4時間であり、78.4%の看護師が超過勤務を行ったとされており、超過勤務が常態化している現状がうかがえます。そうなれば、子育て世代は保育園のお迎えなどの事情で働き続けられなくなり、離職に繋がるという負の連鎖が起きているのです。
看護師不足が引き起こすリスクとは?
看護師不足が続くと、以下のようなリスクが高まります。
・現場の負担が大きくなり負の連鎖を引き起こす
・医療ミスのリスクが高まる
・病床制限、病床縮減、病棟閉鎖や閉院に繋がる
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
現場の負担が大きくなり負の連鎖を引き超す
看護師不足が続くと、それに伴って1人あたりの負担が大きくなり、離職率や休職率の増加に繋がります。そうなれば、さらに人手不足が深刻化してしまい、状況が悪化する可能性が高くなるのです。
医療ミスのリスクが高まる
看護師の人手不足が顕著になり、1人あたりの負担が大きくなれば、医療ミスのリスクが高まります。精神的あるいは肉体的な疲労により正常な判断ができなかったり、診察補助においてミスをしてしまったりと、患者の命や健康にかかわる問題に発展するケースもあります。その責任感の重さに耐えられなくなり離職がさらに加速するリスクがあります。
病床制限、病床縮減、病棟閉鎖や閉院に繋がる
看護師の人手不足は、医療機関の病床制限、病床縮減、病棟閉鎖や、さらには閉院に繋がる可能性もあり、病院経営においては重大な問題です。実際に、看護師不足により経営の危機に陥っている医療機関は少なくありません。
看護師不足に対し、今、できることは?すべきことは?
看護師不足の中、各病院では、
・看護師の適正配置を検討、把握する
・病床の適正数を考える(収支計算)
・各病棟の病床機能を再検討する
今の看護師の数でどのようにして病床の最大化を図っていくのか、あるいは縮小した病床数では何人まで看護師を減らしていいのかを考えながら、最適な施策を考えていくことが大切です。また、現在の病床機能は果たして地域のニーズと合致しているのかなどを2035年~2040年に向けて考えつつ、今年、来年の病院経営の在り方を考えていく必要があります。その中で各病院の看護師配置の適正化は避けられない議論です。
「なぜできないか」を言い合うのではなく、「どうしたらできるのか」を病院全体で考えることにより、看護師不足の中、持続可能な病院経営を考えるための「本質的な対策」を行えるようになります。
まとめ
看護師不足が深刻化している昨今では、経営の危機に直面している医療機関が増えています。看護師の業務量の多さや責任の重さ、不規則な生活や少子高齢化など、看護師不足に陥っている原因には様々なものがあるため、まずは原因を解明しつつ、適切な対策を行っていくことが大切です。看護師不足を解消するには、待遇改善や業務負担の見直しなどがありますが、その中で最も注意すべきなのが「看護師の適正配置と病床数の適正化、および、病床機能の再検討(病床再編の検討)」です。
安易に病床数を減らしてしまうと、経営に大きなダメージが加わり、事態が悪化してしまう可能性があります。一方、だからと言って、看護師は簡単には増えないですし、増やせたとしても人件費が高騰します。もちろん、状況によっては病床数の削減も1つの選択肢となりますが、まずは適性を考えながら、病床の機能の返還(病床再編)も検討しながら、2035年~2040年に向けた病院の方向性を検討していく必要があります。