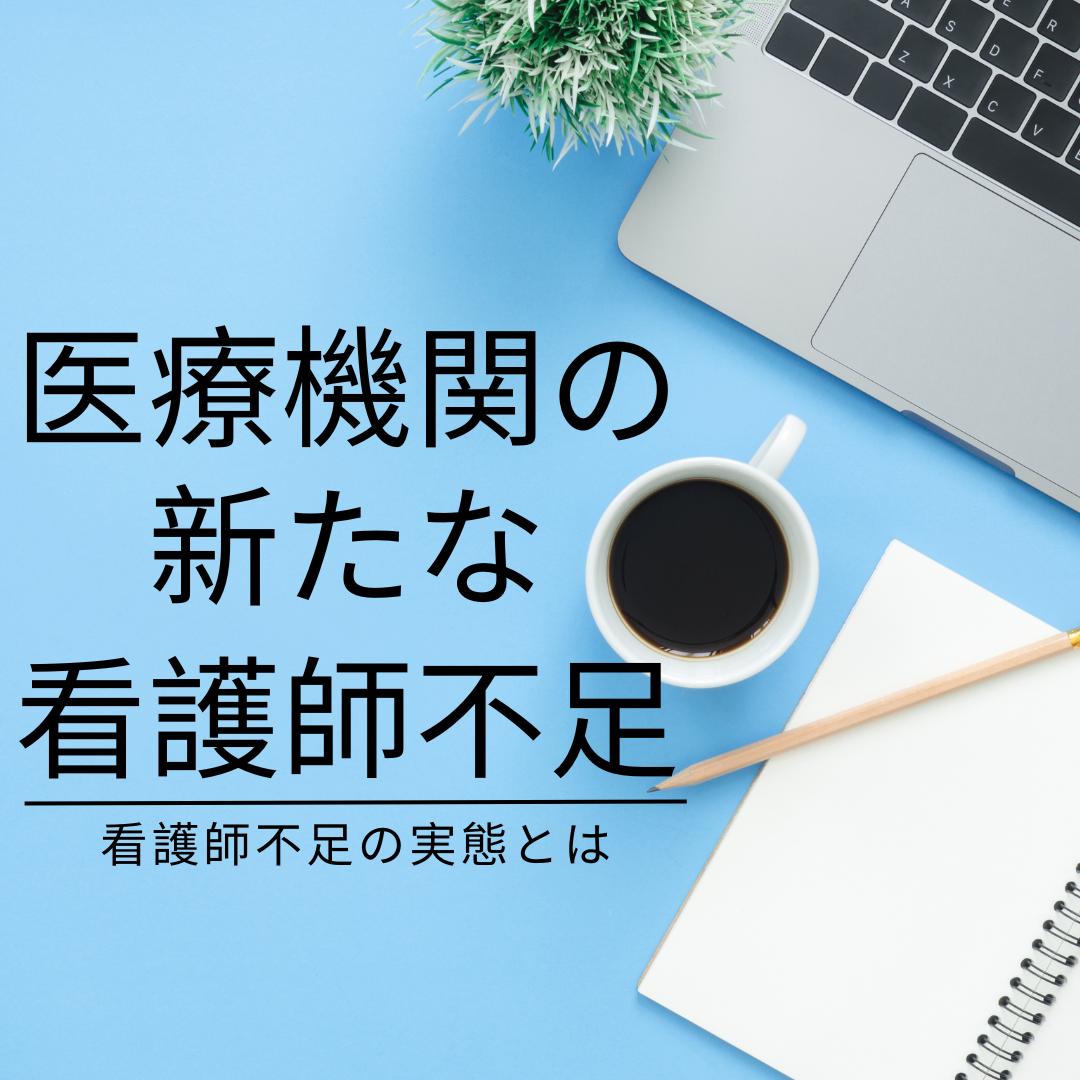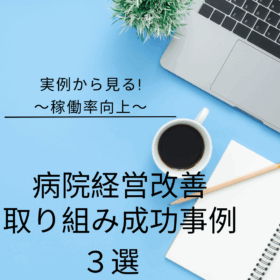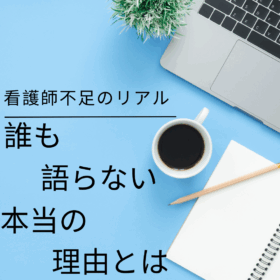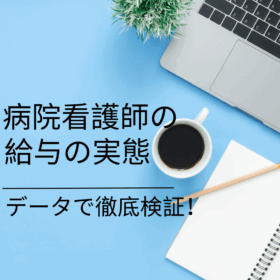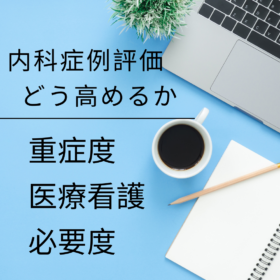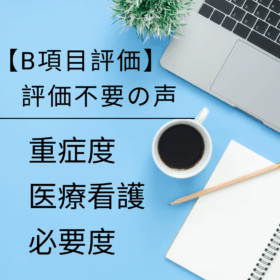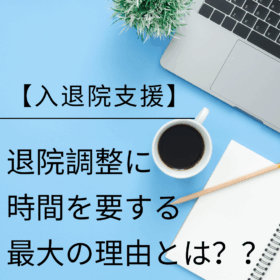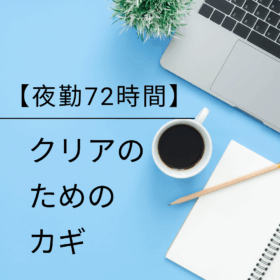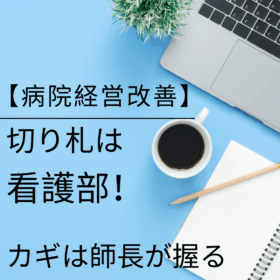看護師の人手不足は、高齢化が進んで看護のニーズがますます高まっている現在の日本において大きな課題のひとつです。個々の病院においても、『シフトが組めない』『夜勤対応できる看護師が不足している』など、看護の現場からの悩みを耳にすることが増えているのではないでしょうか?
Contents
看護師の数は増えている?
この人手不足、単に「看護師の数が少ないから」だと思われがちですが、実はそう単純な話ではありません。事実、看護師の数は年々増えており、2010年には約132万人だった看護師数は、2020年には157万人を超え、10年で約24万人増加しています。それにもかかわらず、厚生労働省の推計では、2025年には最大で27万人もの看護師が不足する可能性があるとされています。この矛盾した状況の背景には、単純な人数の問題にとどまらない、構造的な課題が潜んでいるのです。
看護師の有効求人倍率は職業全体の約2倍
人手不足の深刻さを裏付ける指標として、「有効求人倍率」があります。以下のデータをご覧ください。
| 年度 | 職業全体 | 看護師 |
| 2020年 | 1.01倍 | 2.05倍 |
| 2021年 | 1.05倍 | 2.12倍 |
| 2022年 | 1.19倍 | 2.20倍 |
※出典:厚生労働省「職業安定業務統計」「看護師等の確保を巡る状況」
このように、看護師の有効求人倍率は常に約2倍以上で推移しており、他職種と比較しても深刻な売り手市場であることが分かります。
看護師の数は増えているのに各病院は慢性的な『人手不足』に悩まされている。本記事では、このような表面的な統計では見えてこない「本当の人手不足の原因」に焦点をあて、病院経営の視点から実効性のある対策について考察していきます。
それではまず、看護師不足が及ぼす影響について考えましょう。
看護師不足が医療現場にもたらす深刻な影響
看護師の人手不足は、単に採用活動がうまくいかないという経営上の問題にとどまらず、医療現場そのものの機能や安全性に大きな影響を及ぼします。ここでは、看護師不足が引き起こす6つの主な影響について解説します。
1. 患者と医療の安全性が脅かされる
看護師が不足している状況では、1人の看護師が受け持つ患者数が増えざるを得ません。本来、医療機関には「患者7〜10人に対して看護師1人」という配置基準が求められていますが、現場ではこの基準を下回る状況が常態化しています。
このような過重労働は、患者一人ひとりに十分なケアを提供することを困難にし、医療ミスのリスクを高めます。結果として、患者の安全性が損なわれる恐れがあるのです。
2. 病床数の制限を余儀なくされる
必要な看護体制を確保できなければ、医療機関は受け入れ可能な患者数を制限するしかありません。これは、病床数の一時的または恒常的な削減につながります。十分な看護師を配置できない状態で病床数を維持すれば、現場の負担がさらに増し、安全性が損なわれるからです。
結果として、地域の医療供給能力そのものが低下するリスクがあります。
3. 医療事故のリスクが高まる
過重労働や慢性的な業務負担は、スタッフの集中力や判断力を著しく低下させます。余裕のない状態で業務にあたれば、ヒューマンエラーが発生しやすくなり、結果的に医療事故を招く危険性があります。
重大な事故が起これば、医療機関の信用失墜だけでなく、損害賠償や訴訟、最悪の場合は閉院に至る可能性も否定できません。
4. 病院の閉鎖・閉院に直結する可能性
看護師が確保できないことで、医療機関の運営そのものが立ち行かなくなるケースもあります。実際に、人手不足によって診療科の一部閉鎖や病棟の縮小、さらには病院の閉院に追い込まれる事例も発生しています。
特に、地方や小規模な病院では人材確保が困難であり、代替の医療機関も少ないため、地域医療全体に大きな打撃となります。
5. 人件費の高騰と経営負担の増大
人手不足を背景に、医療機関では給与や手当の引き上げ、人材紹介会社への高額な手数料の支払いなど、採用にかかるコストが増加しています。これにより、病院の収益が圧迫され、他の運営資源に回す余力が失われがちです。
また、既存職員の待遇改善や離職防止にも予算を割かざるを得ず、慢性的なコスト増加に悩まされる医療機関も少なくありません。
6. 医療機関間の格差が拡大する
人材が集まる医療機関と、そうでない医療機関の間で、診療体制やサービスの質に差が生じる傾向が強まっています。給与や福利厚生、働きやすさ、IT活用などに投資できる病院は、より多くの人材を引きつける一方で、そうした環境整備が難しい施設は、ますます人材確保が困難になります。
このようにして、人手不足が医療機関間の“格差拡大”を助長するという悪循環に陥る可能性もあるのです。
以上のように、医療現場の人手不足は、各病院だけでなく地域医療全体に深刻な影響を及ぼす可能性を孕んでいます。
では、このような看護師不足はなぜ起きているのでしょうか?続いての章では、看護師の人手不足を引き起こす要因を3つご紹介します。
看護師の人手不足を引き起こす3つの要因

看護師の人手不足は、一時的な問題ではなく、いくつもの複合的な要因が絡み合って発生しています。人材を増やすだけでは解決できない根深い背景があるのです。ここでは、看護師不足を引き起こしている3つの主要な要因について整理します。
1. 高齢化による看護ニーズの急増
日本は世界の中でも突出した高齢化社会であり、今後も高齢者の割合は確実に増加すると見られています。2025年には人口の約30%、2060年には約40%が65歳以上になると予測されており、看護の需要はこれまで以上に拡大することが明らかです。
高齢者の多くは慢性疾患を抱えており、継続的な医療やケアが必要です。病院や介護施設だけでなく、訪問看護や在宅医療の需要も高まっています。しかし、そうしたニーズに応じられるだけの看護人材の供給が追いついていないのが実情です。看護師不足の本質は、「需要の急増に対して供給が追いつかない構造的な問題」といえるでしょう。
2. 業務負担と不規則な勤務による疲弊
看護師の業務は、単に医師の補助や患者のケアにとどまりません。看護記録の作成や報告業務などの事務作業、さらに夜勤やオンコール対応など、不規則で負担の大きい就業形態も含まれています。
日本医療労働組合連合会が実施した2022年の調査によると、看護師の約78%が慢性的な疲労感を抱え、66%が健康不安、65%が強いストレスを感じていると回答しています。さらに、「仕事を辞めたい」と思いながら働いている人が約8割にも上る結果となりました。
特に夜勤では、少人数体制での病棟管理や緊急対応が求められるため、業務の密度は非常に高くなります。これが長時間労働や休暇の取りにくさにもつながり、心身ともに限界を感じる看護師が後を絶ちません。こうした労働環境の厳しさが、離職を決断する一因となっているのです。
3. 高い離職率と復職の壁
新しい看護師を採用しても、高い離職率が続いている限り、人手不足は根本的に解決しません。離職の主なタイミングは、出産・育児・結婚などのライフイベントによるものであり、特に女性看護師に多く見られます。職場に戻りたくても、夜勤やシフト制といった働き方が障壁となり、復職をためらうケースも少なくありません。
こうした背景から、看護師資格を持ちながら医療現場で働いていない「潜在看護師」が全国に約80万人いるとされています。仮にその3分の1が復職できれば、2025年に予測される27万人の人手不足も大幅に改善できる可能性があります。しかし現状では、復職支援体制が十分とはいえず、再び現場に戻るハードルが高いままです。
以上のように、看護師の人手不足を引き起こしている社会的・構造的要因があることがわかりました。
しかし、医療現場の人手不足の要因はこれだけではありません。現場からは、時代の変化による『新たな人手不足』とも言える悩みが聞かれます。
続く章では、今の医療現場、特に現場の看護師長たちからヒアリングした内容を基に、人手不足の真の要因を紐解いていきます。
時代とともに人手不足の種類が変わっている

時代の変化による『新たな人手不足』
「看護師の数は減っていないのに、シフトが組めない」「特に夜勤のシフトが回せない…」そんな看護師長の声を、多くの医療現場で耳にします。
看護師の総数は着実に増えているにもかかわらず、現場の体感としては「人が足りない」と感じられる。このギャップの背景には、単なる人手不足ではなく、「働ける時間帯や業務内容に偏り」が生じているのです。
ここでは、現代の医療現場が直面している「新たな人手不足」の具体的な要因を4つに分けて解説します。
1. 働き方改革による就労条件の多様化
育児休業の取得期間延長、短時間勤務制度の普及、有給休暇取得率の向上など、看護師を含む医療従事者の労働環境は年々改善が進んでいます。場合によっては再任用制度の活用により、定年後も柔軟に働く看護師も増えています。
こうした「働き方の多様化」は、子育てや介護、ライフスタイルに応じて無理なく働ける選択肢が広がった点で、非常に意義深いものです。しかしその一方で、夜勤や長時間勤務が可能な人材が限られ、結果的にシフト編成が難しくなるという新たな課題も生まれています。
2. 新人看護師の夜勤参加までの時間が延びている
現在は、新卒看護師に対する研修体制が充実しており、丁寧な育成が行われるようになっています。これは新人の早期離職防止や安全な業務遂行のために重要な取り組みです。
ただ、その反面、新人が夜勤に入るまでの期間が以前よりも長くなり、夜勤に参加した後も独り立ちするまでには慎重なステップが設けられています。その結果、夜勤を担える看護師の層が限られ、ベテランスタッフへの依存度が高まっています。
3. 看護師の高年齢化による勤務制限
看護師の平均年齢は年々上昇しており、それに伴って体力的な制約を抱える職員も増えています。夜勤や長時間勤務が難しくなるケースが多く、これまで夜勤を担っていた中堅~ベテラン看護師の夜勤のシフト数が減少している現場も少なくありません。
これもまた「働き続けられる環境」が整備された結果ではありますが、同時にシフト運営の難しさという課題にも直面しています。
4. 「様式9 夜勤72時間ルール」による夜勤時間の上限設定
2006年度の診療報酬改定で導入された「様式9 72時間ルール」は、夜勤を行う看護職員の月平均夜勤時間を72時間以下に抑えることを求める制度です。このルールの目的は、過剰な夜勤労働を抑制し、看護師の健康維持と患者の安全確保を図ることにあります。
非常に重要な制度ではあるものの、このルールの遵守により、1人の看護師に割り当てられる夜勤回数が物理的に制限されるため、夜勤に対応できる人材が多くても、シフト枠には限界が生じてしまいます。
主力層の負担が増えている
このように、働き方改革や制度の充実によって、子育て世代や高齢の看護師も働き続けやすい職場環境が整ってきたのは確かに良いことです。しかしその一方で、夜勤やフルタイムの勤務を担える「主力層」への負担が偏りつつあるという事実も見逃せません。
「看護師の数は足りているはずなのに現場が回らない」――
この現象は、もはや単なる人数の問題ではなく、「勤務可能な条件のミスマッチ」が生み出している、新たなかたちの人手不足なのです。
医療現場の変化による『相対的人手不足』
医療現場で語られる「人手不足」には、単に人数が足りないという『絶対的な不足』だけでなく、患者の状態や業務の性質により、現場の負担が実際以上に重くなる『相対的な不足』も含まれています。
この「相対的不足」は、看護師の数が増えていてもなお、「足りない」と感じる背景に深く関わっています。ここでは、その具体的な要因を4つの視点から解説します。
1. 入院患者の高齢化に伴うケアの複雑化
近年、入院患者の平均年齢は年々上昇しており、高齢の患者が医療の中心層を占めるようになっています。高齢者は、認知症や複数の慢性疾患を抱えていることも多く、日常生活の多くに介助が必要です。
たとえば、トイレ誘導やオムツ交換、食事介助、入浴介助といったケアが必要となり、若年層の患者に比べて看護師の関わりが長時間にわたる傾向があります。そのため、1人の患者にかかる業務量が増え、たとえ看護師数が増加しても、業務の総負荷はむしろ高まっているのが実情です。
2. 入退院のスパン短縮による業務の煩雑化
医療制度改革により、入院日数の短縮が進んでいることも、看護師の業務負担を増大させる要因のひとつです。患者の回転が早くなるということは、それだけ入退院に関わる業務の頻度が高まるということを意味します。
具体的には、入院同意書、診療計画書、手術や検査に関する各種同意書の説明と取得が必要となり、患者1人あたりにかかる説明時間が大きく増加しています。高齢者の場合、家族への説明も必要になることが多く、より丁寧な対応が求められます。
こうした事務的かつ対人コミュニケーションを要する業務が、現場の看護師の時間とエネルギーを大きく奪っています。
3. タスクシフトの難しさと現場の負担
看護師の業務を一部、看護補助者(看護助手・ナースアシスタントなど)に移す「タスクシフト」の取り組みが進められています。しかし、まだまだ医療的判断が求められる看護師でなくてはならない業務ではない業務も、依然として看護師自身が担わざるを得ないのが状況の病院も多くあります。
実際に、看護職員のみなさん自身も「教えているより自分でやった方が早い」「何を任せていいのかわからない」「看護師ではなくてもよい業務とはいえ、何かあったら責任を取るのかわたし」という考えや思いもあり、なかなかタスクシフトが推進できずに頭を抱えている病院も多いのではないでしょうか。
そのため、看護補助者を採用し「人手」は増えたのに、実際に移行できた業務の幅がまだ狭いことから、看護師の負担が軽減されない状況も見受けられます。
4. 入院患者数の増加による業務密度の上昇
最後に、看護師数が増えているにもかかわらず、それ以上に入院患者数が増加しているという実態があります。以下は、直近のデータで病床稼働率が向上していることを示すデータです。以下は、ある120床規模の病院における看護師数と平均入院患者数の推移を示したものです。
【病院における看護師数と入院患者数の推移】
| 年度 | 看護師数 | 平均入院患者数 |
| 2017年 | 94名 | 72名 |
| 2023年 | 109名 | 105名 |
このデータからもわかるように、看護師の人数は6年間で15名増えていますが、同期間に平均入院患者数は33名も増加しています。一人あたりの担当患者数が増えれば、当然、看護師一人の負担も大きくなるのです。
このように、「相対的不足」は、患者の状態や業務の性質、制度の変化といった複数の要因が重なって生じる、非常に複雑な問題です。看護師の数だけを見て「増えているから大丈夫」と判断することはできず、現場の実感を尊重した分析と対策が求められています。
続いては、医療現場の人手不足に対応する解決策について考えましょう。
医療現場の人手不足に対応する解決策 – 病院経営の観点から

採用や待遇を改善するための4つの施策
看護師の人手不足が慢性化するなかで、医療機関にとっても「採用できない」「定着しない」ことへの対策が急務となっています。看護師の数を確保し、かつ働きやすい職場環境をつくるには、経営の視点から継続的な改善が求められます。
ここでは、病院経営者・事務局が取り組むことができる具体的な4つの対策について解説します。
1. 給与待遇や福利厚生の見直し
まず重要なのは、給与や手当、福利厚生の見直しです。人手不足の要因の一つに、待遇への不満や将来不安があります。夜勤手当や残業手当を適正に支給することで、過重労働に対する心理的負担を和らげ、モチベーションの維持につながります。
中には、業務量に対して十分な手当が支払われていないケースも見受けられ、それが離職や再就職への躊躇の原因となっています。給与水準を大きく引き上げるのが難しい場合でも、福利厚生の充実によって職員満足度を高めることは可能です。
たとえば以下のような取り組みが、看護師の定着・復職支援に効果的です:
- 院内託児所の設置:育児中の看護師が安心して勤務できる環境を整える
- 育児・介護休業の取得促進:ライフイベントによる離職を防ぐ
- リフレッシュ休暇や時間単位年休の導入:柔軟な働き方への対応
これらの取り組みは、現職の定着率向上だけでなく、潜在看護師の復職意欲を高めるきっかけにもなります。
2. 医療DX化による業務効率化
次に注目したいのが、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務効率化です。看護師が本来のケア業務に集中できるよう、IT技術を活用して事務作業や管理業務の負担を軽減する取り組みが進んでいます。
たとえば以下のような導入が効果を上げています:
- 電子カルテ、電子処方箋の導入
- 看護記録の音声入力システム
- スケジュール自動化ツールや訪問看護のルート最適化
さらに、看護補助や搬送を担う医療ロボットの導入なども、業務の一部を代替し、スタッフの時間を有効に使える環境づくりにつながります。
人材を増やすだけではなく、限られた人材で高い質の医療を提供するための工夫が、今後ますます重要になってくるでしょう。
3. キャリアアップの支援体制の整備
看護師が長く、前向きに働ける環境をつくるには、キャリア形成を支える制度づくりも欠かせません。スキルアップや専門性の獲得を支援する体制が整っている職場は、働く魅力が高くなり、定着や採用の面でもプラスに働きます。
具体的な支援策には以下のようなものがあります:
- 認定看護師・専門看護師などの資格取得支援
- 研修費用の補助や勤務調整による学会参加支援
- オンライン講座やEラーニングなど柔軟な学習機会の提供
キャリアアップの機会を確保することで、職員のスキル向上とともに医療の質も高まり、病院全体のブランド力向上にもつながります。
4. 求人方法の見直しと情報発信の工夫
看護師の採用においては、従来の求人掲載だけでは十分とはいえない時代になっています。求職者のニーズやライフスタイルが多様化するなかで、ターゲットに応じた情報発信と戦略的な採用体制が、ますます重要となっています。
新卒採用への取り組み:
新卒看護師の確保には、看護学生との早期接点の構築が鍵を握ります。説明会の開催はもちろん、看護学校の教員との関係構築も欠かせません。信頼関係を築くことで、卒業後の進路として病院を推薦してもらえる可能性も高まります。
また、県外の看護学校へも積極的にアプローチし、広域的な採用活動を展開することで、より多くの人材と出会えるチャンスが広がります。
既卒・復職希望者へのアプローチ:
出産や育児を機に離職した看護師の中には、子どもの成長を機に復職を考える母親世代が多くいます。こうした潜在看護師に向けて、職場復帰しやすい環境(院内託児所の有無、夜勤なしのシフト相談など)を具体的に伝えることで、安心感と魅力を伝えることができます。
情報発信手段としては、ポスターやチラシの地域配布、院内見学会の開催、SNS戦略の強化などが効果的です。とくにSNSは、親しみやすさやリアルな職場の雰囲気を伝えるツールとして、復職希望者の背中を押す役割を果たします。
採用を支える「人事部」の創設:
多くの医療機関では、採用業務を総務や事務部門が兼任しているのが現状です。しかし、これでは採用に十分なリソースを割けず、戦略的な活動が難しくなりがちです。
そのため、専任の人事部門の設置が求められています。人事部を立ち上げることで、中長期的な人材戦略の立案、広報活動、採用後の定着支援まで、一貫した人材マネジメントが可能となります。
病院経営においても、「人を確保し、育て、活かす」視点を持つことが、持続可能な医療体制の構築につながります。
以上のように、看護師の数を確保し働きやすい環境を作る方策はいくつかあります。しかし、人員を増やしたり労働環境を改善するには、相応の人件費が必要になります。
限られたリソースの中で室の高い医療を維持するためには、『今いる人員でなんとかする』努力も必要です。
適切な人員配置と『今いる人員』で対応する方法

人員の適正配置と病床数・病棟数の適正化(なるべく病床を減らさない工夫)
人手不足の中でも、現場を支えるためには「新たに採用する」だけでなく、現在の人員を最大限に活かし、無理なく働ける体制を整えることも重要です。限られたリソースで質の高い医療を維持するには、院内の機能や配置を見直しながら、業務効率と働きやすさの両立を図る必要があります。
以下のような取り組みが、有効な対応策として挙げられます。
- ICUやHCUの病床数調整と、一般病棟の病床数の適正化
- 病床数を維持しつつ、病棟数そのものを減らす検討(必要な総夜勤時間を減らす施策検討)
- 病床種別(急性期・地域包括・回復期など)の見直し
- タスクシフトの推進とチーム医療の強化
- 各病棟における診療科の配置バランスの再検討
定着につながるコミュニケーション
これらの運用上の見直しに加えて、今いるスタッフが長く、安心して働き続けるためには、日々のコミュニケーションの在り方が非常に大切です。
看護師の仕事は、身体的にも精神的にも大きな負担を伴います。
命と向き合う現場では、強い責任感や使命感を持って働く方も多く、やりがいと同時に大きなプレッシャーを感じながら日々業務に取り組んでいます。
しかし、日々の業務に追われる中で、「自分のしていることは意味があるのだろうか」と、ふとした瞬間に虚無感に襲われてしまうこともあります。これは、真剣に仕事に向き合っている人ほど感じやすい心のサインです。
だからこそ、忙しい毎日の中でも、「ありがとう」「助かっています」「頼りにしています」といった小さな言葉の積み重ねが、スタッフの心を支える力になります。
業務に対するねぎらいや、スタッフ同士のコミュニケーションが、その人の存在価値を感じられる時間になるのです。
こうした日常的なコミュニケーションの積み重ねが、定着支援として非常に効果的であり、「この職場でこれからも働きたい」と感じてもらうための大きな要因になります。マネジメント側からの一方向的な施策だけでなく、「人と人との信頼関係」を育てる対話が、職場全体の空気を変えていくのです。
スタッフの心に寄り添いながら、業務運営や配置の最適化を進めるためには、現場の状況に合わせた具体的な施策の検討と実行が不可欠です。
「自院ではどこから着手すべきか分からない」「取り組みの優先順位を整理したい」とお悩みの場合は、医療経営の現場に精通したリージョンマネジメント株式会社へご相談ください。
貴院の状況に応じた最適なご提案と、実践に向けた伴走支援を通じて、持続可能な人材マネジメントの構築を全力でサポートいたします。