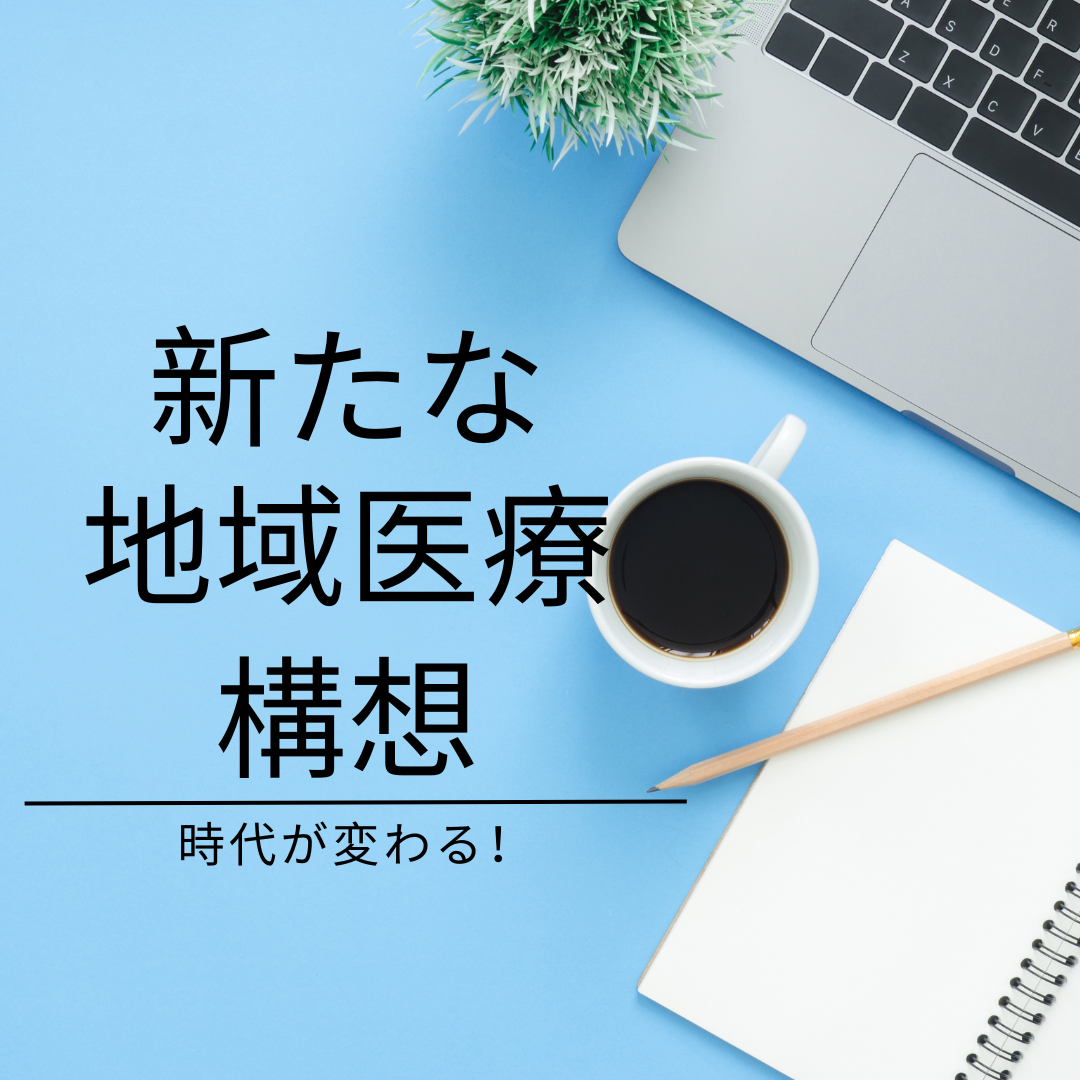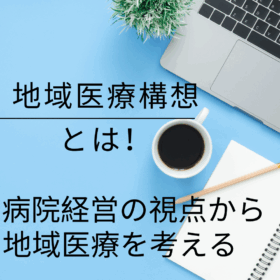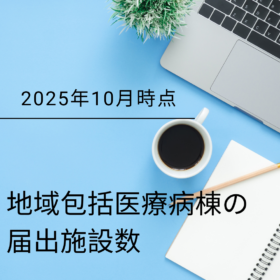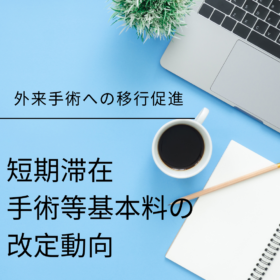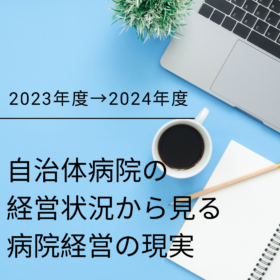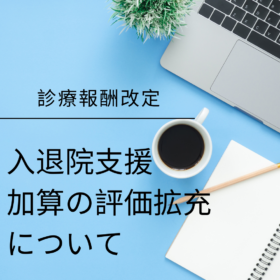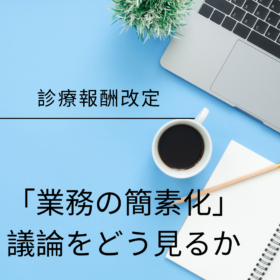こんにちは。病院経営コンサルの勝又です。
本テーマはyutubeに動画をアップしていますので、ご興味のある方はご覧ください。
はじめに:地域医療構想の再考が求められる背景
日本の医療提供体制は、急速な少子高齢化や人口減少、医療技術の進化などにより大きな転換点を迎えています。特に、2040年問題と呼ばれる超高齢社会の到来に伴い、医療資源の適正配分や病床機能の見直しが急務となっています。また、新型コロナウイルスの影響で医療機関の役割が再評価され、地域包括ケアシステムの強化や医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が求められています。持続可能な医療提供体制の構築に向け、新たな地域医療構想が必要とされています。
Contents
1.現行の地域医療構想の評価と課題
(1)これまでの取組
現行の地域医療構想は、2025年に団塊の世代が75歳以上となることを見据え、高齢化による医療需要の増大に対応するため、入院医療を中心に病床の機能分化・連携を推進するものでした。各都道府県では、二次医療圏を基本とした構想区域ごとに、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの病床機能を設定し、2025年の必要病床数を算定して地域医療構想を策定してきました。
2015年の推計では、病床の機能分化を進めなければ152万床が必要とされていましたが、医療資源投入の少ない患者の在宅医療への移行等を通じ、119.1万床に抑えることを目標として進められてきました。そして、毎年度、病床機能報告を通じて医療機関は病床機能の現状と今後の方針を報告し、これを基に地域医療構想調整会議で病床機能の転換や再編について協議が行われてきたところです。都道府県は地域医療介護総合確保基金を活用し、病床の機能分化・連携を支援するとともに、必要に応じて医療法に基づく権限を行使し、構想の実現に向けた役割を担ってきました。国も財政支援に加え、重点支援区域の設定やデータ分析支援、地域医療構想アドバイザーの配置などを通じて、都道府県の取組を後押しして、進められてきました。
(2)評価と課題
現行の地域医療構想では、病床機能の分化・連携が進み、一定の成果が見られています。2015年から2023年にかけて病床数は125.1万床から119.2万床に減少し、2025年の必要病床数119.1万床にほぼ達しました。特に、急性期と慢性期の病床が減少し、回復期が増加するなど、病床機能の適正化は進んでいると言えます。また、療養病床の医療区分1の患者や医療資源投入量の少ない患者の在宅移行が進み、約30万床の削減目標も概ね達成されつつあります。
一方で、いくつかの課題も指摘されています。現行の議論は病床数に偏りがちで、将来の医療提供体制のあり方や外来・在宅医療を含めた地域全体の医療体制の検討が不十分です。また、病床機能報告制度において、高度急性期と急性期、急性期と回復期の違いが明確でなく、必要病床数と実際の病床数との間にも差異が生じています。さらに、必要病床数と基準病床数の関係が分かりづらいなど、制度面の課題も残っているといえます。
2.新たな地域医療構想における基本的な方向性
2040年以降の高齢化と人口減少を見据え、全ての地域・世代の患者が適切な医療・介護を受けながら生活し、必要時に入院し日常に戻れる持続可能な医療提供体制の構築が求められる。そのため、新たな地域医療構想では、限られた医療資源を最適化し、「治す医療」と「治し支える医療」の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制の実現を目指していきます。
(1)高齢者救急への対応
85歳以上の高齢者の入院疾患は若年層に比べて限定的で、手術を伴うものは少ないが、入院中の安静による筋力低下が課題となっています。そのため、入院早期からの離床やリハビリテーションを促進し、早期の退院と在宅復帰を支援することが重要です。特に、大腿骨近位部骨折では早期手術が推奨されますが、国内では手術待機時間が長い地域があり、改善が求められます。また、高齢者の入院期間はADL低下や認知症、単独世帯の増加といった社会的要因により長期化しやすく、今後さらに増加することが予測されています。
このため、高齢者救急への対応として、救急搬送の受入体制を強化するとともに、入院早期からのリハビリ介入や退院調整の充実が必要です。専門病院との連携を図りながら、退院後も通所・訪問リハビリを継続できる仕組みを整備し、医療DXの活用による医療機関・高齢者施設との連携強化が求められています。
(2)増加する在宅医療の需要への対応
外来医療の需要は多くの地域で減少傾向にある一方、在宅医療の需要は増加しており、2040年に向けさらなる拡大が見込まれています。特に、診療所医師の高齢化や人口減少が進む中、在宅医療の提供体制を整備し、地域の医療・介護連携を強化することが求められます。在宅医療は、診療所や病院、訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬局、介護施設などが多職種連携で提供していますが、地域によって提供体制に差があり、特に人口規模の小さい地域では訪問看護の体制が不十分な場合も多々あります。また、在宅医療を担う医療機関の間でも訪問患者数に大きな差があり、効率的な体制構築が課題となっています。
このため、医療機関と訪問看護ステーションの連携による24時間対応の提供体制を構築するとともに、オンライン診療の活用や医師派遣・巡回診療の推進が必要と去れます。さらに、外来医療においても、時間外対応やかかりつけ医機能の発揮を促し、必要な医療提供体制を確保することが求められています。
(3)救急・急性期医療の在り方と医療従事者の確保
近年、一般病床や療養病床の利用率が低下し、2040年に向けて高齢者救急以外の急性期医療の需要も減少する推計が出ています。特に手術症例は多くの構想区域で減少が予測され、すでに夜間や休日の緊急手術件数も少ない地域が多くなってきています。一方、救急医療は高齢者の搬送が増加する傾向にあり、救急搬送の約30%は18~64歳の成人が占めます。二次救急医療施設は約3,200、三次救急医療施設は約300あり、二次救急は救急搬送の7割を受け入れていますが、受入件数には大きな地域差があります。救急車を年間5,000件以上受け入れる施設もあれば、年間500件未満の施設も多く、特に三次救急医療施設の少ない地域では、二次救急施設が中心的な役割を担っています。
こうした状況を踏まえ、緊急対応を含む救急・急性期医療については、地域の医療需要や医療資源等を踏まえながら、持続可能な医療従事者の働き方や医療の質及び患者の医療機関へのアクセスを確保する観点から、搬送体制の強化等に取り組みつつ、地域ごとに必要な連携・再編・集約を進め、二次救急医療施設も含めた医療機関において一定の症例数を集約して対応する地域の拠点として対応できる医療機関を確保することが求められます。
(4)新たな地域医療構想の基本的な考え方
2040年に向け、病床の機能分化・連携だけでなく、外来医療・在宅医療、介護連携、人材確保を含めた包括的な医療提供体制の実現が求められています。そのため、新たな地域医療構想では、「治す医療」と「治し支える医療」の役割分担を明確化し、医療機関の連携・再編・集約化を推進することが重要です。
この新たな構想の策定に向け、
- 2025年度に国がガイドラインを作成
- 2026年度に都道府県で医療提供体制の方向性を検討
- 2027年度以降に具体的な医療機関の連携・再編を進める
上記の計画(スケジュール)となっています。
現行の地域医療構想の取組は2026年度も継続し、2027年度から新たな枠組みへ移行する予定です。新たな構想は、入院医療だけでなく、外来医療や在宅医療、介護との連携、人材確保など地域の医療提供体制全体の課題解決を目指していくことになります。また、これまでの地域医療構想を医療計画の上位概念として位置づけ、医療計画は具体的な実行計画として6年または3年ごとに策定されます。さらに、救急医療施設の役割分担や医療従事者確保を含めた長期的な計画を立て、データに基づくPDCAサイクルに沿って医療機関機能と病床機能の確保を推進することが求められるよう担っていきます。
3.医療機関機能報告・病床機能報告
新たな地域医療構想では、医療機関機能・病床機能を重視した医療提供体制の構築が求められます。そのため、医療機関から都道府県への報告制度、必要病床数の推計、関係者の協議、支援策の見直しが必要となります。病床機能に加え、医療機関機能も報告対象とし、役割分担や連携の協議を促進されていきます。さらに、国民や患者にも報告の意義を丁寧に説明し、診療報酬の届出等に基づく客観的な報告制度を導入し、医療機関の役割を明確化することが重要です。
(1)医療機関機能報告の導入
新たな地域医療構想では、医療機関機能に焦点を当てた地域医療構想を策定・推進するため、病床機能報告の対象医療機関に対し、新たに医療機関機能を都道府県へ報告する仕組みが導入されます。具体的には、二次医療圏ごとに確保すべき機能として、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能、専門医療機能を位置づけ、また、広域的な視点から医育機能や広域診療機能も対象とし、医療機関がこれらの機能を確保し、将来的な方向性を報告する仕組みを構築していく方向性になります。。
医療機関は、主たる機能を選択することが求められますが、地域の実情に応じて複数の機能を担うことも可能とされます。具体的な報告項目や方法については、今後策定されるガイドラインで詳細を検討されていきます。また、高齢者救急に関する報告では、救急搬送だけでなく、医療機関と介護施設の連携による救急搬送を伴わない緊急入院の評価にも留意が必要です。
(2)医療機関機能の名称と定義
新たな地域医療構想では、地域の医療提供体制を確保するため、以下の医療機関機能を設定し、それぞれの役割は以下のようになります。
① 高齢者救急・地域急性期機能
救急搬送を受け入れ、専門病院や施設と連携し、入院早期からのリハビリや退院調整を行い、早期退院を促進する。救急搬送件数が少なくても地域の主要な受入機関である場合は報告対象とし、地域の実情に応じた報告基準を設ける。
② 在宅医療等連携機能
在宅医療の実施と、医療機関や介護施設、訪問看護・訪問介護との連携を通じた24時間対応や入院対応を行う。地域によって在宅医療の中心が診療所か病院か異なるため、地域の実情に応じた報告基準を設定する。
③ 急性期拠点機能
医療従事者の持続可能な働き方や医療の質を確保するため、手術や救急医療など高度な医療資源を要する症例を集約し提供する。地域の医療シェアやアクセスを考慮し、一定の水準を満たす医療機関を報告対象とする。また、構想区域ごとに必要な病院数を設定する。
④ 専門等機能
集中的なリハビリ、中長期入院、有床診療所による地域診療、特定診療科に特化した医療機能を担う。特に高齢者医療では、多疾病併存(マルチモビディティ)患者への対応が重要である。
⑤ 医育及び広域診療機能
大学病院本院などが担う医師派遣、卒前・卒後教育、広域診療を提供し、地域全体の医療人材を確保する役割を担う。急性期拠点機能を持つ医療機関が広域的な診療や人材育成の役割を持つ場合もあり、地域全体での機能確保に向けた協議に活用する。
これらの機能報告は、地域の実情に応じた柔軟な基準を設け、ガイドラインで詳細を検討されていく予定となっています。
(3)病床機能について:回復期機能が「包括期機能」に変更
病床機能区分ごとの必要病床数の推計と病床機能報告は、医療需要を把握し、病床の機能分化・連携を推進する重要な役割を果たしてきました。今後もこの制度を維持し、適切な病床機能の確保を図ることは継続されます。
病床の機能区分(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)は、これまでの取り組みの連続性を踏まえ継続ですが、2040年に向けて高齢者救急の受け皿を強化するため、回復期機能が「包括期機能」に変更されます。「包括期機能」は、高齢者救急の受入れや入院早期からの治療、リハビリ、栄養・口腔管理を一体的に提供し、早期の在宅復帰を目指す機能とする。この新たな概念については、適切に理解されるよう周知を徹底し、医療機関の病床機能報告が適切に行われるよう報告方法の分かりやすい説明が求められます。また、医療従事者確保が厳しくなる中、将来の必要病床数の推計は受療率の変化を踏まえ、定期的に見直しを行うことが適当であり、推計方法は従来の手法を基本としつつ、診療実績データを基に機能区分ごとの推計を行い、ガイドラインで改革モデルを含めた具体的な推計方法を検討されることになります。
(4)基準病床数と必要病床数の整合性の確保
人口減少が進む中、地域の医療需要や医療資源の状況を踏まえ、不足する医療機能への転換や病床の適正化を進める必要がります。基準病床数制度は、病床の地域偏在を是正し、全国的に一定の医療水準を確保するための仕組みですが、第8次医療計画では病床利用率の変化に伴い、多くの都道府県で基準病床数が増加しています。また、既存病床数が基準病床数を下回る場合は、必要病床数を超えても増床が可能となっています。
しかし、必要病床数と基準病床数の関係が分かりづらいとの指摘があり、基準病床数制度と地域医療構想の整合性を確保し、病床利用率の低下を考慮した効率的な病床整備が求められています。そこで、新たな地域医療構想の実現に向け、基準病床数の算定時に必要病床数を考慮することを検討し、必要病床数を超えて増床する場合には、地域医療構想調整会議で必要性が認められた場合に限り許可する仕組みが導入される方向性です。また、都道府県は、既存病床数が基準病床数を上回る場合や、一般・療養病床の許可病床数が必要病床数を超える場合、地域の実情に応じて病床の機能転換や減少を促すため、医療機関に調整会議への出席を求めることができるようにすることができるようになる方針です。
4.おわりに
2040 年頃に向けて、人口動態の変化に伴い、医療の需要や提供体制等の地域差が拡大し、地域ごとに将来を見据えた取組が求められています。新たな地域医療構想を通じて、国、都道府県、市町村、医療関係者、介護関係者、保険者、住民の協働のもと、中長期的に質の高い効率的な医療提供体制が確保されることが期待されます。