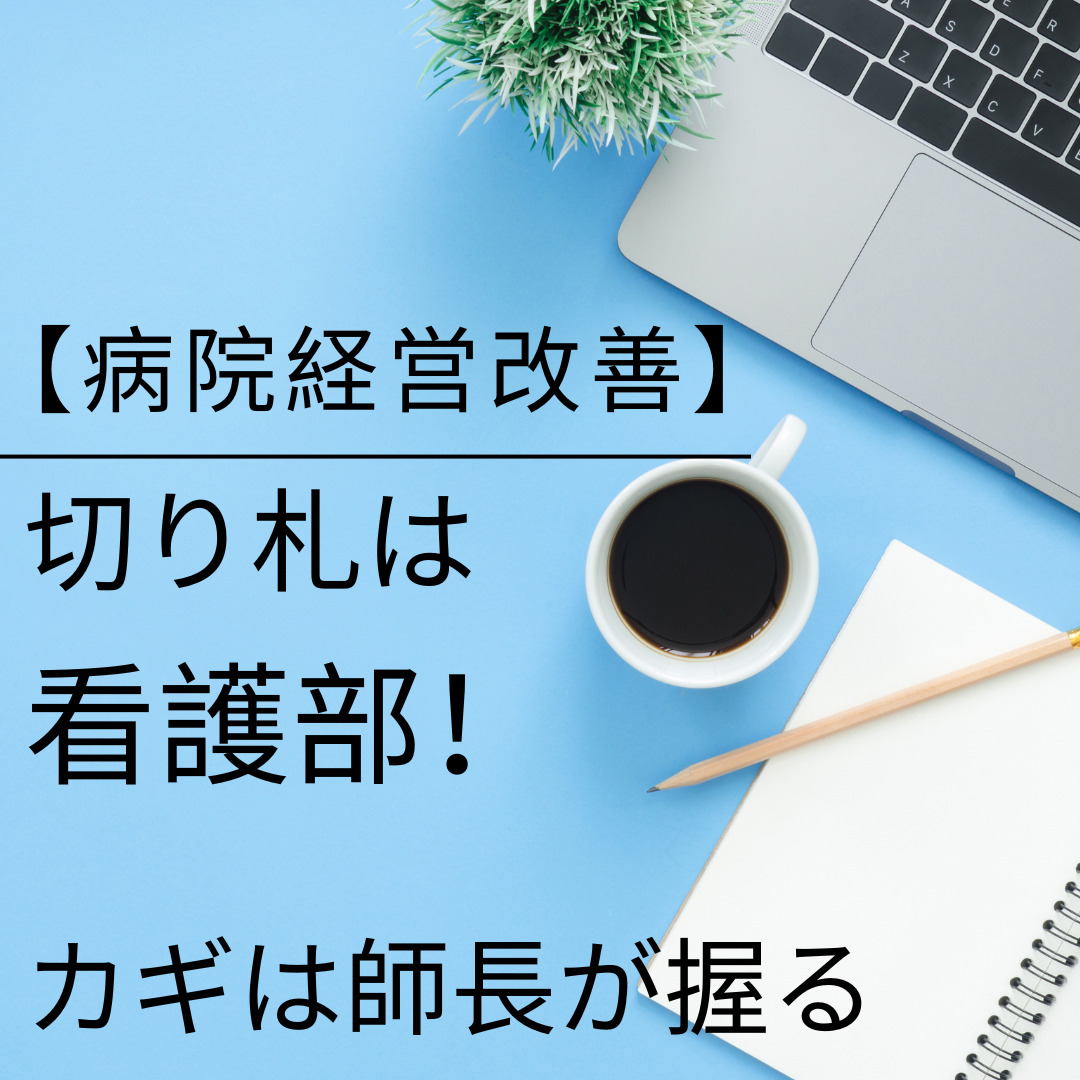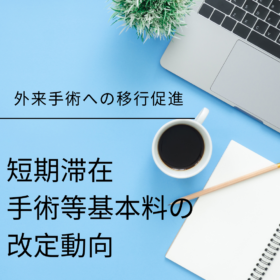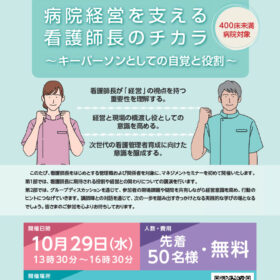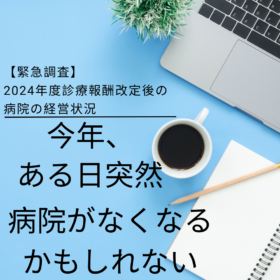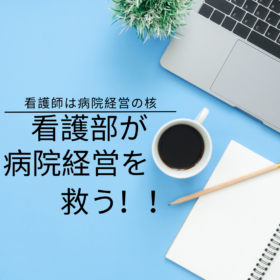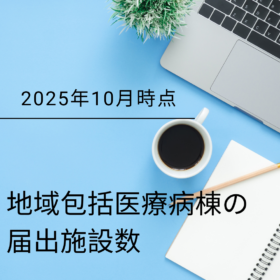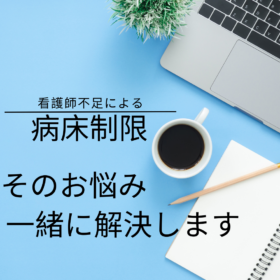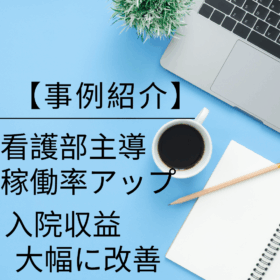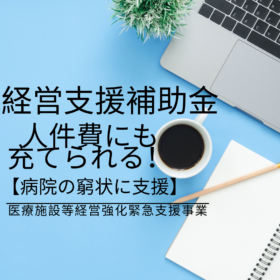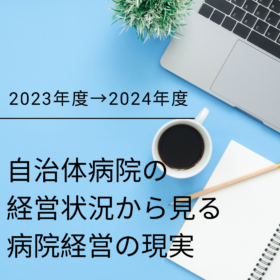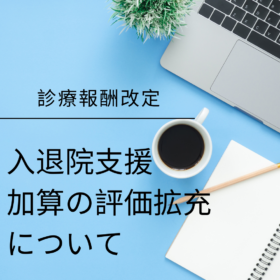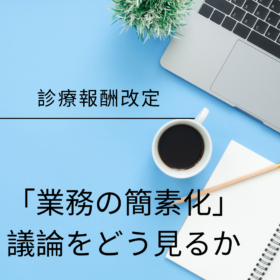Contents
はじめに
病院経営を考えるとき、しばしば「数字」「赤字」「黒字」といった言葉が先行し、冷たいイメージを持たれがちです。けれども実際には、病院は地域にとって欠かせない社会インフラであり、その使命は「質の高い医療を持続的に提供すること」にあります。つまり経営は、利益追求のためではなく、医療を守り続けるための基盤づくりに他なりません。
その中で最も重要な存在となるのが「看護部門」です。看護師は病院全体の職員の半数以上を占め、医療の質、患者満足度、さらには経営の安定性にまで直結します。看護部のマネジメントをどう行うかは、病院の未来を左右する大きな課題です。
YouTubeも配信していますので、是非、ご覧ください。
視点① 医療の質と財務の両立 ― 経営は“盾”である
「病院経営」と聞くと、多くの人は“利益”や“数字”を思い浮かべます。しかし、病院経営の本質は決して利益追求ではありません。病院は企業とは異なり、社会的使命として「良質な医療を持続的に提供すること」を目的としています。だからこそ、経営とは単なるお金の話ではなく、「医療の質を支えるための仕組みづくり」そのものなのです。
医療の質と経営の安定は、両輪である
医療の現場では「経営」と「医療」は対立概念のように語られることがあります。けれども実際は、質の高い医療を提供するためには、安定した経営基盤が欠かせません。たとえば医療機器の更新、人材の確保、研修の実施、働きやすい環境整備――どれも財務的な裏付けがなければ続けることができません。つまり「医療の質」と「経営の安定」は切り離せない関係にあり、この2つのバランスこそが病院経営の要なのです。反対に、経営を軽視すれば、いくら医療の理想を掲げても持続できません。非営利組織である病院であっても、経営を整えなければ医療の継続は不可能です。経営とは、医療を守るための“条件にすぎない”と言っても過言ではありません。
病院経営の目的は「利益」ではなく「持続」
「利益を上げること」は、あくまで病院が地域医療を維持するための手段です。利益そのものが目的ではなく、再投資を通じて医療の質を保つことが本来の目的です。たとえば、新しい医療設備の導入や、看護師の待遇改善、地域連携システムの構築など、どれも財務の健全化があって初めて実現できます。経営を“冷たい数字”と捉えるのではなく、“温かい医療を守るための盾”として考える――それが現代の病院経営に求められる視点です。
経営を支える「五大資源」
病院経営を考える上で欠かせないのが「経営資源」という考え方です。一般には「人・物・金」が三大資源と呼ばれますが、最近では、そこに「情報」と「時間」を加えた“五大資源”を基本として考えるようになってきています。
- 人:医師・看護師・医療技術者・事務職員など
- 物:医療機器、薬剤、診療材料、建物など
- 金:診療報酬などによる収入と費用
- 情報:医療情報・経営データ・電子カルテなど
- 時間:限られた勤務時間、診療時間、患者対応時間
これらをどれだけ効果的に配分・運用できるかが、経営の鍵となります。その中でも「人」、特に看護部門は病院全体の中で最大の組織です。看護師の数は全職員の半数以上を占め、日々のケアや業務の在り方が病院経営そのものに直結します。つまり、看護部の運営=病院の経営安定を左右する要因なのです。
次回は、この五大資源の中でなぜ“看護部門”が最も大きな影響力を持つのか、そして看護師の働き方がどのように病院経営に結びついているのかを掘り下げていきます。
視点② 経営資源と看護部の役割 ― 看護が経営を動かす理由
病院を支える経営資源の中で、最も重要な位置にあるのが「人」、特に看護部門です。どの病院においても、看護師は職員数の半数以上を占める最大組織であり、その運営と働き方が病院全体の経営に直結しています。看護部の力をどう活かすかによって、医療の質だけでなく病院の財務状態までもが左右される――それが現代医療経営の現実です。
看護部が「経営の鍵」と言われる理由
看護師は患者にとって最も身近な存在であり、入院生活のほぼすべての時間を共にします。患者満足度、リピート率、口コミ評価といった外部指標に直結するのは、実は看護師の接遇・対応・ケアの質が多くを占めます。言い換えれば、看護部の働き方が病院ブランドをつくるといっても過言ではありません。
さらに看護業務は、診療報酬制度と深く結びついています。たとえば「看護配置」や「看護必要度」といった項目は、入院基本料の算定に直結します。つまり、看護師の動きひとつひとつが病院の収入に直結しているのです。
「患者数 × 診療単価」という単純な計算式で収益が決まる病院経営の中で、看護師はその両方に影響を与える存在です。患者に選ばれる病院をつくるのも、単価を支えるサービスの質を保つのも、現場で汗を流す看護職員の力にかかっています。
看護部門は最大の「費用」でもある
一方で、看護部は経営の柱であると同時に、最大の費用要因でもあります。病院の支出の中で最も大きな割合を占めるのは「人件費」であり、その中でも看護職員にかかるコストが最も高いのが実情です。病院によっては、総費用の50〜70%以上を人件費が占めることもあり、その多くが看護部門に関係しています。
このように看護部は、「経営を支える柱」であると同時に、「経営を圧迫する要因」にもなり得るのです。ゆえに、看護部のマネジメントは病院経営の“心臓部”と言えます。現場の働き方ひとつ、勤務表の作り方ひとつで、経営が大きく変わる可能性があるのです。
経営視点を持つ看護管理者の重要性
看護師としてのスキルに加えて、経営意識を持った管理者が増えることで、病院全体のパフォーマンスは飛躍的に向上します。「看護=医療の質」だけでなく、「看護=経営資源」という視点を持てるかどうか…これが、今後の医療現場を大きく分けるポイントとなります。
看護部長や副部長だけでなく、病棟単位で現場を支える師長・副師長・主任クラスのリーダーたちが、この意識を持つことが極めて重要です。現場を最もよく知る立場にある彼らこそが、経営改善の“最前線”に立っているからです。
第3回:収入と費用 ― 看護部門が抱える現実と人件費構造
病院経営は、大きく「収入」と「費用」のバランスで成り立っています。その中で最も大きな費用項目となるのが人件費、そしてその大部分を占めるのが看護部門です。つまり、看護部の運営は病院経営の安定性を左右する最重要領域だといえます。
病院の収入は「患者数 × 診療単価」
病院の収入は、診療報酬をベースとした非常にシンプルな構造です。「患者数 × 診療単価」という掛け算で決まり、患者数が減れば収入も減り、診療単価を上げるには加算や施設基準の届出など、相応の努力が必要となります。しかし現在、多くの病院では患者数の伸び悩みと単価の頭打ちという“二重苦”に直面しています。
診療報酬改定が抑制傾向にある中で、外来・入院ともに患者数が減少すれば、経営は直ちに圧迫されます。一方、医療の質を維持するためには人員削減は難しく、看護師不足の中で採用・教育コストは上昇。結果として、収入が横ばいのまま費用だけが増えるという状況に陥る病院が増えているのです。
看護部門の人件費が占める割合
病院経営における費用構造を見ると、人件費の割合は50%〜70%、その中でも看護部門が占める割合は実に半分近くにのぼる場合もあります。医師の給与が高く見えるものの、人数の面で圧倒的に多いのは看護職員。そのため、看護部門の人件費が経営全体の最大要因となるのです。
ただし、この数字は単なる“コスト”ではありません。看護師が安心して働ける環境、十分な人員配置、教育体制の整備は、そのまま患者安全と医療の質の向上につながります。経営側が「削減すべき費用」として見るのではなく、「未来の収益を支える投資」として捉える視点が求められています。
視点③ 看護師不足と人件費高騰のジレンマ
近年の医療現場では、慢性的な看護師不足が深刻化しています。同時に昨今の給与水準の引き上げの波により、経営サイドとしては人件費を抑えたい一方で、現場では「人が足りない」「負担が増える」「離職が進む」という悪循環が起きています。この矛盾を解決するには、単に給与を上げるか下げるかではなく、生産性を高める仕組みづくりが必要になります。
視点④ 現場の葛藤と生産性 ― 看護師不足の中で求められる判断
病院の収入を支える要素は、「患者数」と「診療単価」です。一方で、現場を動かすのは医療者の“人の力”です。経営上の数字を追うほど、現場の負担が増す――。この矛盾の中で、いま多くの看護管理者が日々葛藤しています。
「高稼働」と「安全な看護」の板挟み
経営的には、病床稼働率を上げることが最もシンプルな収益向上策です。しかし、入院患者を増やすということは、それだけ看護負担も増えるということになります。特に近年では、認知症や介護度の高い高齢患者の増加により、看護の手間は単純な人数以上に膨らんでいます。また医師の判断では「退院可能」とされた患者であっても、退院先が見つからず病院に留まらざるを得ないケースも少なくありません。その結果、ベッドは埋まっているのに医療依存度の低い患者の増加と介護度の高い患者の増加に直面することもあります。
そんなジレンマの中、「稼働率を上げたい経営」と「安全を守りたい現場」、その板挟みの中で最も苦しんでいるのが、まさに師長・副師長・主任クラスの看護管理者たちです。
単価を上げる努力と業務の増加
もう一つの収益要素である「診療単価」を上げるためには、各種加算の算定や新たな施設基準の届け出が欠かせません。しかしこれには膨大な書類作成、カンファレンス記録、患者説明などが伴い、現場の事務作業は確実に増加します。結果として、「患者と向き合う時間が減り、記録や報告に追われる」という現象が起きています。看護師が最も大切にしてきた“患者に寄り添う時間”が削られ、「自分は何のために看護師になったのか」と悩む職員も少なくありません。経営のための業務改善が、看護師のモチベーションを下げてしまう――。これもまた現場のリアルな葛藤です。
生産性をどう高めるか
こうした中で避けて通れないテーマが「生産性の向上」です。人件費の高騰と看護師不足という二重の課題のもとで、限られた人員でいかに質を落とさずに業務を回すか…それがいま、病院経営における最大のテーマとなっています。単純に「少ない人数で多くの仕事をこなす」ことではなく、重複業務を減らし、システムを活用し、時間の使い方を変えることが求められています。たとえば電子カルテやシフト作成ツールの二重入力など、現場では意外に“非効率な慣習”が多く残っています。これらを整理し、業務を最適化することが第一歩ではないでしょうか。
看護管理者の視点から言えば、「気合でで乗り切る」時代は終わりました。これからは、働き方そのものを設計する力が求められています。その鍵を握るのが、現場のリーダーである師長・副師長・主任たちのマネジメント力です。
視点⑤ 師長・副師長・主任のマネジメント力が変える病院経営の未来
看護部の力が病院経営に直結することは、これまで見てきた通り明らかです。しかし、その中でも特に大きな影響を与えているのが、現場の中心に立つ「師長・副師長・主任」などの看護管理者です。看護部長や副部長が全体の方針を決める存在であるのに対し、現場を具体的に動かしているのは現場の看護管理者です。つまり、病院経営の最前線に立つ“経営実践者”こそが師長や主任たちなのです。
現場を動かす「管理者の一言」
看護師のシフトを組み、人員配置を決め、業務の優先順位を判断します。それら日々の判断一つひとつが、病院全体の稼働率や離職率、患者満足度にまで影響します。看護部長がトップダウンで示した方針も、実際に形にしていくのは現場の管理者たちです。彼らの「一言」「判断」「姿勢」が、看護部全体の雰囲気を左右し、結果として経営成果にも直結します。
また、スタッフへの声かけやフォロー、モチベーション管理も欠かせません。師長や副師長が部下に対してどう向き合うかで、現場の士気が変わります。看護師が「自分は大切にされている」と感じる環境は、離職率の低下やチームの安定に直結するものです。まさに、看護管理者が病院経営を支えているといえます。
マネジメントは「生まれつきの才能」ではない
とはいえ、看護管理者の多くは、現場叩き上げのベテランです。看護技術や臨床経験は豊富でも、「人をまとめ、組織を導く」ためのマネジメント教育を受けていないケースも少なくありません。実際、「主任になったけど何をすればいいのかわからない」「師長になった途端、孤独を感じる」といった声も多く聞かれます。
マネジメントは、経験や感覚だけで行うものではありません。計画・実行・評価・改善というPDCAを回す力、目標設定と人材育成、コミュニケーションスキル、業務改善の分析力――これらは学ぶことで高められるスキルです。看護協会などが提供する「看護管理者研修(ファースト・セカンド・サード)」の受講を通じて体系的に学ぶことは、個人だけでなく病院全体の経営力を底上げする重要な投資といえるでしょう。
管理者の待遇と評価の見直しを
もう一つ見過ごせないのが、看護管理者の待遇です。多くの病院では、役職手当がわずかで、時間外勤務がつかなくなるなど「管理職になるメリットが感じられない」という声があります。責任ばかりが増え、給与面の評価が追いついていない現状では、「なりたくない管理職」が増えてしまうのも当然です。
今後は、管理者を「負担の多い役職」としてではなく、「病院の未来を支える専門職」として正当に評価することが求められます。マネジメント教育と同時に、給与体系や働き方を見直し、“看護管理者になることが誇り”と思える環境づくりが必要です。
まとめ ― 病院経営を支えるのは現場の力
病院経営は、単なる「数字」や「利益」の話ではありません。医療の質を守り、地域に継続的に医療を届けるための仕組みづくりそのものです。そのためには、医療の質と財務の両立という視点を持ち、五大資源(人・物・金・情報・時間)をいかにバランスよく運用できるかが鍵となります。
中でも「人」、特に看護部門は病院経営の中心にあります。看護師のケアの質や働き方は患者満足度や病院ブランドを左右する一方で、人件費の大部分を占める費用要因でもあります。この二面性を理解し、看護部のマネジメントをどう行うかが、病院の未来を決定づけるのです。
さらに、現場を具体的に動かす師長・副師長・主任といった看護管理者の存在は極めて大きな意味を持ちます。日々の判断やマネジメント力が病院全体の安定や発展につながるため、彼らを「経営の実践者」として正しく評価し、学びと待遇の両面で支えることが求められます。
病院経営の本質は「持続性」にあります。その持続を実現するのは、経営会議でもなく、数字だけでもなく、日々の現場を支える看護職員、そして彼らを導く看護管理者たちです。経営と現場をつなぐマネジメントの力こそが、病院の未来を形づくっていくのです。
第3回:収入と費用 ― 看護部門が抱える現実と人件費構造
病院経営は、大きく「収入」と「費用」のバランスで成り立っています。その中で最も大きな費用項目となるのが人件費、そしてその大部分を占めるのが看護部門です。つまり、看護部の運営は病院経営の安定性を左右する最重要領域だといえます。