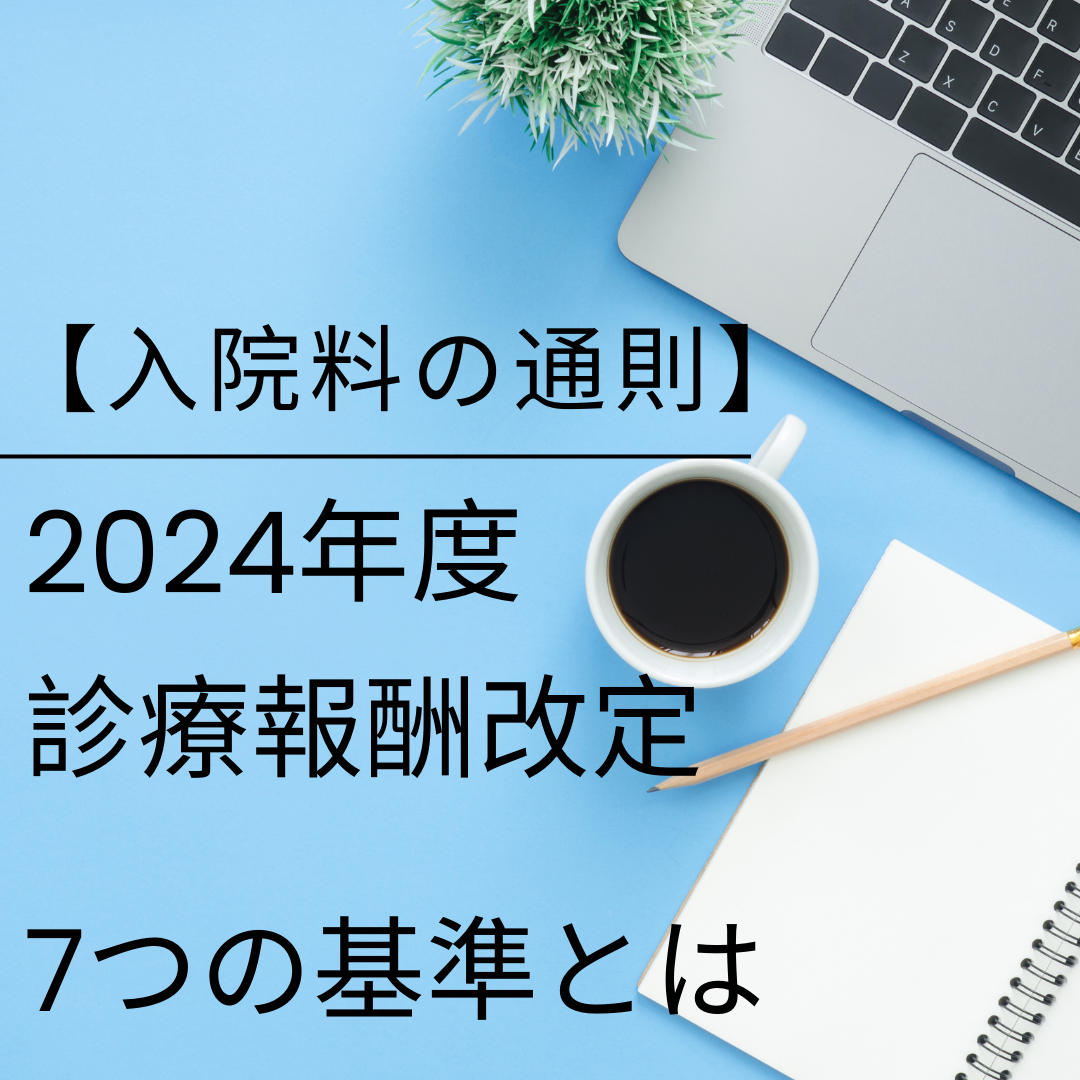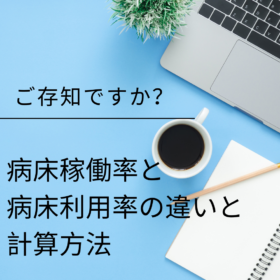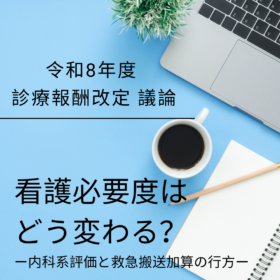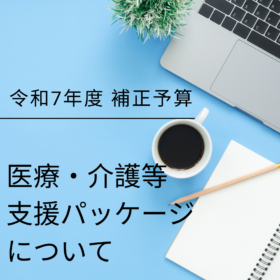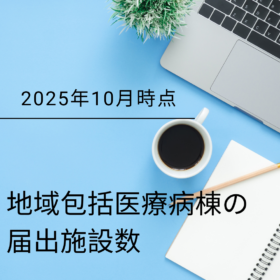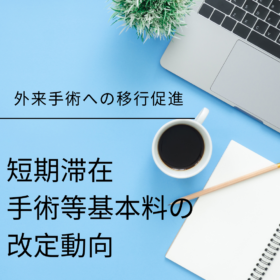Contents
はじめに
2024年度の診療報酬改定において、大きな注目を集めていたのが「入院料の通則」の見直しです。栄養管理体制の明確化、身体的拘束の最小化取組の強化や人生の最終段階における意思決定支援が新たに加わり、従来の5項目から7項目に拡大しました。この記事では、制度の解説だけでなく、現場で働く看護師や医療従事者が「日常業務の根拠」として理解できる視点で、入院料の通則7項目を整理していきます。
こちらは動画でも解説していますので、ぜひ、ご覧ください。
入院料の通則の7項目とは?
「通則」とは、各入院料(急性期一般入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリ病棟入院料など)に共通して適用される必須要件のことです。つまり、この基準を満たしていない場合には入院基本料そのものが算定できない、病院経営に直結するルールです。
7項目は以下のとおりです。
- 入院診療計画
- 院内感染防止対策
- 医療安全管理体制
- 褥瘡(じょくそう)対策
- 栄養管理体制
- 人生の最終段階における意思決定支援
- 身体的拘束の最小化の取り組み
これらの通則は、「入院料を算定する場合に満たすべき基準」です。さらに、2024年度の診療報酬改定で、栄養管理体制や身体的拘束最小化の基準を満たしていない場合は、1日につき40点の減算という厳しいルールが明記されました。さらに「基準に適合していることを示す資料等を整備しておく必要がある。」と明記されており、証拠(記録・資料)の整備まで求められるという点が重要です。
では、一つずつ解説していきましょう。
1. 入院診療計画の基準
入院患者に対して、この入院診療計画書を入院後7日以内に策定・説明し、文書を交付することが求められます。
計画書には以下の内容を記載することが求められています。
- 病名や症状
- 治療・検査・手術の内容と日程
- 予測される入院期間
- 栄養やリハビリに関する方針
小児や意識障害などで本人への説明が難しい場合は家族への説明で代替でき、再入院でも病態によっては新たに作成・説明が必要です。説明に用いた文書は必ず交付し、その写しを診療録へ添付することまでが要件に含まれています。現場の感覚で言えば、「いつもやっている入院時の説明と配布書類」が、制度面では“入院基本料の前提”であり、看護師が担う説明と記録の一つひとつが病院の算定根拠を形づくっている、という理解が重要です。
2. 院内感染防止対策の基準
次に、院内感染防止対策です。病院には感染防止対策委員会の設置が求められ、月一回程度、(対面に限らず)委員会の開催がされている必要があります。委員会の構成メンバーは、院長、看護部長、薬剤部門・検査部門・事務部門の責任者、そして感染症対策の経験をもつ医師など多職種です。
各病棟の微生物学的検査の状況等をまとめた「感染情報レポート」を週一回程度作成し、委員会で十分に活用する体制が必要です。当該レポートは入院患者の細菌検出状況や薬剤感受性のパターンを病院の疫学情報として把握・活用する目的で作成され、単なる拭き取り検査の羅列ではありません。
また、流水による手洗いの励行とともに、水道や速乾式手指消毒剤の設置を徹底します。精神科や小児病棟などは患者の特性に配慮し、携帯用消毒剤で代替する柔軟性も認められています。私たちが日常で行う手指衛生は、単独の個人技に留まらず、委員会・レポート・設備・運用という“仕組み”に準じて、組織の感染対策として実施されております。――そう捉えると、日々の一動作の意味がより鮮明になります。
3. 医療安全管理体制の基準
医療安全管理体制も、医療法と通則の中核です。安全管理の指針を整備し、基本的な考え方や事故発生時の対応方法まで文書化すること、院内報告制度を運用してインシデントや医療事故を収集・分析し、改善へつなげる体制を回すことが求められます。安全管理委員会は月一回程度(オンラインも可)開催し、年二回程度の職員研修を計画的に実施します。
日々のヒヤリ・ハットの報告や研修への参加は、この通則に基づいて行われており、組織全体の安全文化を支える大切な要素です。インシデントレポートの提出や研修への参加は、単なる義務ではなく「自分を守る盾」にもなります。万一事故が発生した際に、組織として適切に安全体制を運用していたことが証明できれば、過剰な個人責任の追及を避けることができます。つまり、しっかりとエビデンスを残すことは、患者さんを守るだけでなく、現場で働く一人ひとりを守ることにも直結しているのです。
4. 褥瘡対策の基準
褥瘡対策は、患者の療養生活の質と予後に直結します。専任の医師と、褥瘡看護の臨床経験を有する専任の看護職員で構成される褥瘡対策チームの設置が求められています。当該チームが日常生活自立度の低い患者について危険因子の評価を行い、危険因子がある患者や既に褥瘡を有する患者には、適切な診療計画を作成し、実施し、評価します。ここで作成された計画に基づく取り組みであれば、実施者はチームの専任者以外でも構いません。薬学的管理や栄養管理の記載は患者の状態に応じ、必要に応じて薬剤師や管理栄養士と連携して記載します。チームの構成メンバーによる委員会の定期開催が望ましく、さらに体圧分散マットレス等を適切に選択・使用できる体制を整えることが要件となっています。そして毎年八月に褥瘡患者数等の届出を行うことも含まれます。
褥瘡は一度発生すると多くのケースで治癒に時間がかかり、感染やADLの低下を招きやすいため、予防的に取り組むことは患者の生命予後や生活の質を守るうえで極めて重要です。組織的な褥瘡対策は、病院全体の医療の質を映し出す指標とも言えるでしょう。
5.栄養管理体制の基準
2024年度の改定で強化されたのがこの栄養管理体制です。病院には常勤の管理栄養士を一名以上配置し、医師・看護師・管理栄養士を中心に、標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等を組み込んだ手順を整備します。入院時には医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認し、特別な栄養管理の必要性の有無を入院診療計画書に記載します。特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者には、栄養状態、摂食機能、食形態を考慮した栄養管理計画(別添様式に準ずる)を作成し、救急入院や休日入院などで当日策定が難しい場合でも、入院後七日以内の策定が求められます。計画には栄養補給量や方法、特別食の有無、入院時・退院時の栄養食事指導の計画、その他の課題や評価間隔などを記載し、計画書またはその写しを診療録等に添付します。実施後は、計画に基づいて栄養管理を行い、定期的に栄養状態を評価し、必要に応じて見直します。
栄養状態は、入院患者の予後や療養生活の質に直結する大きな要素です。低栄養の状態にある患者は、褥瘡や感染症を合併しやすく、ADLの低下や入院期間の長期化、再入院のリスクが高まることが、国内外の研究でも明らかにされています。厚労省はこうしたデータを踏まえ、栄養管理を「加算」ではなく「入院料の通則」に格上げして必須化しました。背景には、いくつかの政策的根拠があります。
- 厚労省が提示している「高齢者の低栄養予防」や「フレイル対策」の流れ。高齢化が進む中で、栄養不良が医療・介護の負担を増大させるリスクとして重視されています。
- 令和6年度改定説明資料でも、GLIM基準(国際的な低栄養判定基準)を用いた評価の活用が推奨され、標準化を国レベルで進める方針が示されています。
- 「栄養管理体制加算」など従来の加算が十分に浸透していなかった実態を踏まえ、「どの病院でも最低限実施すべき取り組み」として通則化した、という側面があります。
つまり、厚労省は「低栄養が入院医療のアウトカムを悪化させ、医療費全体を押し上げる」ことを明確に問題視しており、入院時・退院時を含めた栄養評価と管理を病院全体の標準業務にすることを狙いとし、通則において栄養管理手順が明確化されました。
6. 意思決定支援の基準
意思決定支援は、厚生労働省が策定した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に基づき、各医療機関で院内指針を整備することが求められています。2024年度改定では、これが「入院料の通則」として全病院に必須化されました(一部病棟のみを有する医療機関は対象外)。ここで重要なのは、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)を単なる“書面化の手続き”に終わらせず、“関係性と対話のプロセス”として日常業務に根付かせることです。
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)が推進される背景には、いくつかの社会的・医療的要因があります。まず、日本社会の高齢化が進むなかで、人生の最終段階における治療選択の重要性が急速に高まっていることが挙げられます。現場では「本人の意思が確認できず、家族や医療者が判断に迷う」という状況が繰り返し発生しており、誰もが安心して納得できる意思決定のプロセスを整える必要性が増しています。さらに、国民の権利として自己決定を尊重する医療を実現することも大きな課題です。
そしてもう一つの背景には、医療費や入院期間の観点から、不要な延命治療を避け、患者自身が納得できる医療を選択できるようにすることが政策的に求められているという事情もあります。こうした要因が重なり、ACPの推進が国を挙げた取り組みとして進められているのです。
意思決定支援の通則化は、病院にとって「必須の制度対応」であると同時に、現場の看護師や医師にとっては「患者の声を拾い、対話を積み重ねる」営みを制度的に裏付けたものです。今後は診療所や在宅領域にも拡大し、単なる指針の有無ではなく、ACPが実際にどのように機能しているかが評価対象となるでしょう。つまりACPは、制度的な必須要件であると同時に、患者の尊厳と安心を守るために不可欠なプロセスとして、さらに強化・推進されていくのです。
7. 身体的拘束最小化の基準
身体的拘束の最小化は、「緊急やむを得ない場合を除き拘束を行わない」という原則を、現場で実際に運用できる仕組みへ落とし込むことを意味します。拘束を行った場合には、その態様や時間、患者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を必ず記録しなければなりません。また、専任の医師と専任の看護職員で構成される「身体的拘束最小化チーム」を設置し、実施状況を把握するとともに、管理者を含む職員に対して定期的に情報を周知することが求められます。
さらに、このチームは拘束最小化のための指針を作成し、それを職員へ周知・活用させ、定期的に見直しを行います。指針の内容には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や、身体拘束以外の行動制限を最小化するための工夫を盛り込むことが望ましいとされています。そして、入院患者に関わるすべての職員を対象に、定期的な研修を実施することも要件に含まれています。
実際の現場では、ナースコールの頻回や頻繁な離床、せん妄、夜間の不穏、家族の同意形成の難しさなど、どうしても“拘束に頼りたくなる瞬間”が少なくありません。だからこそ、代替策の選択肢を増やし、環境調整や見守り体制の工夫、薬物の使い方、家族との協働のあり方まで、チームで知恵を出し合うことが重要です。そしてその取り組みを記録に残し、次のケアにつなげていく。この一連の営みを組織の仕組みにまで高めることこそが、今回の通則で示された身体的拘束最小化の核心なのです。
最後に
最後に、実務上の重要な点を確認しておきましょう。通則は「やれば良い」ではなく、「やっていることを確認できる形に整える」ことまでを求めています。委員会の開催通知と議事録、病棟ラウンドの記録、評価票や計画書、研修計画と出席簿、設備配置の台帳、感染レポートの回付記録――こうしたものは決して煩雑さの象徴ではありません。むしろ患者にとって望ましいケアを、組織として持続させるための“見える化”であり、同時に私たちの実践を評価につなげるための橋渡しです。
七つの通則は、日々の「業務」を単なる作業としてではなく、患者の尊厳と権利を守り、安全で質の高い医療を実現するための共通言語と言えるでしょう。私たちが日々の説明・観察・介入・記録を丁寧に積み重ねることこそが、患者の安心と安全を支え、ひいては病院の信頼と経営基盤を強固にします。そして現場の一人ひとりが、自分のケアが通則のどこに位置付くのかを意識し、チームで小さな変化を拾い上げ、共有し、次へとつなげていく、その積み重ねこそが、通則の本質であり、これからの入院医療の質をかたちづくる原動力となるのです。