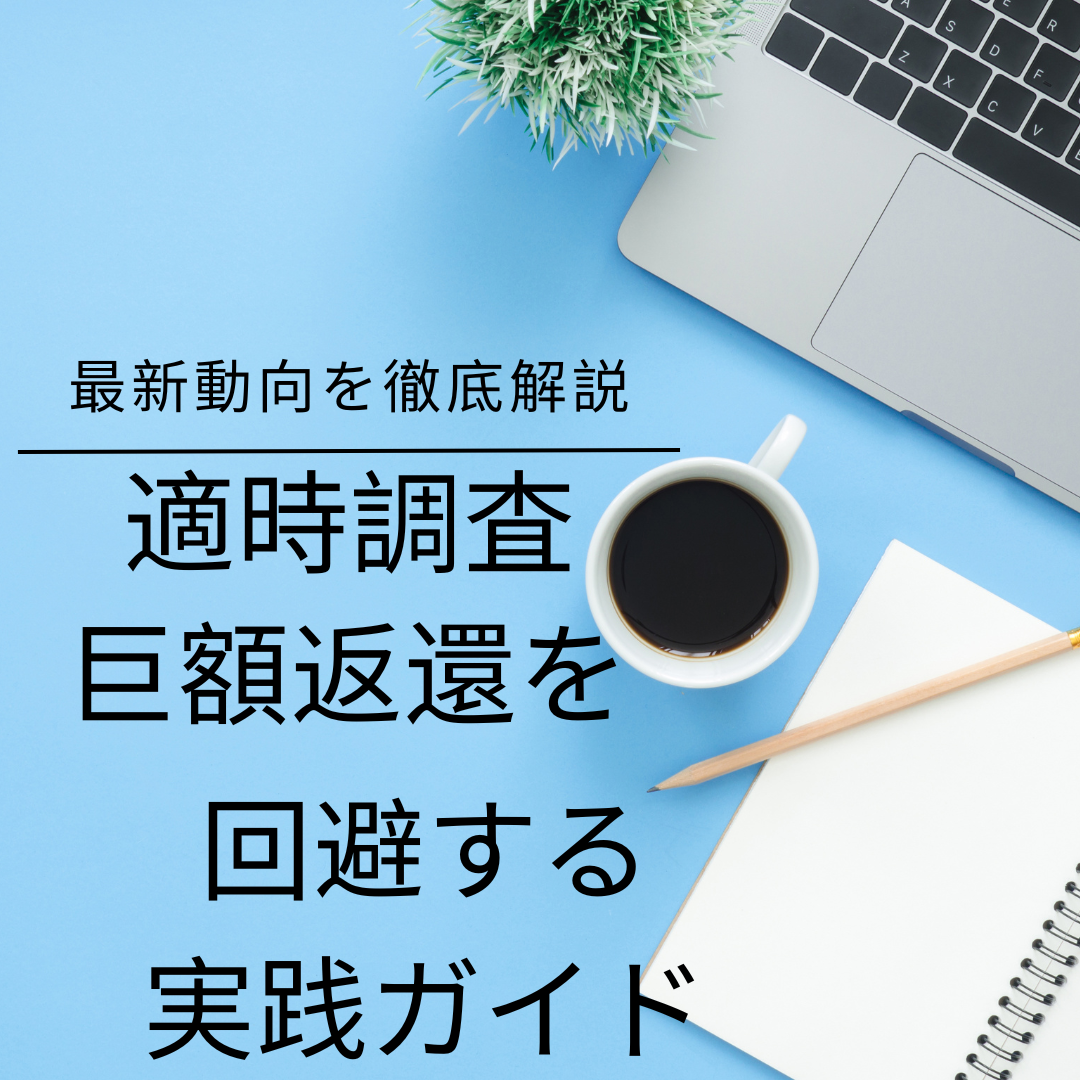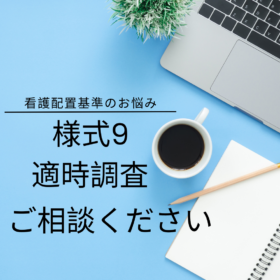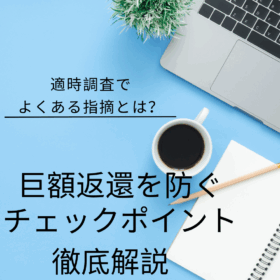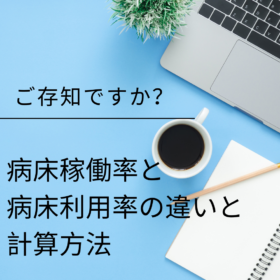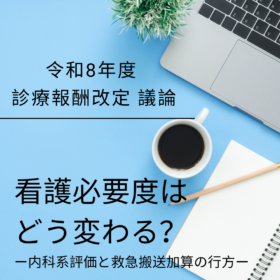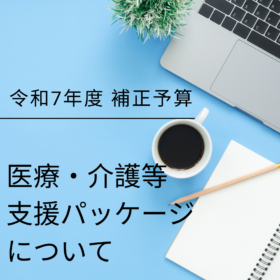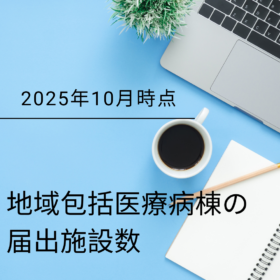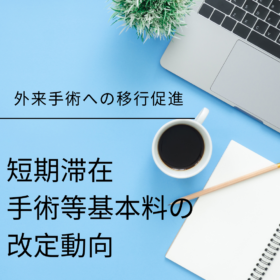こんにちは。病院経営コンサルタントの勝又です。本日は、病院経営においてときに“天敵”とも言われる適時調査をテーマにお話しします。
適時調査がなぜ「怖い」と言われるのか――それは、一度不備が見つかると、過去数年分の診療報酬返還が求められる可能性があるからです。数千万円単位ならまだしも、数億円規模に上る事例も報告されています。院長先生や事務長の方々にとって、経営面のダメージは計り知れません。
この適時調査については別途YouTubeでも動画をアップしております。
2024年度(令和6年度)の診療報酬改定後、厚生局による立ち入り調査の体制がいよいよ本格化し、施設基準の厳格な遵守がこれまで以上に求められています。すでに適時調査が再開され、看護配置基準などを満たせていなかったことで、数億円規模の返還を迫られた事例も報告されています。こうした事例を聞くと、「いつかはウチの病院にも…」と心配になりますよね。
実は適時調査の要諦は、「平時から当たり前のルールをきちんと運用し、書類で証明する」ことに尽きます。調査が入ることになってから慌てて書類を用意するのではなく、常日頃のセルフチェックと正確な管理ができていれば、巨額返還などの最悪シナリオはかなりの確率で回避可能です。
本記事では、
- 適時調査とは何か?医療監視との違い
- 2025年版・最新の調査スキーム
- 巨額返還を招いた実例
- 事前準備と役割分担(経営層・看護管理者・事務職)
- 調査当日の立ち回りと指摘後のダメージコントロール
といった流れで、適時調査への具体策をまとめました。この記事を最後までご覧いただければ、「適時調査とは何か」「巨額返還を招く事例はなぜ起こるのか」「どのように備えればよいか」が、ひととおり理解できるようになるはずです。診療報酬の返還リスクを最小化し、病院経営を守るための実用的なガイドとしてぜひお役立てください。
Contents
1.適時調査とは?医療監視との違い
◆ 適時調査とは
適時調査とは、保険診療を行っている病院や診療所、保険薬局が届け出た施設基準を、実際に遵守しているかを厚生局が立ち入りで確認する制度です。具体的には、
- 一般病棟入院基本料
- 地域包括ケア病棟入院料
- リハビリテーション料
- 各種加算(看護補助体制加算、認知症ケア加算、栄養管理加算、など)
など、「ポイントが高い」あるいは「新設された」施設基準を重点的にチェックします。書類審査だけでなく、現場を実際に視察し、看護体制や掲示物が基準どおりかを確認されます。
調査の結果、施設基準を満たしていないと判断されれば、過去にさかのぼって算定した分の診療報酬返還が命じられます。場合によっては数千万円~数億円の巨額返還になることもあり、病院経営を大きく揺るがす原因になりかねません。さらに悪質だと判断された場合には、保険医療機関としての指定取消しにつながるケースもあるため、まさに病院にとっては“命綱”ともいえる調査です。
◆ 医療監視との違い
病院を対象とする立ち入り調査には医療監視(医療法第25条に基づく立ち入り検査)もありますが、こちらは主に保健所が行い、「医療法の基準に適合した安全管理がなされているか」を見るものです。建物の衛生設備や感染対策の実施状況などをチェックし、問題があれば是正指導はありますが、診療報酬の返還に直結することはありません。
一方、適時調査は主務官庁が厚生局で、施設基準の届出と運用の適合を厳しく確認するのが目的です。もし不備が指摘されれば膨大な返還リスクが伴う点が最大の違いです。「医療監視」と「適時調査」は混同されがちですが、経営に直結するのは適時調査ですので、ここへの備えが非常に重要になります。
| 適時調査 | 医療監視(医療法第25条) | |
| 管轄 | 厚生局 | 保健所 |
| 主目的 | 診療報酬の適正化、施設基準適合の検証 | 医療施設の衛生・安全確保 |
| 頻度 | 不定期(重点施設基準など重視して実施) | 概ね3~5年ごと |
| 返還リスク | 高い(巨額返還・指定取消の可能性あり) | ほぼ無し(是正指導が中心) |
2.2025年版・最新の調査スキーム
適時調査の実施頻度は「原則年1回」と定められていますが、対象施設が多い都道府県では2~3年に1回程度になっているケースもあります。いずれにせよ、診療報酬改定のタイミング(2年に1度)にあわせて、新設された項目の「重み付け」も強化されてきているため、注意が必要です。
◆ 調査の流れ
1.調査予告・実施通知(約1か月前)
厚生局から書面で「○年○月○日に立ち入り調査を行う」旨の通知が届きます。通知には、事前提出書類の締切や必要書類リストが示されます。
2.事前提出書類の準備・提出(調査10日前が期限)
ア)保険医療機関の現況
イ)入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類
(様式9)及び勤務実績表等の看護要員の病棟配
置状況等が確認できる書類
ウ)別途定める事前提出書類
エ)その他必要に応じた書類
不備があると、当日の調査が厳しさを増します。提出後も追加資料の提出を求められる場合があるため、各部署との連携が重要です。
3. 当日の準備書類(調査日までに用意)
調査当日にヒアリングや書類提示を求められたとき、即座に出せるように準備しておきます。例えば看護部の研修記録や人員配置に関する詳細資料など、“調査官が分かりやすく”準備することがポイントです。
4. 適時調査当日
- 開始時の打ち合わせ、調査方針の説明
- 病棟や設備状況などの現場視察
- 書類をもとに質疑応答
- 調査結果の概要フィードバック
- 厚生局側で集約し、後日正式通知
ここで重大な不備や不正請求が疑われると、より厳密な監査に移行する可能性があります。
5. 正式な調査結果通知・改善報告書の提出
調査終了から1か月程度で書面通知が届き、返還命令や改善命令の有無・指摘事項などが正式に示されます。もし不適合・不備が指摘されれば、
軽微な指摘であれば改善報告書を出して終了するケースもあれば、
返還額が億単位に上るような深刻な事例
もあります。
結果報告・指摘区分
-
- 口頭指摘:軽微な問題のため、改善すればOK
- 文書指摘:改善計画書・報告書の提出が求められる
- 不適合:返還請求、施設基準の届け出取り下げ指示、指定取消し等
◆ 「重点項目」と新設項目が要注意
厚生局は、「重点的に調査を行う施設基準」リストを公開しています。そこには、
- 入院基本料(一般病棟7対1、10対1、地域包括ケア病棟入院料など)
- 各種加算(看護補助体制充実加算、医師事務作業補助体制加算、認知症ケア加算、栄養管理加算 など)
- 新設されたばかりの個別項目
が含まれています。新設された加算・評価項目は現場もまだ不慣れなため、記録や届け出との食い違いが起きやすいものです。また、届け出ているすべての施設基準が調査対象になり得ることは言うまでもありません。もし基準を満たせなくなったら、速やかに届け出を取り下げることが必要です。「気づかず算定し続けていた」→「数年分を遡って返還」という事態は珍しくないので注意しましょう。
3.巨額返還を招いた実例
適時調査における最大のリスクは、〈診療報酬返還→不備が指摘された場合に、不適切に算定していた期間分の報酬を返還する義務〉が生じる点です。通常、施設基準が満たせていない事実が判明すると、その期間にさかのぼり算定の修正が行われます。基準を満たしていないにもかかわらず、数年にわたって算定を継続していた場合、返還額は数千万円から数億円に達することもあります。これは、病院のキャッシュフローを一気に圧迫するだけでなく、経営全体の信頼に影響を及ぼしかねない重大なリスクです。
さらに、〈保険医療機関の指定取消→厚生労働大臣(または都道府県知事)による公的保険医療機関としての指定を取り消される処分〉が下されることもありえます。悪質とみなされた不正行為が発覚した場合には、指定取消という厳しい処分に発展するケースが生じます。指定取消を受けると、医療機関は公的保険による診療を継続できなくなり、事実上の経営停止に近い状態に追い込まれます。
2024~2025年にかけて、既に報道や厚生局の公表資料などで幾つかの巨額返還事例が確認されています。ここではその中から代表的な3つをご紹介します。
- 夜勤帯看護師不足で1億円超の返還
夜勤帯に看護師2名を配置すべき病棟で、救急対応などの理由で1名が離れており、事実上“看護師1名”だったと認定され、結果として1億2586万円の返還対象になりました。小規模病院ほど夜間の人手不足が顕著であり、また夜間の救急対応を要する症例がさほど多く生じないなどの背景もあり、救急対応専任の看護師配置ができていないという事情が考えられます。 - 准看護師を看護師として届出し3億円超返還
緩和ケア病棟では夜間に看護師2名を配置する必要があるのに対し、実際には1名が准看護師だった日が、月に7日間程度あったとして、約3億2000万円の返還が生じたケースがあります。一般病棟入院基本料のルールと混同してしまったことが背景として考えられます。「看護師」「看護職員」「看護要員」のそれぞれの用語がさす対象職種が違うため、施設基準の文言を正確に読み込む必要があるという教訓的な事例です。 - 虚偽申告による看護師数“水増し”で5億超返還+指定取消
2014~2019年まで実際には足りない看護師数を“書類上”増やし、7対1の高い点数を算定していた病院が発覚しました。このケースは悪質と判断され、5億7000万円あまりの返還と同時に保険医療機関指定取り消しに至りました。意図的な不正は絶対にしないでください。
こうした事例の背景には、「日常の運用と施設基準の解釈にズレがある」「書類管理が杜撰で証明ができない」「悪質ではなくても思い込みや見落とし」という要因が潜んでいます。いずれにせよ適時調査では“書類があってこそ初めて適切に運用しているとみなされる”ため、“やっているけど記録がない”=“やっていない”扱いになる点を肝に銘じましょう。
4.事前準備と役割分担
~経営層・看護管理者・事務職それぞれが連携を~
適時調査を乗り切るには、病院組織全体が一丸となる必要があります。医事科だけ頑張っても限界があるため、経営層・看護管理者・事務職それぞれの役割を整理し、互いに情報を共有しておくことが肝心です。
(1)経営層(理事長・院長・事務長クラス)
- トップダウンの体制構築
経営者が「適時調査対策は当院の最重要課題の一つ」と位置づけ、はっきりと旗振りをしたほうが良いでしょう。特に診療報酬の返還リスクは財政危機に直結するため、問題の把握、そしてそれに対する対応等の判断が必要になることがあります。 - 内部監査・セルフチェックを仕組み化
平時から看護配置や勤務表、各種施設基準の運用状況をレビューする“院内ミニ監査”を定期的に行うようにします。事務部や看護部だけに任せるのではなく、経営層自らも定期報告を受け、問題点を早期につぶす姿勢が重要です。 - リスクマネジメントと意思決定の迅速化
実際に適時調査の通知が来ると1か月程度で準備しなければならず、想定外の対応を要するケースも多いです。院内で決裁が必要な事項(例:人員補充、もしくは届け出を下げるなど)が出た場合、経営者レベルで即断できる体制を整えておくとスムーズに対応できます。 - 悪質ではない不備も深刻な返還につながる
経営者が「意図的な不正をしていなければ大丈夫だろう」と油断しがちですが、前述の事例のように「見落としや勘違い」でも億単位の返還になることがあると強く認識してください。現場への危機感共有や励ましはトップの役割です。
(2)看護管理者(看護部長・師長)
- 看護師配置基準の維持に全力
病院経営を左右するのは、まず入院基本料です。夜勤体制の確保が難しい病院ほど、日常的に勤務表と様式9を突き合わせ、基準を割っていないか毎月チェックしましょう。夜勤72時間ルールや看護補助者の区分など細かい要件を正しく理解し、異動・退職・産休などがある際はすぐ総務や事務に相談して対策を練りましょう。 - 正確な記録(研修・会議録など)の整備
研修の受講実績や会議やカンファレンスの議事録、ラウンド記録などが求められます。「やっていたけど記録がない」では実施していることを証明できません。調査当日に「こちらが証拠書類です」と即提示できるよう、日ごろの記録を整理しておきましょう。 - チーム医療の教育・周知
看護師だけでなく補助者や医師事務作業補助者、リハビリスタッフなど、多職種と連携する場面が増えます。現場のメンバーが「自分たちの配置や役割が施設基準にどう関わるのか」基本的な理解を持てるよう、現場管理者向けに院内勉強会を開催するのも有効です。
(3)事務部門(医事課・総務課)
- 届出書類・様式の一元管理
どの施設基準をいつ届け出て、どんな要件を満たす必要があるのか――これらを一覧化した“施設基準管理台帳”を作り、院内人事情報・研修情報とも連携してアップデートを行っている病院もあります。該当する要件が満たせなくなったら、速やかに気づくことができるよう、それぞれの病院で体制の見直しを検討しましょう。 - 看護部・診療部との連携強化
様式9などの重要書類は看護部主導で作成する病院が多いですが、最終的には医事課も「数字が合っているか」「書式に不備はないか」をダブルチェックするべき書類得です。看護部任せにしてしまうと、いつの間にか大きなミスや認識の相違が生じていることもあります。必ず他部署のチェックが入るようにしましょう。
5.調査当日の立ち回りと指摘後のダメージコントロール
いよいよ適時調査の当日が来たら、落ち着いて丁寧に対応することが何より大切です。「とにかく隠す」「言い訳する」といった焦りは逆効果です。「調査に協力する姿勢」を示すことで、印象も大きく変わります。
◆ 指摘を受けたあとの流れ
- 正式通知(1か月以内目安)
適時調査からしばらくして、厚生局から正式な結果通知が届きます。そこに「〇〇が基準未達」「過去○年分の返還対象」などが書かれている場合、返還額を算出し速やかに支払い手続きを行う必要があります。 - 改善報告書の作成・提出
指摘事項それぞれに対して「原因」と「再発防止策・改善策」をまとめ、文書で報告します。たとえば、夜勤帯看護師2名体制が崩れていたら、「夜勤専従看護師の配置を増強し、夜間救急対応と病棟が連動できるよう○月○日から体制変更しました」など、具体的に示しましょう。 - 再発防止のための仕組みづくり
「来年から同じミスをしないためにはどうするか」を考え、院内のルールやマニュアル、教育システムを見直します。今回の教訓を次回調査まで“使い捨て”にせず、毎月のセルフチェックや内部監査に落とし込んでこそ意味があります。 - 万が一、指定取消になったら
悪質な不正請求や再三の是正指導にも応じない場合、保険医療機関指定の取消しが行われます。その場合は事実上、保険診療が不可能になりますので病院経営への打撃は計り知れません。経営権の変更・新規届け出で再度指定を取り直す道はありますが、信用回復は容易ではありません。
まとめ:日常から“適時調査モード”でのセルフチェックを
適時調査は、年に数回しかない特別なイベントに見えますが、実際は日常の施設基準運用が正しくできていれば怖くないものです。問題は、多忙を極める現場で「いつの間にか届出要件を満たしていなかった」状態に陥りやすいこと。そこにこそ大きな落とし穴があります。
- 毎月の様式9チェック
看護部・医事課が協力し、夜勤体制や重症度などを厳密に点検し、数値が満たせているか必ず確認を行いましょう。 - 職員の入退職や長期休暇の把握
人員要件をギリギリで満たしている加算は、1人抜けただけで簡単に要件割れが起こります。異動時期には管理職が総務と連携して実数を確認しましょう。 - 研修・委員会活動の記録徹底
会議や委員会の開催、研修の実施要件などは「やった証拠」を残さないと返還リスクが高まります。議事録・研修報告書をすぐ出せる形で保存しておくのが大切です。 - 院内掲示や書式類のメンテナンス
「掲示物が届出内容と違う」「非常勤医師の保険医登録情報が最新で管理されていない」などで突っ込まれるケースも多いです。返還につながることはないこともありますが、定期的にラウンドして点検すると、ミスを早期発見できます。
こうしたセルフチェックを日頃から回し、「調査が来たからあわてて書類を整える」のではなく「いつ来ても大丈夫」の状態を目指すと、返還のリスクはグッと下がります。
適時調査は病院全体のコンプライアンス度合いを測るチャンスでもあり、そこで改善すべき点が洗い出されれば、むしろ病院の経営体質を強化する好機となります。ぜひ本記事を参考に、院内各部署で連携した準備を進めてください。将来の数千万円・数億円の返還リスクを回避し、患者さんにも職員にも安心して利用・勤務してもらえる病院を目指していきましょう。
【あとがき】
適時調査の「怖さ」は、その大半が「知らなかった」「うっかり見落とした」など、準備不足から生じるケースです。問題が起こってしまったあとでは大きな痛手を負いますが、実は事前の対策はさほど難しくありません。夜勤配置表のダブルチェックや事務局との情報共有など、地道でシンプルな取り組みが、巨額返還というホラーを回避する鍵になります。ぜひ今回の記事を参考に、自院の現状を改めて点検してみてください。
もし本記事で不明な点や個別のお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
適時調査を前向きな成長の機会と捉え、上手に乗り切っていきましょう。