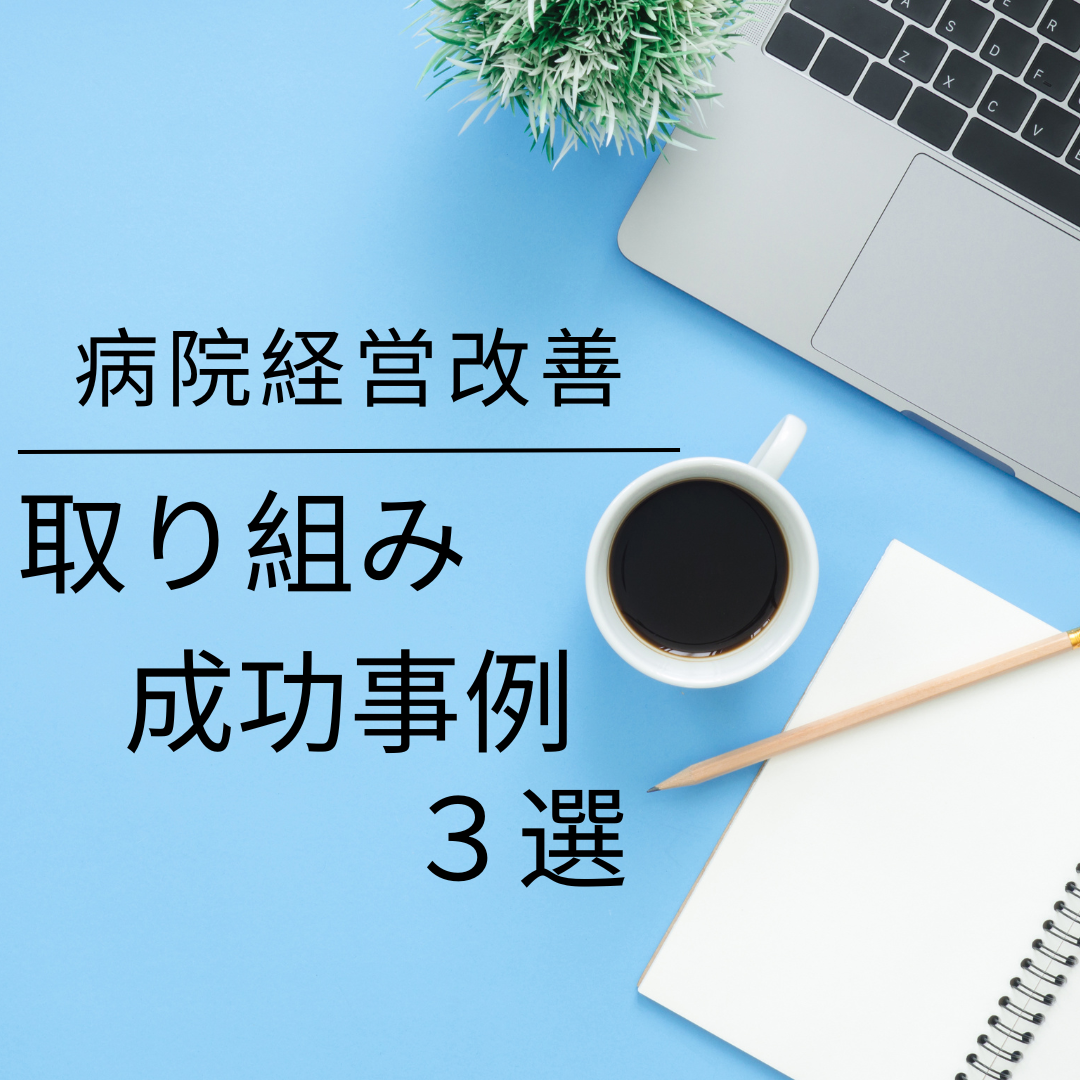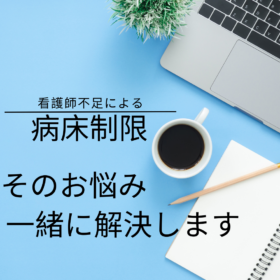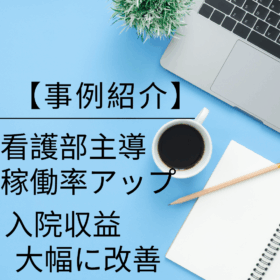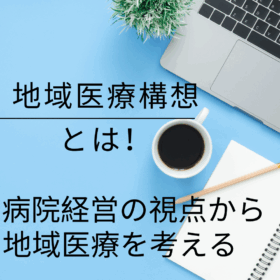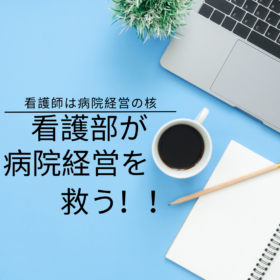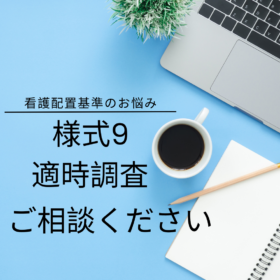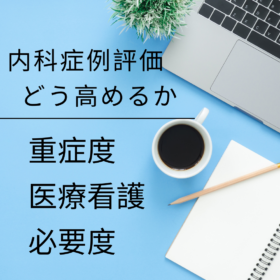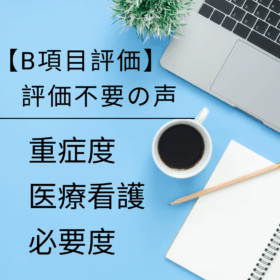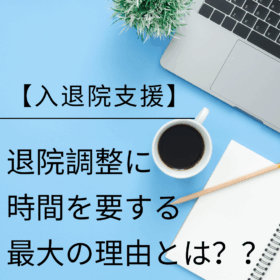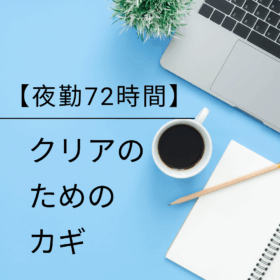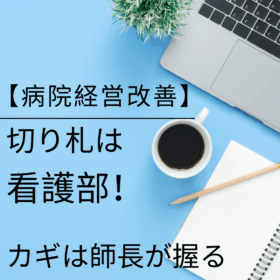病院は地域にとって、なくてはならない重要なインフラです。しかし、多くの病院は今、深刻な経営危機に瀕しています。診療報酬改定、急激な物価高騰、人件費の高騰、人材不足など、病院を取り巻く状況はたった1年の間でも刻々と変化しています。
関連するいくつかの記事では、看護師不足の知られざる現場や診療報酬改定後の病院経営状況について、深刻な現場を解説してきました。
関連記事↓↓↓
こうした状況の中、地域のニーズや自院の役割を分析し、経営改善に成功している病院も少なくありません。
この記事では、経営改善に成功した病院の取り組み事例を3つ紹介します。経営改善のための具体的な道筋を立てるため、どのように現状を分析しどのような方向性で改善を進めるべきか、実際の事例からみていきましょう。
※ご紹介する事例は、弊社コンサルタントが実際に現場に入り対応支援した事例です。現状分析、改善計画の立案から経営改善に至るまで、お気軽に弊社にお問合せください。

Contents
病院経営改善のための現状分析
病院経営の改善に取り組む第一歩は、現状の正確な把握です。特に重要なのが「地域の医療ニーズ」と「病床稼働率」の2つです。これらは経営方針の根幹を左右する要素であり、改善策の優先順位を決めるための土台となります。
もし病床稼働率が85%を下回っている場合、向上できないのであれば病床数削減を検討しなければなりません。入院収益は病院の主な収入源であり、病床稼働率の上下により病院の収入は億単位で変わるからです。
しかし、病床数を削減するか否かは、地域の医療ニーズや病床稼働率が低い本当の原因をしっかり分析して判断する必要があります。
病床機能が地域の医療ニーズに合致しているか
地域のニーズと現在の病床機能が乖離している場合には、病棟の一部を別の機能に再編することが選択肢となります。特に近年では、急性期から回復期(地域包括ケア病棟やリハビリテーション病棟)への転換を図る医療機関が増加しています。これは、地域包括ケアシステムにおける「中間施設」としての役割を果たすことで、地域ニーズに応えると同時に経営の安定化を図ることができるためです。
しかし、病床機能の再編を検討している病院経営者は多くいらっしゃるものの、「どのように再編を進めるべきかわからない」「変更したもののうまく運用できていない」という声も多く聞かれます。病床機能を地域ニーズに有ったものに再編しても病床稼働率が改善しない場合、入院患者数が増加しない原因は他にあるのかもしれません。
病床稼働率が低い隠れた原因
病床稼働率が改善しないのは、現場の受け入れ体制に原因がある場合もあります。たとえば、何らかの理由で、入院患者を十分に受け入れられていない状況があるかもしれません。このようなケースでは、看護部長や副部長、各病棟の看護師長が実際の運用状況をよく把握しているため、現場スタッフへのヒアリングを通じて実態を把握する必要があります。
このような分析により、「今よりも入院患者数を増やせるかどうか」を見極めることはとても大切です。
それでは、入院患者数増加で病床稼働率を向上させ、病院経営を改善した事例を3つみていきましょう。

病院経営改善事例その① – 病床稼働率を上げるための機能転換
関東圏にある、稼働病床数約130床の公立病院(許可病床数180床)の事例をみてみましょう。
この病院は3つの病棟を抱え、急性期一般入院基本料1(看護配置7対1)の施設基準を維持していました。しかし、周辺にある大規模な急性期病院や大学病院と競合しており、その中で急性期一般入院基本料1を維持するために、稼働率が下がっていました。
さらに、診療報酬上求められる「重症度、医療・看護必要度28%」の基準を満たすためには患者数を減らすしかなく、稼働率は60%を切っている状態でした。
病床機能転換
2024年度の診療報酬改定により、この病院では急性期一般入院基本料1の維持が困難であることが明確となりました。
そのため、病院は戦略的な判断として入院基本料2(看護配置10対1)へと転換を決断しました。これにより、現行の看護師数を維持したまま、より多くの入院患者を受け入れられるようになりました。
経営危機の共有と目標の明確化
経営改善に向けてまず行ったのは、赤字やキャッシュフローの実態を職員にオープンにし、経営の危機感を全職員と共有することでした。その上で、各診療科ごとに入院患者数の明確な目標を設定しました。
更に、院長による医師面談とコンサルタントによる看護師長面談を実施し、目標達成に関する不平不満と要望を出せるようにしました。
発生したハレーション
この過程で、現場の医師たちからは「目標達成が難しい理由」が多く挙げられ、看護部からも「ナースステーションから遠い病室には患者を入れたくない」など、ネガティブな意見が多く出てきました。「どうすれば受け入れられるか」ではなく、「なぜ受け入れられないのか」に終始する空気が課題として浮き彫りになったのです。この状況下で板挟みとなる看護師長を支えながら、経営陣と現場の間の信頼関係を再構築していきました。
改善の兆しと成果
ネガティブな意見がある一方、医師からは目標達成に向けた具体的な方策や前向きな要望が徐々に出るようになり、病院全体で数値目標を明確に設定しながら、実行と調整を繰り返すことができました。それに伴い看護現場の「現場力」も向上し、患者受け入れに対する責任感が浸透していきました。
その結果、2024年6月には入院患者数が大きく増加し始め、7月には目標数を上回る実績を達成。物価高騰の影響で収支は依然厳しい状況でしたが、病床稼働率85%が現実的な視野に入るまでに改善しました。
現場への影響と院内文化の変化
稼働率の向上により現場の忙しさは増しましたが、看護師たちはその変化に適応しました。「以前の患者数の状態なんて、もう想像できない」との声も出るほどになり、患者を受け入れなければいけないという責任感が強くなりました。
特にインフルエンザ流行時や年末年始といった繁忙期でも、「どうしたらもっと受け入れられるか」といったポジティブな会話がされるようになり、現場の主体性が大きく向上したのです。
成功の本質は「病院のあり方の再定義」と「経営と現場の一体化」
この事例から明らかなように、病床稼働率を向上させるためには、自院が「どのような病院であるべきか」を再定義し、その役割にふさわしい患者を受け入れる体制を構築することが不可欠です。
自院の「あるべき姿」に照らし合わせ、目指すべき方向と優先順位を明確にすることが現場の意識改革にもつながります。また、経営陣が赤字やキャッシュフローなどの「不都合な真実」も含めて現場と共有し、全職員が経営の現実に当事者意識を持つことで、組織全体の推進力が生まれます。明確な数値目標を設定し、それを現場とともに実現していく姿勢こそが、最終的に持続可能な病院経営につながるのです。

病院経営改善事例その② – 院内の運用見直しで実現した稼働率向上
続いては、約30床の地域包括ケア病棟を運用している病院についてみていきましょう。
もともとはコロナ禍で確保されていた専用病床を、感染症対応の必要性が落ち着いたタイミングで地域包括ケア病棟に転換。しかし、転換後もしばらくは稼働率が上がリませんでした。
院内の運用見直し
まず取り組んだのが、「どのような患者を地域包括ケア病棟で受け入れるべきか」を明確にすることでした。医事課・看護課・リハビリテーション課が連携し、急性期病棟から転棟可能な患者の選定基準を整理したシートを作成し、日常的に運用しました。
さらに、地域包括ケア病棟の役割や治療の継続に関してドクターの理解を促すことにより、病棟間での患者移動の判断がスムーズになり、地域包括ケア病棟の「受け皿」としての機能が強化されました。これにより、急性期病棟での病床確保にもつながり、病院全体の病床稼働率向上にも寄与しました。
運用見直しにより病床稼働率は向上させられる
この事例が示しているのは、特に200床未満の地域包括ケア病棟においては、院内の運用を見直すことで病床稼働率を大きく改善できるということです。
入院患者の適切な選定とスムーズな転棟の仕組みを作ることにより、空床を防ぎ、病院全体の病床運用の最適化につながります。
病院経営改善事例その③ – 看護師配置の見直しで実現した稼働率向上
最後に、関東圏の急性期病院の事例をみてみましょう。
この病院では、許可病床数が300以上あるものの実際の運用病床数が240となっていました。
看護師配置の見直し
この病院においては、40床以上の病床がありながらも、稼働病床が30前後の低水準に落ち込んでいる病棟が複数ありました。
そこで、現場の看護師に対して危機感の共有と説明を徹底し、看護師配置の見直しにより、まず届出済の稼働病床数まで運用数を増やすことができました。
発生したハレーションと目標達成
改善を行う中で、当然現場におけるハレーションが発生しました。現場の看護師に対する説明会では、「人が足りていないのをわかっているんですか!?」という意見や感情的な意見も多く出てきました。
しかし、板挟みになる看護師長たちの立場を守りつつ説明を徹底し、配置運用を見直すことで、目標を達成することができました。この病院では、許可病床数の達成が視野に入るまでに改善が進んでいます。

経営改善努力は現場にも良い影響を及ぼす
この記事では、病床稼働率の向上により病院経営改善に成功した事例を3つ見ることができました。地域ニーズにマッチした病床機能に再編し病床稼働率を向上させるには、現場の医師や看護師を含めた危機感と目標の共有、そして現場の意識改革が不可欠です。
改革におけるハレーションは当然予想されますが、数値目標を明確に掲げその目標に向かって改善しながらアジャストしていくことにより、現場一人ひとりのやりがいや責任感が強化され、「現場力」が向上していきます。
リージョンマネジメントでは、看護師現場の豊富な経験を持つコンサルタントが、現場から病院経営を改善するコンサルティングをご提供します。お気軽にお問合せください。