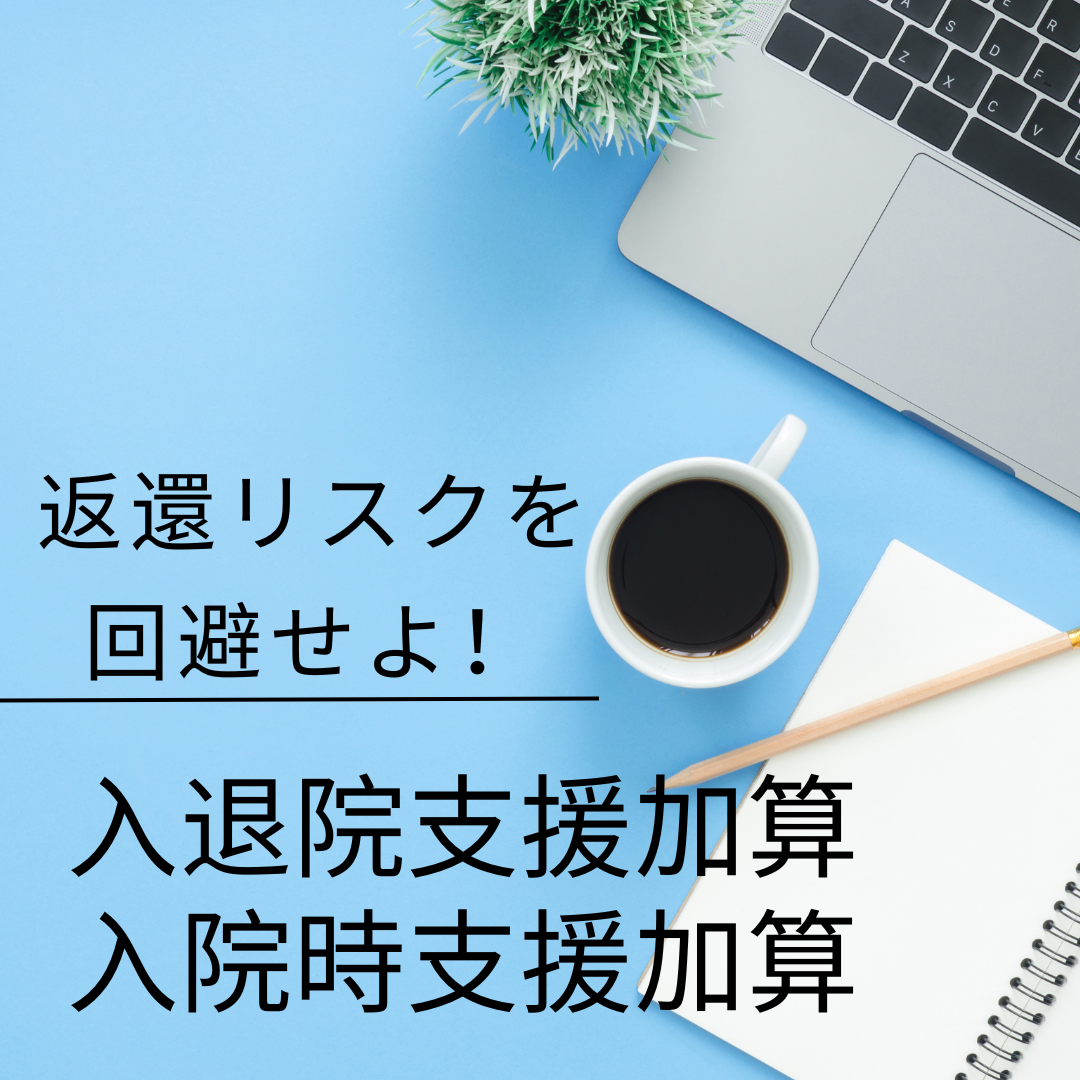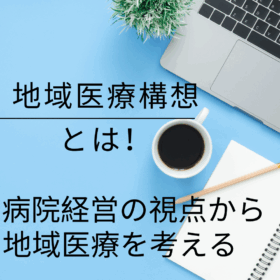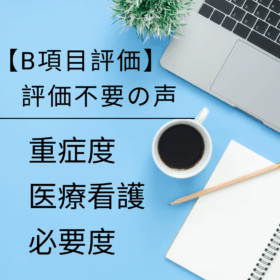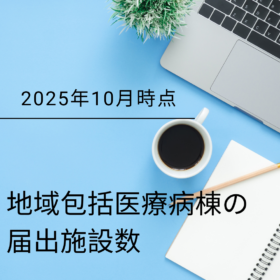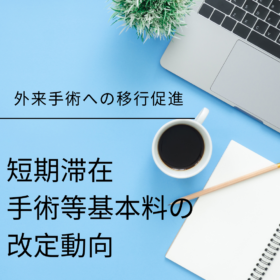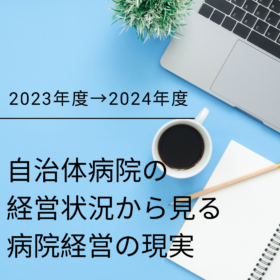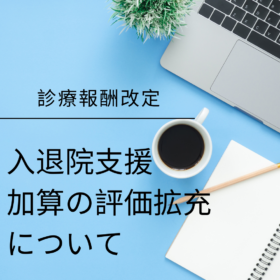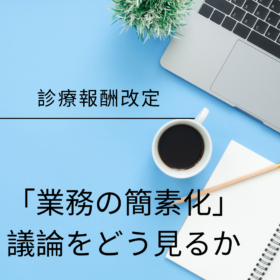こんにちは。病院経営コンサルタントの勝又です。本日は、地域連携室が関わる診療報酬の加算について説明いたします。
YouTubeでも動画をアップしておりますので、ご覧ください。
Contents
はじめに:地域連携室の加算はなぜ複雑か?
地域連携室が関わる診療報酬の加算は、入退院支援加算や入院時支援加算、患者サポート体制充実加算など、多岐にわたります。とくに「専従」「専任」の違いや、「病棟単位での配置」などを正しく理解していないと、適時調査などで返還リスクが生じる可能性があります。実際、施設基準や要件の細部が分かりにくいため、算定要件を満たしているつもりでも指摘されるケースは少なくありません。
この記事では、地域連携室が中心となって算定する以下の加算について、人員配置基準や兼務の可否などを整理します。
- 入退院支援加算1・2
- 入院時支援加算(1・2)
- 患者サポート体制充実加算
入退院支援加算1と2の違い、病棟ごとの担当者配置、非常勤スタッフ2名以上による専従みなし規定など、「専門的だけれどわかりにくい」ポイントを噛み砕いて説明します。経営陣や事務・医事課スタッフ、看護管理者の皆さんが返還リスクを回避し、適切に加算を算定できるよう、ぜひご参考ください。
1. 「専従」と「専任」の基本をおさえる
はじめに、診療報酬の施設基準で頻出する「専従」と「専任」という用語の意味を明確にしておきましょう。この2つを混同すると、適時調査の指摘対象になりやすいです。
● 専従(せんじゅう)
- 定義:特定の業務または部署に「もっぱら」従事すること。基本的に他の業務や他部署との兼務は認められません。
- ポイント:
- 他の業務へ時間を割くことは不可(原則)。
- その職員が専従で従事する時間帯は、当該業務に専念していなければならない。
● 専任(せんにん)
- 定義:特定の業務を「主たる担当」として任命された職員のこと。ただし他の業務を一部兼務してもよいとされています。
- ポイント:
- あくまで”主たる業務”が専任業務であることが必要がある。
- ただし、施設基準で定められた活動時間が決まっている場合(例:認知症ケア加算1の16時間など)は、その時間帯は当該業務に専念しなくてはならない。
- それ以外の時間や範囲であれば兼務も可能。
たとえば「入退院支援加算1」でいう「入退院支援部門に専従の看護師を配置する」という場合は、その看護師が他部署を兼ねたり、病棟夜勤などを行うのはNGです。一方で「専任」であれば、一部の兼務は許容されるケースもあります。この違いを理解しておくと、後段で出てくる人員配置がスムーズに把握できます。
2. 地域連携室に関連する主な加算
地域連携室では、以下のような診療報酬加算が関わることが多いです。
- 入退院支援加算1・2(・3)
- 入院時支援加算(1・2)
- 総合機能
- 介護支援連携指導料
- 患者サポート体制充実加算
- 重症患者初期支援充実加算
- 退院時共同指導料II
…など
このうち本記事で注目するのは、特に人員配置基準が複雑な入退院支援加算1・2、入院時支援加算、患者サポート体制充実加算の3つです。まずは、入退院支援加算1について見ていきましょう。
3. 入退院支援加算1:専従・専任職員の配置と病棟担当
入退院支援加算1(および2)を算定するには、まず「入退院支援部門」を院内に設置し、その部門に必要な人員をそろえる必要があります。加算1は要件がより手厚くなっており、人員配置の基準が満たせず、加算1の届出ができていない病院様も多くあります。
● 入退院支援部門の人員:専従+専任
「入退院支援部門」には、以下いずれかの組み合わせが必須となります。
- 専従の看護師(Aさん) + 専任の社会福祉士(Bさん)
- 専従の社会福祉士(Bさん) + 専任の看護師(Aさん)
要するに、専従者と専任者で看護師・社会福祉士の組み合わせをそろえる格好です。専従が看護師なら専任は社会福祉士、逆に専従が社会福祉士なら専任は看護師、というように、2職種をそろえるのがルールになっています。そして、そのうち片方は他業務を兼務しない「専従」である必要があります。
■ 非常勤2名以上で専従とみなせるケース
厚労省の基準では、週3日以上かつ所定労働時間(週22時間以上)で勤務している非常勤スタッフを2名以上組み合わせて、1名の常勤専従者とみなすことも認められています。人員確保が困難な病院でも、非常勤者の活用次第で専従要件を満たせる仕組みです。ただし、常に専従としての業務に対応できるようシフトを組むなど、実務上の管理が必要です。
● 病棟ごとの担当配置(加算1の場合)
入退院支援加算1を算定するにあたっては、各病棟に専従の退院支援を担う専任者を配置する要件があります。ここでのポイントは「各病棟に専従する専任者」という表現が厄介な点です。
- 実質的には「病棟専任担当者」は当該病棟での退院支援・地域連携業務に専従する必要があります。(原則)
- 一人で2病棟(合計120床)まで担当可能(1病棟あたり60床を想定)。
- 20床未満のICUやHCUなどは、病棟数の計算から外してよいが、病床数には含める。
たとえばICU 8床 + HCU 10床 + 一般病棟60床を持つ場合、ICU・HCUは「病棟数」にカウントされず、一般病棟1つ(60床)と合わせて合計78床なので、1名の専任者が担当できる可能性がある、という計算になります。
● 病棟担当専任者の「兼務」可否
通知では、病棟に専任で配置されている者は、入退院支援部門の専従職員とは兼務できないが、入退院支援部門の専任職員を兼ねることは可とされています。たとえば、「入退院支援部門の専任者Bさん」がそのまま「病棟担当の専任者」を兼務する、というケースは許容されるわけです。一方、専従者Aさんが病棟担当を掛け持つのはNGとなります。
また、専従・病棟担当の専任者のいずれも「病棟夜勤の業務」を兼ねることは認められないことが多いようです。稀に「日中は地域連携業務、夜は病棟勤務」のような体制を取っている施設がありますが、これは専従や専任要件と矛盾し、適時調査で指摘・返還対象になり得ます。
4. 入院時支援加算:入院前支援で上乗せの算定が可能
次に、「入院時支援加算」について解説します。「入院時支援加算」は、「入退院支援加算1または2」を算定している患者に対し、入院前に患者支援を実施した場合に上乗せで算定できる加算です。
- 入院時支援加算1: 240点
- 入院時支援加算2: 200点
いずれも、入退院支援加算を算定する患者のうち、「予定入院」してくる際に、入院前支援などを行うことで算定が可能です。
● 「入退院支援加算2だから入院時支援2しか算定できない」は誤り
実は「入退院支援加算2の届出だから、入院時支援加算2しか算定できない」というわけではありません。入退院支援加算1または2の施設基準を届け出ていれば、入院時支援加算1か2は支援の内容に合わせて算定できます。
よって、A患者には入院時支援加算1、B患者には入院時支援加算2、といった運用が同一病院内で可能です。ここではあくまで「入院時支援加算を届け出しているかどうか」が第一のチェックポイントになります。
● 入院時支援加算に必要な人員(200床以上/未満で異なる)
■ 200床以上の病院
- 「専従の看護師が1名以上」または「専任の看護師+専任の社会福祉士」のペア配置
■ 200床未満の病院
- 「専任の看護師1名以上」のみでOK
つまり200床未満の病院にとっては、入院時支援加算の人員要件は比較的ハードルが低いです。200床以上の場合は、専従看護師を置くか、看護師・社会福祉士の専任ペアを置くかことで要件を満たします。
■ 兼務に関する疑義解釈
200床以上の病院が「入院時支援加算を満たすため専従の看護師を配置した」場合、その専従看護師は入退院支援部門の他の専従・専任を兼ねることはできません。一方、専任の看護師と社会福祉士をペアで配置するパターンなら、病棟専任を兼務しているケースなど一定の範囲で兼務が認められています。ただし専任業務を3つ以上掛け持つのは不可とされる点が注意点です。
5. 患者サポート体制充実加算:相談窓口と専任スタッフ
最後に、地域連携室と並行して運用されやすい「患者サポート体制充実加算」について触れます。こちらは病院の”患者相談窓口”を強化し、十分な相談体制を整備している場合に入院初日に加算できるものです。
- 患者サポート体制充実加算:入院初日 70点(令和6年度時点)
● 常時相談対応可能な体制
加算算定のポイントは「患者や家族がいつでも相談できる窓口を、標榜時間内は無人にしない」ことです。そのため、患者相談窓口に専任スタッフを常時1名以上配置しなければなりません。看護師やMSW(社会福祉士)などでもよく、「医療相談員」として配置されるケースがあります。
● 他業務との兼務は可能だが、窓口を空けない工夫が必要
患者サポート体制充実加算の専任担当者は、完全な”専従”とまでは規定されていません。そのため、リスクマネジメント(医療安全対策加算2の場合に限る)などと兼任していても構いません。ただし、たとえば会議や病棟巡回などで席を外す際も、必ず別の担当者を窓口に置く体制が必要です。窓口が無人になると加算要件を満たさなくなる可能性があるため、院内の連携をしっかり確保しておく必要があります。
6. まとめ:パターンを整理して返還リスクを減らそう
ここまで解説してきたとおり、地域連携室(入退院支援部門)に関わる加算の人員配置要件は複雑です。専従と専任の区別、あるいは病棟担当者の配置要件などを誤解したまま運用すると、適時調査で返還を指摘されるリスクが高まります。
特に注意したいポイントを整理すると、以下のようになります。
- 専従職員は他業務を原則兼務できない
- 夜勤や管理業務との兼務は不可。
- 専任職員は主たる業務が当該加算業務であればOK
- ただし、配置時間が定められている場合はその時間帯は従事し続ける必要がある。
- 病棟担当者は一人につき2病棟・合計120床まで、原則、専従扱い
- 20床未満のICU・HCU等は「病棟数の算定」から外せるが、「病床数」には含むルール。
- 非常勤2名以上で専従換算できるケースがある
- 週3日以上勤務かつ週22時間以上の所定労働時間を満たす非常勤スタッフを2名以上組み合わせる。
- 入院時支援加算1・2は患支援内容により患者ごとに選択可能
- 入退院支援加算2だから入院時支援2のみしか算定できない、という制限はない。
- 患者サポート体制充実加算は相談窓口の常時配置を確保
- 担当者が他業務で席を空ける際は代替要員を置く。
自院の病棟数・病床数、看護師・社会福祉士(MSW)の在籍状況などを踏まえ、「どの職員を専従にするか」「誰を病棟専任にするか」「兼務は成り立つか」「非常勤スタッフ2名でカバーするか」などを一度見直しておくことをおすすめします。とくに入退院支援加算1の要件は手厚いため、複数の専従・専任を組み合わせる際に齟齬が生じやすいです。
おわりに:複雑なルールこそ、現場と管理部門で共有を
入退院支援加算や入院時支援加算、患者サポート体制充実加算などは、地域連携室が中心となって算定を進めますが、実際には病棟看護師長や看護部管理者、医事課・経営企画部門との連携が不可欠です。誰を専従とするか、夜勤シフトに入れるかどうかなど、部署をまたいだ調整が発生するからです。
そこで大切なのは、「専従」と「専任」の明確な区別や配置枠の正しい理解を、全員で共有しておくことです。複雑に見えるルールでも、要点を押さえていれば返還リスクをぐっと減らせます。適時調査に備え、あらためて院内で人員体制を点検・確認する機会を設けるのはいかがでしょうか。
院内外の連携を円滑にし、患者さんのスムーズな入院や安心できる退院支援を実現するためにも、制度のルールを正しく把握したうえで、よりよい運用を目指していただければ幸いです。