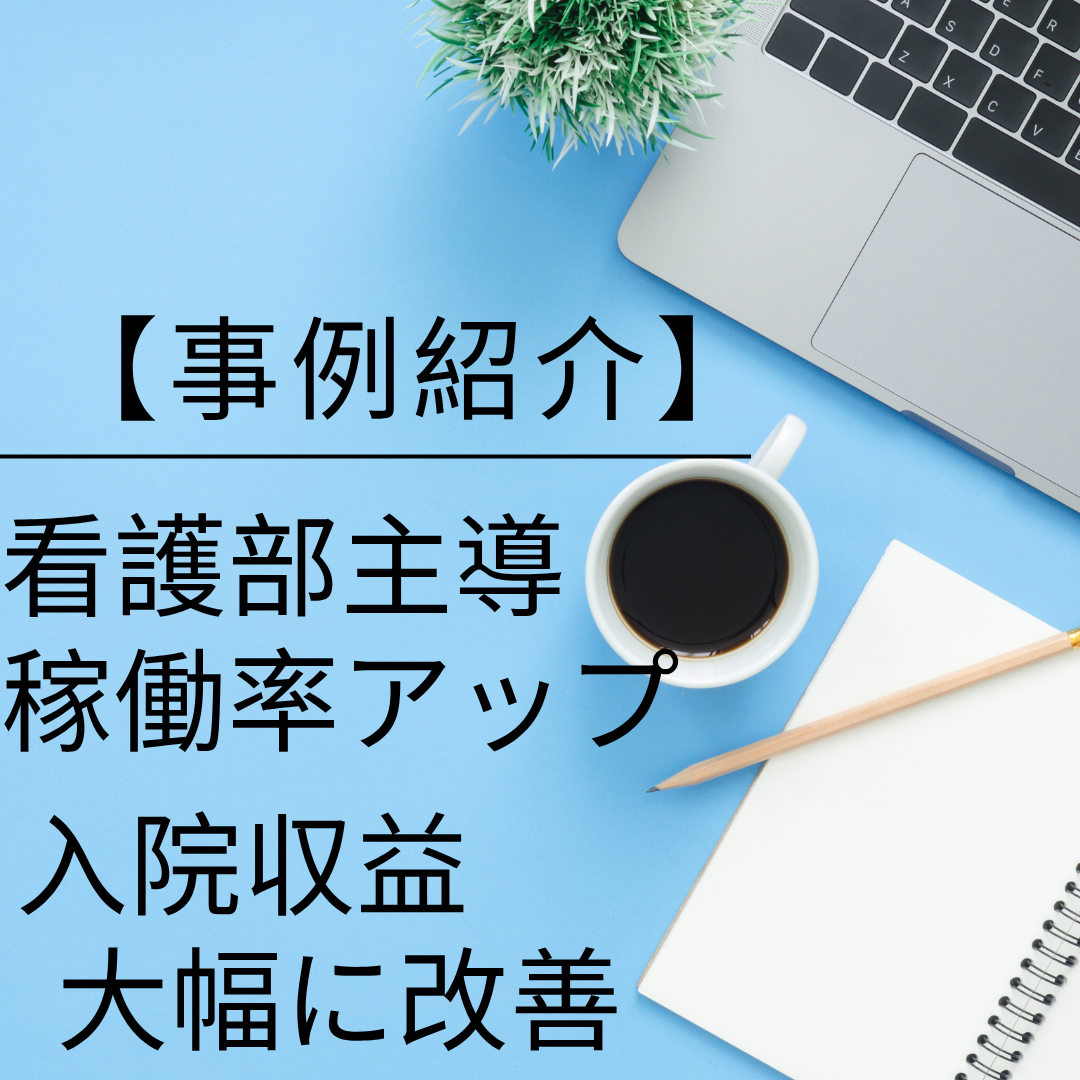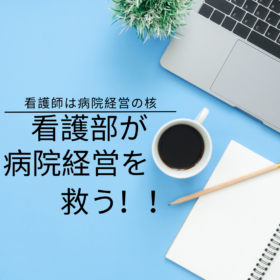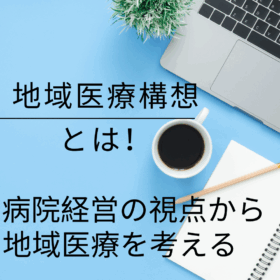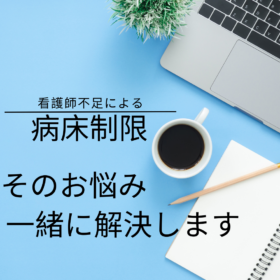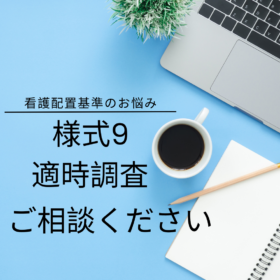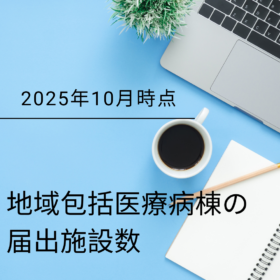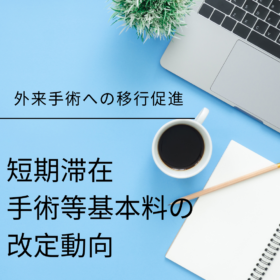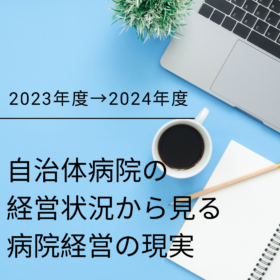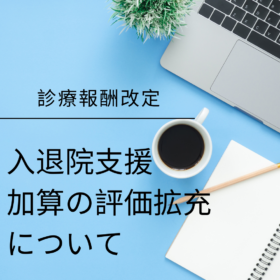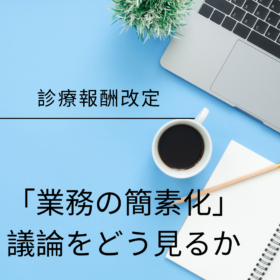Contents
「稼働率が上がらない…」悩み続けた急性期病院が、なぜ4億円の入院収益を改善できたのか?
「急性期入院基本料1は、絶対に維持したい」
これは、とある地方中規模病院の院長の強いこだわりでした。
その病院は、一般病床と地域包括ケア病床を有する120床の病院で、内科・外科・整形外科・脳外科・泌尿器科など、バランスよく診療科が揃った急性期病院です。
しかし現実は厳しく――。
・医師の確保は年々難しくなり、
・看護師側も、ナースステーションから遠い病室には患者を入れられない、というローカルルールが常態化
その結果、ベッドは空いているのに患者が入らないという事態が続き、稼働率は60%と低迷していました。
本来の機能を果たしきれていないことへの焦り、そして収益確保への危機感。
この状況を打破すべく、病院はある一手を打ちました――。
看護部長が前面に立ち、全職種を巻き込んだ「入院強化プロジェクト」
この病院が行った最大の変化――
それは、入院患者数を増やすことを「病院全体の共通目標」とし、戦略的に動き出したことでした。
まず、病院の中に“経営と現場をつなぐ新たな推進チーム”(以下、経営推進チーム)を立ち上げました。リーダーには現職の看護部長が専従で就任し、看護部長職は別の管理職に引き継がれました。病院全体のベッド稼働を改善するために、「入院強化プロジェクト」を始動したのです。
このプロジェクトでは、
-
各診療科に入院患者数の目標値を設定し、
-
その達成に向けた具体的な行動計画を提出してもらいました。
-
看護部やリハビリ部門、事務部門などすべての部門にも同様に目標を提示し、面談を通じて責任の所在と協力体制を明確化しました。
「まず患者を受け入れる」ことに注力する――
プロジェクトの始動により、病院運営の優先順位が明確に変わりました。それまでの運用では、たとえば認知症患者の早期退院を促したり、ナースステーション近くの病床が空いていないと入院を見送ったり、あるいは看護必要度の維持が難しくなることを理由に軽症患者の受け入れを控えるなど、「施設基準を守るために、患者を慎重に選ぶ」ような運用が日常的に行われていました。
結果として、「入院を断っても仕方がない」という空気が、現場に根付いてしまっていたのです。
しかし、このプロジェクトでは「まずしっかり患者を受け入れ、稼働率を上げる」ことを最優先に、ベッドコントロールを中央管理体制へと移行しました。
看護部が中心となって入院病棟や受け入れ先を判断し、全病棟の空床状況を横断的に把握しながら、最適な病棟配置を一元的に指示できる体制が整いました。現場では「なぜこの病棟に?」と問うのではなく、「快く受け入れること」を徹底、看護部主導で現場の声を生かしながら、運用の見直しと工夫が進められていきました。
加えて、地域包括ケア病床の施設基準も再整理し、転床ルールを明確化。
高齢患者や在宅復帰支援が必要なケースにも、より積極的に対応できる体制が整備されました。
もちろん、現場には戸惑いや不安もありました。しかし、「ナースステーションから遠いから入れられない」といった運用は見直され、“入院を断らない文化”の再構築が進みました。高齢化が進む地域において、今後さらに重度・認知症等を有する患者の増加が見込まれる中、「まず看護師として何ができるか」を前向きに考える姿勢が、徐々に広がってきたのです。
施設基準を守るために患者を制限するのではなく、地域の医療ニーズに応える――
その本来の使命に立ち返ったことで、結果的に稼働率も大きく上昇し、病院全体に前向きな空気が浸透していきました。たしかに、入院基本料は1から2に下がったという現実もあります。
しかし、地域に必要とされる患者をしっかり受け入れられるようになったことで、現場の意識は「できない理由を探す」から「どうすればできるかを考える」思考へと大きく転換し、そしてそれが、劇的な稼働率の改善へとつながったのです。
かつては「施設基準を守るためのベッドコントロール」が第一に考えられていましたが、今では「まずは受け入れる。そのうえで、どう施設基準を満たすかを考える」という、柔軟で前向きな姿勢が根付きつつあります。そして、仮に施設基準を満たせない状況が発生した場合には、その都度関係部署で協議を行い、改善策や仕組みの見直しへとつなげていく。そんな、実践的で持続可能な運営スタイルが、病院全体に少しずつ定着してきているのです。
わずか3か月で稼働が急上昇、入院収益は前年比「4億円以上」の改善
この取り組みは、4月に経営推進ユニットを立ち上げてから、わずか2か月後の6月には成果が見え始め、7月には一気に軌道に乗り始めました。平日・休日それぞれの稼働目標を明確に設定し、ベッドコントロールを一元管理に切り替えたことに加え、「優先順位の明確化」と「日々の現場との対話・情報共有」が特に大きな効果を発揮しました。
中心となった経営推進チーム(元看護部長が率いる)は、毎日のように各部署へ声かけを行い、入院数や稼働状況をメールで共有。“数字の見える化”を通じて、現場のモチベーションを着実に引き上げていったのです。
その結果、前年60%だった稼働率は、75%にまで上昇
2024年度の入院収益は、2023年度と比較して約4億円以上の改善を記録しました。
この数字には、入院患者数の増加に加え、加算取得による診療報酬の上振れも含まれています。
“やりたい医療”から、“必要とされる医療”へ
この取り組みから学べるのは、「施設基準を守るために自院の理想やルールを優先する」といった運用から脱却し、「まず患者を受け入れる」というシンプルな行動を、全職種で徹底したことが病院全体の回復力を引き上げたという事実です。
看護師が経営の最前線に立つ
この取り組みでもう一つ注目すべき点は、「看護師が経営の最前線に立った」ことです。
ベッド運用、受け入れ判断、患者導線――病院の実働部門である看護部が中心となり、さらに元看護部長が率いる経営推進チームが現場と一体となって動いたことで、“現場感のある経営改善”が実現しました。「経営は事務部門の仕事」と分けるのではなく、看護部門こそが日々の運用を通じて経営に直結する意思決定に関わるべきだという姿勢が、組織全体に共有されたのです。
その結果、誰もが「自分ごと」として病院経営に向き合える環境が生まれ、職種の垣根を越えた協働が進みました。
まさに、看護部が動けば、病院が変わるという変革の象徴となったのです。
「うちの病院も、変われるかもしれない」
そう思ったときが、変化の始まりです。組織の構造改革、稼働率改善、看護部主導の経営参画――
ご相談は、リージョンマネジメント株式会社までお気軽にどうぞ。