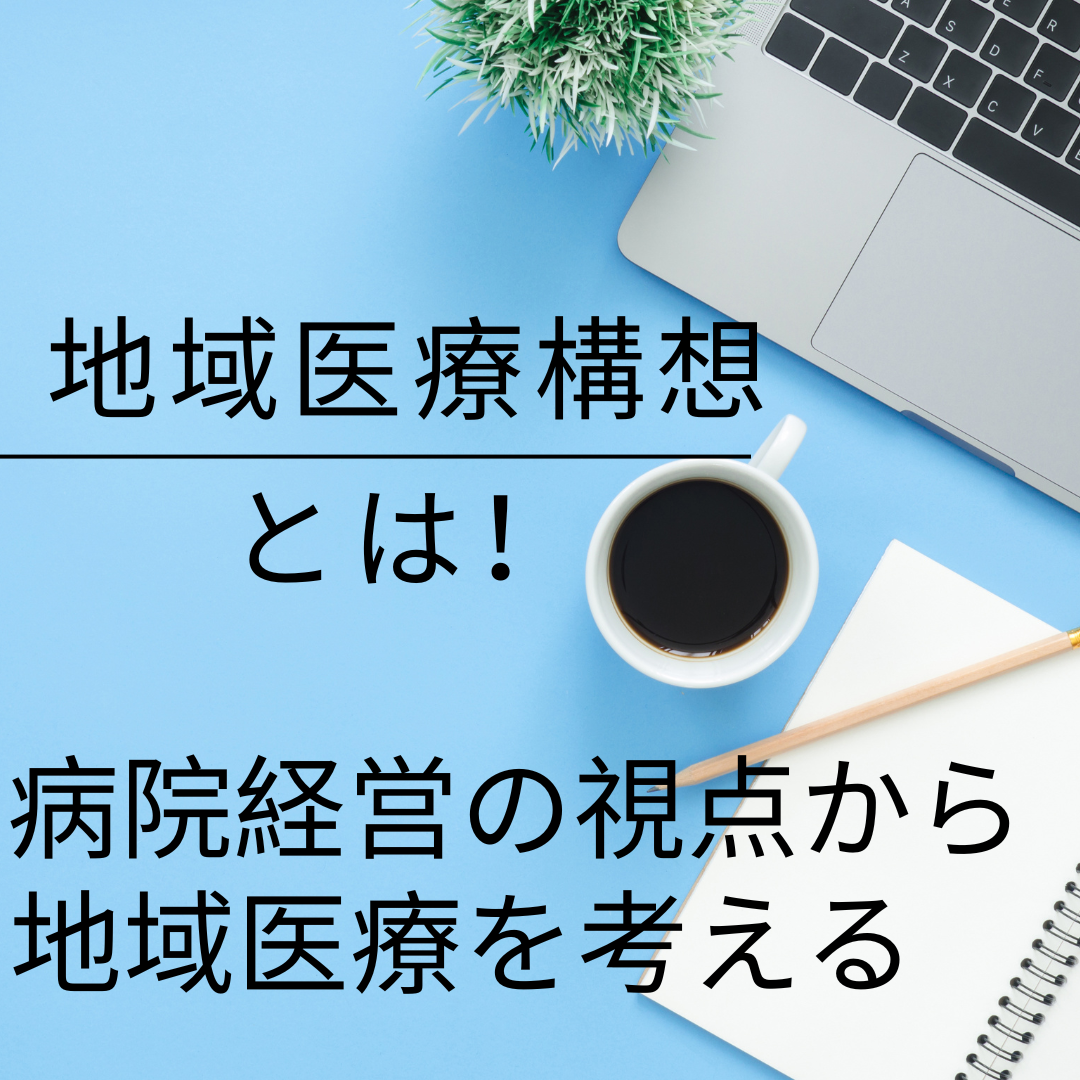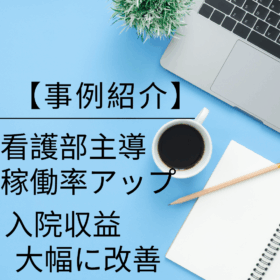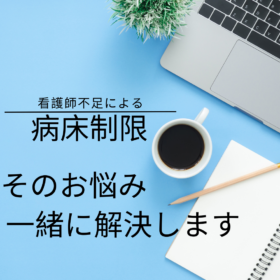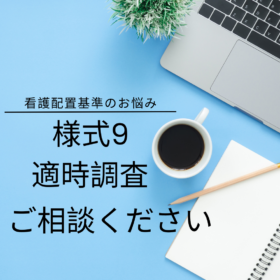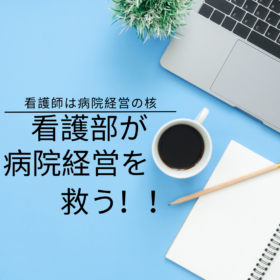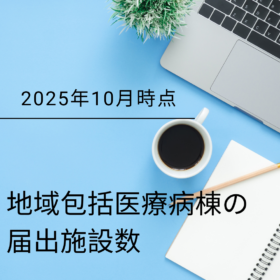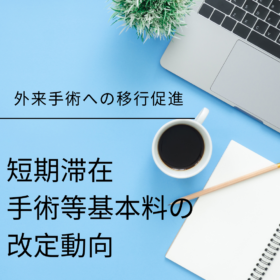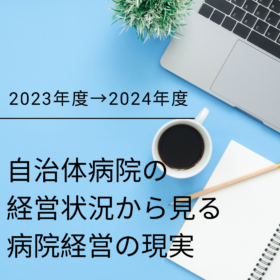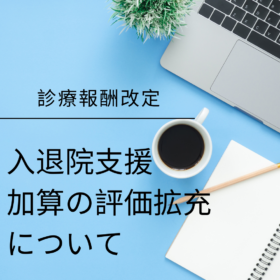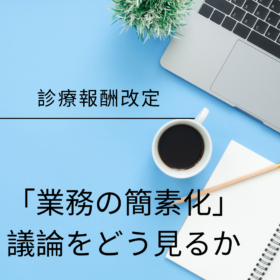2025年、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となり、日本は本格的な超高齢社会に突入します。この年には、75歳以上の人口が約2,200万人に達し、65歳以上の高齢者が全人口の約3分の1を占めると推計されています。これに伴い、医療・介護の需要は急激に高まり、国民医療費は2025年に60兆円に達する見通しです。
一方で、少子化の進行により生産年齢人口が減少し、医療従事者の確保がますます困難になることも予測されています。人手不足によるサービスの質の低下、地方を中心とした病院の統廃合、そして在宅医療や地域医療へのニーズの急増——こうした多面的な課題が医療現場を圧迫しつつあります。
このような厳しい社会構造の変化を前にして、持続可能な医療提供体制をいかに構築するかが、今まさに問われています。その中心的な取り組みが「地域医療構想」です。この記事では、この地域医療構想の目的と現状について、より具体的に掘り下げていきます。
Contents
地域医療構想とは?〜2025年を見据えた医療体制の再編〜
地域医療構想とは、団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となる2025年を見据え、全国の都道府県単位で地域の医療提供体制を再構築する国の取り組みです。
少子高齢化が進行する中、医療・介護の需要は今後ますます増加すると予想される一方で、医療人材や病床といった供給資源は限られています。こうした背景から、限られた医療資源を有効に活用し、効率的かつ質の高い医療を地域全体で提供する仕組みづくりが求められています。
地域医療構想はその一環として、医療機関の機能分化と連携を促進し、地域の実情に即した病床の適正配置を実現することを目的としています。
医療圏ごとに策定される地域医療構想
構想の実施単位は「二次医療圏(医療圏)」であり、都道府県はそれぞれの医療圏ごとに、将来(主に2025年時点)に必要となる病床機能の推計を行っています。この推計に基づき、以下の4つの機能別に病床の再編が進められています。
- 高度急性期(大学病院や特定機能病院など)
- 急性期(地域医療支援病院など)
- 回復期(主にリハビリテーション・在宅復帰支援など)
- 慢性期(長期療養など)
この枠組みにより、各病院が自身の担うべき役割を明確にし、地域全体で「必要な時に、必要な場所で、必要な医療」が提供できる体制を目指しています。国がこの医療構想を実現させるために活用してきているのが、2年に1度の診療報酬改定です。
地域包括ケア病床への転換と診療報酬
地域医療構想を具現化する手段のひとつが、診療報酬制度の活用です。特に、診療報酬改定により、急性期病床から回復期・地域包括ケア病床への転換が促されてきました。2014年以降、急性期医療から地域包括ケアへの機能転換が推進され、国が推計する必要数には近づいていると言えます。それでも、国が意図した地域包括ケアと実際の運用に隔たりがあるという指摘もあるのが現状です。
こうした現状を背景として、地域包括ケア病床が果たすべき各機能の強化が図られています。
地域包括ケア病床には、「ポストアキュート(急性期直後)」「サブアキュート(慢性期へ移行する患者の受け入れ)」「在宅復帰支援」の3つの主要機能が求められ、年々その要件は厳格化されています。2024年度診療報酬改定では、サブアキュート機能をより明確化するために看護必要度の基準も引き上げられ、施設基準を遵守するためにより高度なベッドコントロールが求められるようになりました。
これに対して、医療機関現場からは「ルールが複雑化しており、運用しづらい」といった声も上がっています。実際、病床転換を進めるには、医療の質を担保しながら職員教育や業務体制の見直しを行う必要があり、単なる制度的誘導だけでは限界があります。
また、今後ますます需要が高まると見込まれる在宅医療や訪問看護などとの連携強化も、地域医療構想における重要な課題の一つです。地域包括ケアの本質は、病院完結型の医療から、地域ぐるみで患者を支える共助型医療「地域完結型」への移行にあります。

2040年を見据えた新たな地域医療構想〜医療費のピークと医療人材の確保に向けた制度改革〜
2025年を目標とした従来の地域医療構想が終盤を迎える中で、次なる転換点として注目されているのが2040年問題です。この年、日本の高齢化率はピークに達し、75歳以上の人口は現在よりもさらに増加。結果として、社会全体の医療・介護費用も過去最大に達することが確実視されています。
このような人口動態の変化を背景に、国は「新たな地域医療構想」の再構築に着手しています。その最大の目的は、医療資源を持続可能な形で再配置し、医療費の適正化と医療サービスの質を両立させることです。
病床数の見直しと機能報告制度の導入
新たな構想では、2027年を目処に病床機能ごとの必要推計を再提示する予定です。これは、2040年に向けた医療ニーズの変化を見据え、現在の病床配置や機能を見直す重要な作業です。また、医療機関機能報告により、自院の機能(高度急性期、急性期、包括期、慢性期等)や人員配置、稼働状況などを定期的に報告させることにより、地域における病院機能の適正配置や連携を促進します。
医療機関機能報告について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。↓↓↓
【医療機関機能報告】新たな地域医療構想に向けて未来の自院を創造(想像)する~今、病院は何をすべきか?~
医療人材の偏在とDX推進による対応
2040年に向けたもう一つの大きな課題は、医療人材の確保と偏在の是正です。地域によっては医師・看護師の不足がすでに深刻化しており、専門領域においても偏在が顕著です。特に、近年は医療従事者の一部が美容医療分野に流出する傾向も指摘されており、臨床現場の人材基盤が揺らぎつつあります。これらに対応するため、国は医療現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)化の推進にも力を入れています。電子カルテや遠隔診療の活用、AIによる診断支援、医療情報の地域間連携といった技術導入は、限られた人員でも一定の医療提供体制を維持するための不可欠な手段と位置づけられています。
2040年に向けた地域医療構想は、従来以上に「持続可能性」と「地域間の公平性」を重視した設計が求められています。医療機関にとっては、今後さらに詳細な病床機能の見直しや体制強化、人材確保戦略の再構築が不可避となるでしょう。

在宅医療と『エンディング』について考える
医療費が国家財政を圧迫する中、国としては医療費の削減が急務となっています。そのために、在宅医療の推進や地域包括ケアによる在宅復帰支援により、病床数の適正化や医療資源の適正利用が図られています。しかし、制度を整えるだけではじゅうぶんとは言えません。
高齢者が高いQOL(Quality Of Life)を維持しながら自宅で余生を過ごせるようにするには、本人とその家族の意識改革も必要です。早いうちからエンディングについて家族で話し合い、本人や家族の心の準備を整えておく必要もあります。
医療の逼迫や医療費の増大を少しでも軽減するためには、制度の改革だけでなく、このような国民全体の意識改革も進めていく必要があるのです。
地域医療の課題と病院経営
今回の記事では、医療における2025年問題と2040年問題、それに対応するための地域医療構想について考えました。超高齢化社会の到来で、医療機関の逼迫や介護・医療費の膨張など、解決しなければいけない問題は山積みです。
また、地域医療においても、
- 病院へのアクセスの問題
- 医療者の不足問題
- 自治体の財政力の問題
など、様々な課題があります。
こうした中で、病院単体での対策はもちろんのこと、地域全体としてどのように医療を維持していくかを考える必要があると言えるでしょう。具体的な成功事例についてお知りになりたい方や病院の経営改善についてご相談になりたい方は、リージョンマネジメント株式会社にお気軽にお問い合わせください。