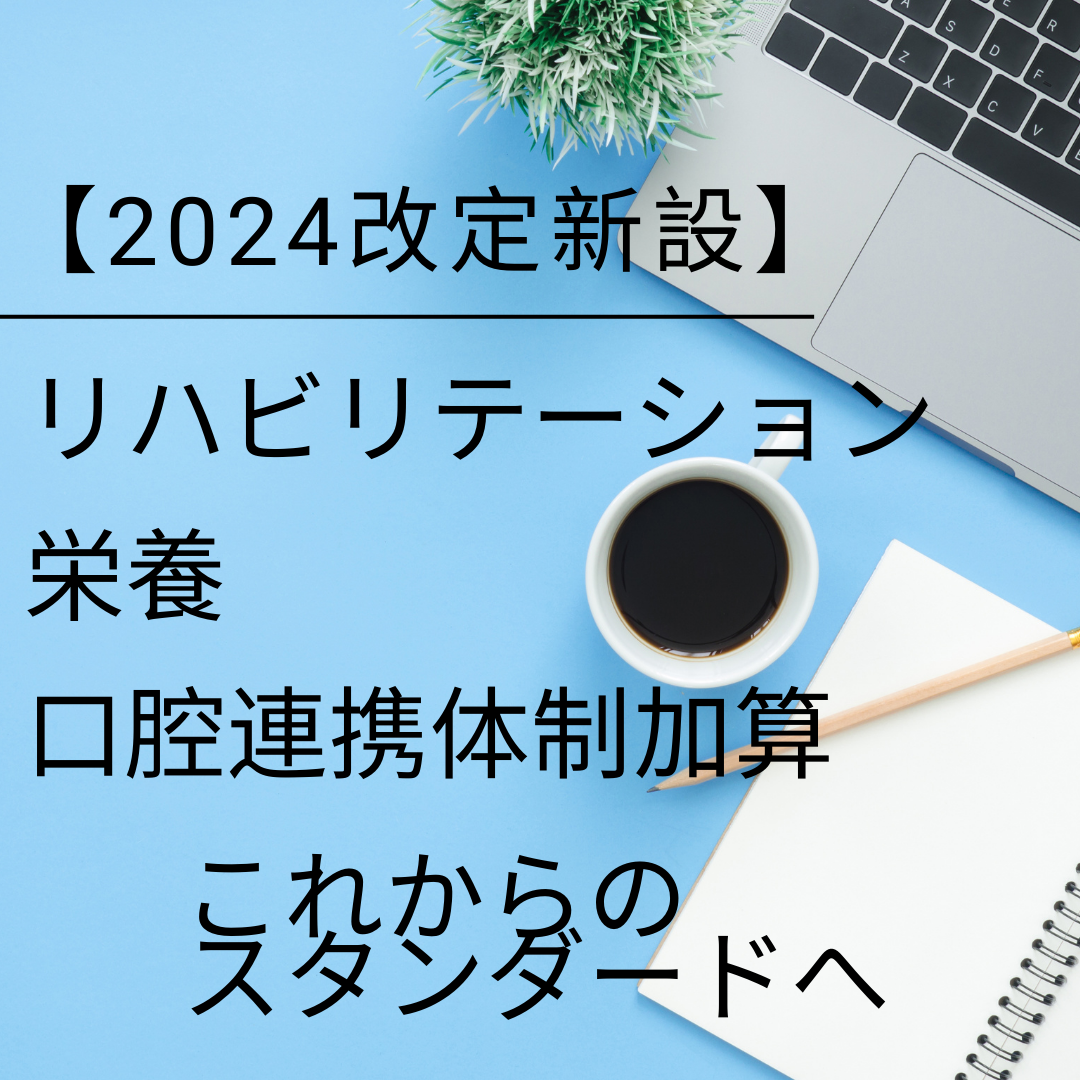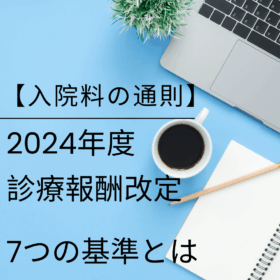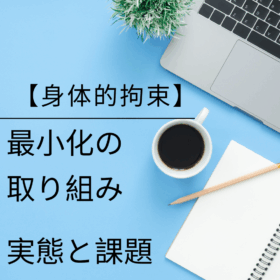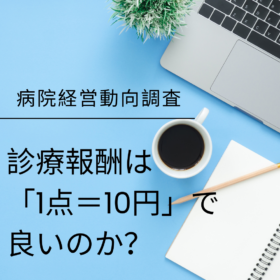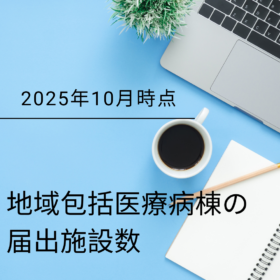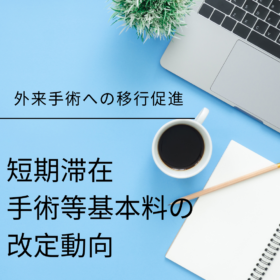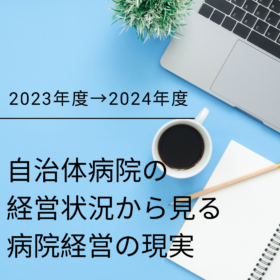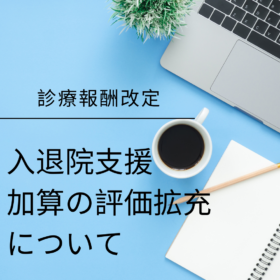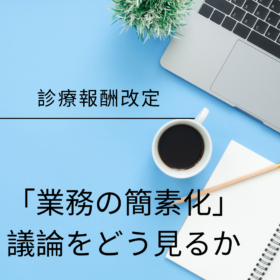Contents
はじめに
2024年度の診療報酬改定では、急性期入院医療の質をさらに高めるために「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(A233)」が新設されました。これは、急性期においてリハビリ、栄養管理、口腔ケアを一体的に提供する体制を評価する加算であり、単なる点数の新設ではなく、「寝たきりをつくらない医療」「急性期からの多職種連携」*を推進する大きな転換点といえる内容です 。
本記事では、この加算の目的や算定要件、背景にある考え方を整理しながら、現場の看護師・医療従事者にとってどのような意味を持つのかを考えていきます。
YouTubeでも解説していますので、是非、ご覧ください。
加算の目的 ― 急性期からのADL維持と経口摂取の促進
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の最大の目的は、急性期入院患者のADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)の維持・向上を図り、早期離床や経口摂取を促すことです。これまでは「疾患の治療を最優先」とするあまり、患者が急性期治療を終えて転院した時点で廃用症候群や低栄養、口腔機能の低下を抱えてしまい、慢性期病院や在宅での回復に長い時間を要することが少なくありませんでした。この加算の新設は、その問題を正面から捉え、「急性期から寝たきりやサルコペニアをつくらない」「治療と並行して機能を守る」ことを評価する枠組みです。
算定対象と点数
対象は 急性期一般入院料(7対1・10対1)の病棟 です。病棟単位での届出が必要であり、専従リハビリ職員や専任管理栄養士の配置が前提となります。
点数:1日につき120点
算定期間:計画作成日から最大14日間
(入棟後48時間を超えて計画を策定した場合でも、入棟後3日目を起算日とする扱い)
施設基準 ― 多職種の配置と質の担保
加算を算定するためには、病棟に以下のような体制を整える必要があります 。
- 専従リハビリ職員の配置:PT・OT・STを2名以上配置(うち1名は専任でも可)。疾患別リハ担当との兼務は不可。
- 専任管理栄養士の配置:病棟ごとに1名以上。栄養管理に専念する体制を整備。
- リハ経験を持つ医師の配置:3年以上の経験と包括的研修修了が要件。
- アウトカム評価の導入:
-
-
-
- 入棟後3日以内にリハ算定患者割合が8割以上
- 土日祝日のリハ提供量が平日の8割以上
- 退院・転棟時のADL低下が3%未満
- 新規褥瘡発生率が2.5%未満(または患者80人以下の病棟では2人以下)
-
-
- 脳血管・運動器リハ料の届出、入退院支援加算1の届出が必要
- BI研修の開催:年1回以上、職員を対象にBarthel Index(BI)測定研修を行うこと
この施設基準は、単なる人員要件にとどまらず、プロセスとアウトカムの両面で「質」を数値化して示すことが強く求められています。
算定要件 ― 計画・カンファレンス・記録の徹底
算定にあたって病棟が取り組むべき要件は、次のように整理されています 。
- 入棟後48時間以内に計画を作成
リハ・栄養・口腔管理を統合した計画を患者全員に策定し、退棟時も含めて評価・再評価を行う。 - 定期的なカンファレンスの開催と記録
多職種が参加し、患者ごとの状態を共有。記録を診療録等に残す。 - 適切な口腔ケアの提供
必要に応じて歯科医師と連携し、診療や受診を促す。 - 診療録への要点記載
栄養・口腔・リハの取り組みを簡潔に記録する。 - 非リハ対象患者への支援
疾患別リハの対象外でも、ADL維持・向上を目的とした指導を行う。
さらに専任管理栄養士については、GLIM基準を用いた栄養評価や、食事観察(週5回以上)、カンファレンスでの食事調整の提案が義務付けられています。
背景にある考え方 ― 「多くの寝たきりは急性期で作られる」
この加算の背景には、「多くの寝たきりは急性期で作られる」という強い問題意識があります 。慢性期病院の現場では、急性期から転院してきた患者が低栄養やサルコペニア、廃用症候群の状態にあり、数か月単位で回復に時間を要する例が多く見られます。こうした患者が減少すれば、慢性期病院では疾患治療により集中でき、結果として在院日数の短縮や医療資源の効率的活用につながると期待されています。つまり、急性期病院が責任をもって「ADLを落とさない状態で次につなぐ」ことが、医療システム全体の質と効率を高めるのです。
看護師にとっての意味
この加算は、リハ職や栄養士、医師だけでなく、看護師にとっても大きな意味を持ちます。看護師は患者の食事や口腔ケア、離床支援、ADL評価の場面で中心的な役割を担っています。
- 食欲の低下や食事量の変化を日々観察する
- 口腔清潔や嚥下状態の変化を把握する
- ベッド上安静から早期離床へつなぐ支援を行う
- カンファレンスで情報を共有し、栄養士やリハ職へフィードバックする
こうした日常業務の一つひとつが、加算の算定根拠になり、病院全体の評価へ直結していきます。
さいごに
今後、この加算の届出状況や急性期から転院する患者の状態、療養病棟でのリハ効果や在院日数の変化などが検証されることになります。慢性期医療の現場では「急性期からのADL低下が減れば、その後の回復もスムーズになり、結果的に地域全体の医療が効率化する」と期待する声が上がっています 。
また、厚労省が進める「地域包括ケア」の流れとも合致しており、急性期から慢性期、在宅へとつながるシームレスな医療の実現に向けた重要な一歩といえるでしょう。リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、急性期病棟に「多職種連携によるADL維持と経口摂取の促進」を求める新しい仕組みです。リハ職、栄養士、医師だけでなく、看護師の日々の観察と介入が大きな意味を持ち、患者にとっても「寝たきりをつくらない医療」への期待が高まります。